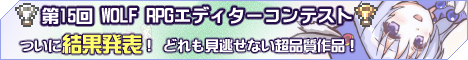第15回ウディコン全作品レビュー
前書き
注意
- このレビューは、筆者個人の独断と偏見によって書かれています。筆者の好みが多分に影響していますことをご了承ください。
- 出来る限り気を付けていますが、一部ネタバレを含む可能性もあります。問題がある場合は、プルリクやTwitter等にてご指摘いただけると助かります。
- レビュー内容は主にプレイ当時のバージョンに基づいています。最新バージョンと動作などが異なる場合がありますが、ご了承ください。
初めに
WOLF RPGエディターコンテスト(ウディコン)は、ウディタ製のゲームを競う、年に一回開催されるコンテストです。
第15回となる今年は、60作品ものゲームがエントリーされました。製作ツールがウディタであれば後は問わないというコンテストであるために、それぞれジャンルも異なれば雰囲気も異なる多種多様な作品が出展されており、様々なゲームを楽しむことができる場となっています。
今年は全作品クリアしつつ、熱中したり感動したり夜を更かしたりと楽しめましたので、ささやかな返礼としてプレイ作品のレビューをしていこうと思います。
なお、筆者は漫画でいえばARIAが好きで、最近の推しなら淡海乃海で、小説でいえば米澤穂信さんが好きで、好きなゲームはFF10で、最近やったゲームではHades、コロぱた、端木斐异闻录あたりが好みです。プレイ時間で言えば、未だにスマブラをやりすぎています。前回のウディコンで一番好きだったのはメトロノームファイトです。
加えて、筆者自身はゲームプログラマーを生業としています。その辺りを評価から差っ引いて考えると、より公平に感じるかもしれません。
ネガティブな感想を見るのが不快という方は、こちらのボタンを切り替えてください。ネガティブな感想を含む項目が隠れます。
補記。投げ銭もあるので開催者の方に遠慮なく還元していきましょう。
凡例
良かった点
- 筆者が良かったと思う点を書き連ねています
気になった点
- プレイ中に気になった点を書き連ねています
- 必要ない方は上記のボタンを押して消してください
レビュー
- レビューの文章を書いています
感想
- ネガティブ/ポジティブにかかわらず感情側に寄った感想を書きます
- より直截的な表現およびネタバレが多いので、基本は非表示にしてあります。読みたい方だけ都度ボタンを押して読んでください
- ここの文章の推敲は甘めです、不適切な表現があるかもしれませんがご了承ください
レビュー
01. 零落と紺碧の海神

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ノンフィールドRPG+ADV | 冒険者@シロヰ |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 20分 | 1.00 | クリア |
良かった点
- ジュブナイル然とした良いシナリオでした
- ノンフィールドパートはサクサクと進行して良かったです
- 相互のパートがテンポ感を失わないように上手くバランスを取っていました
気になった点
- アイテム枯渇後に3連戦など、やや苦しい運を引くこともありました
- ゲームオーバーが本質的にないので致命ではありません
レビュー
ある夏の物語
零落と紺碧の海神は、ジュブナイル然としたストーリーが楽しめるノンフィールドRPGです。
二度とは訪れない19歳の夏、『僕』こと蒼海は自転車のカゴに自由帳を放り投げ、荷台に幼馴染の彼女を乗せて、ペダルを漕ぎ始めます。あの磯臭い海へと向かい、未練を断ち切るために。
| 戦闘パート |
|---|
彼の道程はノンフィールドRPGとして表現されており、道中では空想の敵と遭遇したり、アイテムを拾ったりといったイベントが発生します。拾得したアイテムを上手く使って敵を倒していきましょう。
ただし、各アイテムにはそれぞれ耐久値が割り振られているため、戦闘における使用アイテムの選択や、拾ったアイテムの取捨選択が必要になります。上記の戦闘シーンで言えば、無限に使える自由帳は攻撃力が低い一方で、火力の期待値が高いステップアックスは12回までしか使えません。
これに加えて、耐久消費を増やす代わりに右クリックで強い攻撃をしたり、特定条件を達成することでアイテム取得などの恩恵を得たりといった要素もあるため、これら全体のリソース管理が上手く敵を倒していくカギとなるでしょう。
そうしてイベントを起こしつつ、ペダルを漕ぎ進めることで少しずつ物語が進行していきます。
次第に海に近づいていく二人とそれが表す意味は、99km地点に辿り着くことで明らかとなるでしょう。
なお、ノンフィールドRPGパートにおいてはゲームオーバーがないため、ストーリーのために厳密にクリアする必要はありません。極端な話をすれば、会敵したら即逃げるというのでも構いません。
しかし上手く攻略していくとポイントが加算されていき、このポイントによりオンラインランキングが作られています。我こそはという方は挑戦してみましょう。
青い空、入道雲、海、ひまわり、そしてソーダと、爽やかに夏をモチーフとした本作品は、けれど決して爽やかなだけではないテーマに立脚しています。しかしその読後感は、抜けるような青空さながらに清々しいものとなっていることでしょう。
青春の柔い成分を摂取したい方にお勧めの作品となっています。
感想
「咳をしても一人」とは尾崎放哉の句ですが、何とはなしに感じたのは尾崎豊の「卒業」でした。尾崎繋がりですね。
シチュエーションとしては等しく孤立したものを感じるところではありますが、尾崎放哉が晩年というどん詰まりで詠んだそれに対し、この物語はある種の始まりでその表現が使われるあたりは良い対比ですよね。だからこそに、この支配からの「卒業」とも感じたわけですが。
また、支配と一口に言っても、この物語はムラという支配の他に、自縄自縛の自身から生み出された世界からの支配も存在しています。この内的要因があるゆえに、物語がただ家出をすればいいというものでなくなっているのが美しいです。ムラにまとわりついた自己の一面との決別ですね。
また楽曲の話をするんですが、たまゆらという作品のED曲である「神様のいたずら」の歌詞に「いちばん大切なものだけをどこかに置き去りにさせてぼくたちを大人にするんだ」という一節があります。
彼にとって紺碧の色は大切であったろうし、この空想もまたかけがえのないものだったのだろうけれど、主人公はこれを置き去りにしていきます。何故ならば、紺碧の色は暗い影を落とすムラと分かちがたく、空想は子供の特権であるがゆえに、その代表である彼女は置き去りにしていかねばならないから。
加えてこの作品ではそれを忘れゆくものとしているのは興味深いところで、より強い離別の意思を感じます。それがムラとの絶縁を意味するのか、海神の生まれ変わりという立ち位置からの脱却を意味するか、あるいはその両方なのかは分かりませんが。
つらつらと自己解釈を書いてきましたが、何が言いたいかというと、そういった曲群を想起させるような琴線に触れたシナリオだったという話です。みんなも読もう。筆者個人がインスタントバレットを始め、青春の柔い部分が好きであることを差っ引いても良い作品だったと思うので。
こういう空気感の作品の熱量というか感性は、なんとなく年を経るごとにどんどん鈍麻していくのかなと勝手に思っているので、描ける寿命も短ければ読める寿命も短いんじゃないかと思っています。今がチャンスだ。
シナリオ面については、清々しいほどに夏のモチーフが入っているのも特徴ですね。海、青い空、ソーダ、白いワンピース、ひまわり、これで麦わら帽子があれば数え役満だったかもしれません。何ならどこかで麦わら帽子を幻視していた可能性すらあります。
後はシナリオの細かいところを話すと、ちゃんと序盤に感じた口調の違和感とかを最後に回収してくれるのは良いですよね。
終盤の展開については、空想ともいえるし、海神の思し召しともとらえられるかなと思っています。母親が身を投げたそこからすべてが始まっているので。ただそれを認めてしまうと、その行為自体に意味があったように思えてしまうので何とも難しい所ではあります。
そろそろゲーム性の話をします。
ノンフィールドRPGを中心にシナリオを乗っける手法はヒュプノノーツを始め色々とありますが、このゲームは一本道であることをシナリオ面でも意味づけていたなあと感じていました。この一本道というのは、原則ゲームオーバーのない仕様も含んでいます。
ペダルを漕いでいる彼らにとっては空想の中の敗北には特別に意味がなく、ただ終わりに向かって進んでいるという強い印象付け。それと不可逆である意味が強いシナリオとの親和性はかなり高いなと思っています。
そういう意味では空想の戦闘はある種のおまけではあるんですが、それでもアイテムの取捨選択や耐久を2倍消費して火力を上げる仕組みなど、色々と考える要素はあるのでゲームとして成立しています。
このゲームとして完成されているというのは大きく――それらがテンポ良く機能したということも併せて――、ノベルパートと交互に来ることで飽きさせない作りになっています。
ノベルパートについてもオープニングとエンディング以外はかなり短めに収められていて、サクサクと進められるのも好印象でした。オープニングがやや長いのは必要経費くらいの感覚です。
一方でゲームバランスとしては、敵との連戦の後にアイテムを大量に取得するようなことが度々あったので、やや運に左右されるかなという印象はありますが、基本的に敗北ペナルティは薄いので気にはなりません。スコアアタックをやるなら吟味がいるのかもしれない。どちらにしてもダメージ計算自体でさえも強く運にからむものなので、あまり厳密にやるものではない印象を受けています。
また周回自体はさほど長いものではないので、取捨選択の見直しも踏まえて、ある程度の運を期待して再プレイすることもできそうです。
ちなみにこれは余談中の余談ですが、タイトルを見た時にデュエルマスターズのレインボー呪文にありそうな名前だなと思っていました。水/闇のコスト7くらいの。クリーチャーかもしれない。
最後に、これがウディコンのエントリー番号1にあったのは個人的には好きでしたし、価値のあることだったなと感じています。最初に手を付けた後、爽やかな気分になれるので。
02. 少女大猩猩 -その猩猩、凶暴につき-

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ゴリラアクション | 餓鬼郎党 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 30分 | 1.00 | クリア |
良かった点
- ゴリラメタモルフォーゼがAにも割り当てられることで押しやすくなりました
- ゲージが導入されゲーム性が生まれています
- ゴリラ時のイベントなど細かいところも作られていました
気になった点
- セーブ時の選択枠が見にくい印象を受けました
- 背景の明滅か、枠そのものの色がもう少し変化すると分かりやすくなりそうです
- マップチップの上下設定ミスがやや見受けられました
レビュー
ゴリラメタモルフォーゼ
少女大猩猩 -その猩猩、凶暴につき-は、ゴリラメタモルフォーゼを駆使して障害となる敵をなぎ倒していくゴリラアクションです。
ゴリラに変身できる高校生、森谷稟がある悲鳴を聞いたところから物語は始まります。
プレイヤーはゴリラのGあるいはAボタンを押すことで、任意のタイミングでゴリラに変身することができます。ゴリラは霊長の王であるため、ひとたび変身してしまえば、敵も障害物も触れただけで立ち所に全て吹き飛ばされていきます。バッタバッタと敵をなぎ倒していきましょう。
| ゲージ回復中 |
|---|
しかし、ゴリラになるにはGP(ゴリラパワー)ゲージが必要です。これはゴリラになっている間に消費され、人間の間に回復していきます。このゲージが0になると強制的に人間に戻ってしまうほか、最大でないとゴリラメタモルフォーゼはできません。
敵を倒すことに夢中になっているとゲージが枯渇してピンチになることもあるため、適宜人間に戻って逃げ回る必要があります。なお、人間はか弱いので敵に触れると立ち所にゲームオーバーになります。
このようにゴリラと人間を使い分けていき、迫りくる危機に対応していきましょう。
困ったらゴリラメタモルフォーゼです。
感想
このゲームを初めて見た感想は、「あ、あの少女大猩猩に続編があるんですか」でした。確かに続編作れそうな終わり方をしていましたが、よもや来年見ることになろうとは思ってもみませんでした。エントリーしているのを見て、一番笑みがこぼれた作品かもしれません。
前作で気になっていたGキー押しにくいかもしれないという話に対して、Gキーを外さないこだわりを残しつつ、Aキーが使えるようになっているのは嬉しかったです。位置的にも押しやすいですしね。Appearの略という、Military Operation Organization Guidance / Logistics Expert くらいの感覚の設定がありますが、ともかく押しやすいのが良いです。
また、前作においてはギミックで解除する以外は実質的な無敵性能を持っていたゴリラメタモルフォーゼに対し、ゲージを設けることで上手く異なったゲーム性を付与しているのも面白い所でした。
前作では敵との戦闘においては蝶ギミックのようなものでないと敵の勝ち筋がありませんでしたが、今作ではちゃんと逃げるフェーズがあるので別軸の楽しみ方があります。無双パートとその準備段階みたいなイメージです。『魔法少女は自由に変身できない。』が類型かもしれませんが、ゴリラという唯一無二性と、ゴリラであるときの細かいイベントなどの作り込みが良い味を出していました。
後は、はにわを探して隠し通路があるなどのところも細かい作り込みですね。オマケ部屋ではゴリラで掃除できるみたいな小ネタも好きです。
また、ゴリイチゴが無くても無双できるように見えながらも、ちゃんとラストはゴリイチゴを使いたくなる敵が出てくるあたりのレベルデザインも良く出来ています。短編でちゃんとゴリラメタモルフォーゼをマスターできるようなデザインになっているのが良いですね。ゴリラメタモルフォーゼをマスターって何だ。
なお、マップチップの上下設定ミスというのはつまり以下のような感じですが、意図して突っ込まない限りそんなに目立つものではありません。ゴリラメタモルフォーゼして突っ切ってればそんなに気にはなりませんね。
そもそもゴリラメタモルフォーゼするとさらに大きくなるので、それで整合性を取ろうとすると結構難しいのかもしれません。
![]()
セーブ枠については割と気になっていて、祟女の方では気になっていないのでウィンドウの標準色の問題かなと思っています。枠の明滅が分かりにくいのもあるんですが、背景が明滅するほうが分かりやすい度合いは上がるかなという印象でした。
20分の短編で大量にセーブ分ける変人がどれくらい居るかは知りませんが。
今年のゴリラ成分は多分これを含めて大体2作、細かいところを含めればもっとあるので、十分なゴリラ分と言えるかもしれません。来年のゴリラはいったいどんなゴリラになるんでしょうか。
03. 祟女 -TATARIME-

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ホラーADV | 餓鬼郎党 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 25分 | 1.00 | 全END |
良かった点
- マップが短編に則って最小限に構成されていました
- 主人公に同情したくなります
気になった点
- 特にありません
レビュー
前門のストーカー後門の幽霊
祟女 -TATARIME-は、ホラーテイストのADVです。
最近一人暮らしを始めた主人公タミオは、幼馴染で付きまとってくるオカルト好きの少女ミサオにその部屋が呪われていると忠告を受けます。その呪われた部屋を舞台に、物語は展開していきます。
システムとしてはオーソドックスな短編ADVであり、迷うようなことはなく最後まで読み進めていくことができるでしょう。
そうしてADVとしてホラー展開が続く中、主人公が迎える結末は3つに分岐していきます。どの結末を迎えるかは、あなたの選択次第です。
感想
始終主人公がかわいそうだなあと思ってプレイしていました。特別悪いことしてないのに。友人がそこそこ薄情なのもかわいそうさに拍車をかけているんですが、付きまとっている人物が人物だけに仕様がない面もありそうだなという印象があります。
個人的には友人の先輩の話というのすら本当か疑わしいのかなと思っていて、操が何かしら吹き込んだのかなという疑いを持っています。これはTRUEエンドルートの話で、昏睡ルートの場合はまた話が変わってきますか。
そもそも、TRUEのルートと昏睡のルートが全く同じ世界線だとすると、なんで昏睡するのかがいまいちわからないのも気になります。よしんば昏睡したとしても、操が去る理由が一番良く分からない。何かやりすぎたんでしょうか。
なので、個人的にはそれぞれ別の世界のお話ということで頭の中では決着をつけていました。もしくは本当の幽霊もいたんですかね。ベランダ行くとちょくちょく見えたり、風呂場のゲームオーバールートがあったりするので。
ちなみに一番驚いた上で笑ったのは操がEDを飾るシーンで、ある意味オチに相応しい存在だなと感じ入っていました。ある意味では幽霊より怖いですからね、この人。ジャンプスケアとしては怖がるべきなんでしょうが、若干面白さが勝つ不思議な感情でいました。
ゲームとしてみるとマップの構成が最小限度なのが良くて、本当に必要範囲以外は無駄に作られていません。おかげで、無駄なくADVを楽しめます。それでいてベランダや風呂場の小ネタといった、ちゃんとホラー要素にかかわるところは抜け目なく用意されているあたりの芸の細かさもあります。最小構成ではあっても最低限度ではない感じ。
なお、地味に少女大猩々とのコラボというかクロスオーバーがあり、プレイ順でこちらが後だと微妙なネタバレを食らいます。ただ、ネタバレを食らったとしても何でそうなるか気になるので、むしろプラスにしか働いていません。操というキャラの強さが出てますね。
04. Forcelagoon2 因果律の少女

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ファンタジーRPG | レイディース |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 16時間+1時間 | 1.38 | クリア/組手完了 |
良かった点
- コインやアイコンを用いた誘導が常に丁寧な作品でした
- オリジナルのグラフィックで世界観やキャラクターが生き生きと表現されています
- キャラクター同士の会話劇により各々の魅力が増幅されています
気になった点
- ヒールに対する攻撃魔法や、下位魔法と中位魔法について、消費MPとのバランスがやや悪く感じました
- 上位を習得する終盤まで来ると、大きく気にならないレベルになります
- 地名表示に文字送りが必要なため、微妙にテンポを削ぐところがあります
- 地名自体は世界観を表す雰囲気として良いので、ピクチャなどを利用してモーダルっぽい動きにならなければ良いなと思っています
レビュー
掛け合いが楽しいRPG
Forcelagoon2 因果律の少女は、ファンタジー世界で因果をめぐる冒険が繰り広げられる長編RPGです。
主人公であるベヨネットは、ある時から見知らぬ少女の助けを呼ぶ声を夢に見るようになりました。その少女との因縁が、やがて大陸を越え世界中を巻き込む壮大な因果へと繋がっていきます。
ゲームとしては極めてオーソドックスなRPGであり、世界を巡って冒険していきながら敵と戦って物語を進めていくことになります。
その中でも特徴的なのは、レベルアップにより上がるステータスがHPとFP(MP相当)のみというシステムになります。このため、どれだけレベルアップしたとしても、その他の基礎ステータスはすべて武器や防具に依存することになります。その時々で上手く装備を取り換えつつ、効率よく敵と戦っていきましょう。
そうしてゲームを進めていく中で、ベヨネットは様々なキャラクターと仲間になっていきます。どのキャラクターも個性豊かであり、それぞれが思いをもって彼女の冒険に同行してくれるでしょう。
そんな仲間との掛け合いは、各所にある絆の種と呼ばれる地点を調べると見ることができます。キャラクター同士の関係性や世界のことを知りたいのであれば、積極的に見ることをお勧めします。
当然、仲間は戦闘においても心強い味方となります。それぞれには独自のスキルが存在し、これを上手く活用していくことで戦いを有利に運ぶことができます。パーティーの編成はいつでもできるため、適宜好きなパーティーや相性の良いパーティーで、ダンジョンや強敵に挑んでいきましょう。
主要キャラクターや敵グラフィックを始めとし、NPCまでもがオリジナルのグラフィックで描かれたこの作品は、魅力的なキャラクターの会話劇も相まってユニークな世界をいかんなく表現しています。
そんな世界の様々な地を渡り歩き、個性豊かで魅力的なキャラクターを仲間に加えて、はるか昔からの因果に決着をつけていきましょう。
感想
まずは20時間級のファンタジーRPGをシナリオ付きでまとめきったことに賛辞と感謝を述べさせていただいて、そこから感想に入りますね。
この規模となると戦闘バランスの調整、シナリオの不整合の確認、山とオチの配分、フラグ管理の整備、システム面での頑強化とか諸々の障害が立ちふさがるんでしょうが、それらを全て解決してこの精度で完成させたというのが凄いです。
とりあえずゲームシステム面について。
誘導をコインでこなすのはアクションではよく見る手法ですが、RPGでやっているのは初めて見たかもしれません。特に前半においてはプレイヤー利益の塊なので、良いシステムだなあと思っています。中盤だとさすがにそんなに利益はないんですけど、何となく取ってしまう魅力もありますね。
加えて、アイコンによる誘導がかなりちゃんと整備されており、話を若干忘れてしまっても進行に影響があまりないようになっています。特にこのレベルの長編となると一息にクリアするのが難しく、どうしても中断を挟んでしまうので、このシステムは大変ありがたかったです。やるべきことが思い出せる。
また、シンボルエンカウントの採用がなされているのも良くて、こちらでダンジョンのエンカウント率を調整できます。
戦って稼いでおきたいなら積極的に当たりに行きますし、そうでないなら上手く避ける楽しみもあります。マップによっては回避が難しいところもありましたが、多くは避けられるレベルになっているのも配慮がありました。
同じエリアにもう一度入り直すことも少なくない長編として、この辺の雑魚戦を無駄にやらせない配慮があるのも良いところです。
一方で、上述している地名表示に文字送りがあるのは若干移動のテンポを削いでいる印象がありました。
地名表示の雰囲気作り自体は大事なのかなと思っているので、プレイヤーの操作を奪わないのが理想なのかなと感じています。雑なイメージだと下記みたいな感じ。
フェードアウトまで勝手にやれば大体のケースで邪魔にならないと思いますが、上下で移動するマップだとたまに被る可能性はあります。難しい。
![]()
また、物凄く細かい上に好みのわかれるところとして、セーブの際にいちいち休憩を開く必要があるのがやや手間を感じました。
工程が一つ増えているだけではあるんですが、セーブ地点が用意されていると要素として分離できそうな印象はあります。世界観的にどうなんだという話はありそうですが。
最後の細かい点として、キャラクター編成時にメニュー画面上で変化がないことがうっすらと気になっていました。装備の付け替えとかをやり始めるとキャラクター自体は変わっていることが分かります。
多分メニューの更新が走ってないんだと思うんですが、ここでメニューを閉じる仕様とかにすると利便性を著しく削ぐので、可能なら即座にキャラクターの見た目の繁栄もされて欲しいなとは感じています。
続いて戦闘について。
戦闘バランスは全体を通してかなり良好で、様々なキャラクターを使い分けることが可能にもかかわらず、常に良いバランスで戦えました。
レベルはHPなどにしか影響がなく、装備で能力値がカスタマイズされるというのが良くて、装備の性能で上手く味方側の能力を調整していたのかなと感じています。
さすがに終盤になると装備が充実しすぎて回避100のタンクという最適解に落ち着きはするんですが、それでも攻撃側を詰めるなどの考えは残るので最後まで楽しむことはできました。
| 回避100のタンク (状態異常対策も完璧なので必中以外は脅威じゃない) |
|---|
個人的にやや気になったのは中盤くらいの味方側のバランスで、中級魔法と初級魔法の間に消費MP比の火力差が出ていませんでした。これによりあまり中級魔法を使う機会がなく、初級魔法でちまちま削ることになるケースが多かった印象です。
加えて、ヒールの消費MPに対して攻撃魔法の消費MPが割高なのも影響して、魔法使いがMPを使って攻撃参加するよりMP消費を抑えてヒールしてもらう方がコスパが良くなってしまっている印象もありました。
もしかしたら、中盤はFP回復手段がそれほど潤沢に用意できないからこういう感想を抱いている可能性もあります。
終盤になってくると、敵の攻撃も強く、加えて固くもなっていることから上級魔法を使うモチベーションも増えてくるため、このあたりについては完全に中盤に限った話になります。
なお、終盤でもコスパを考えるとテレシコアがメガリバースした上で回復したほうがコスパが良いきらいはあるものの、こちらはリスクを取っていてかつコンボ技っぽいのもあってあまり気になってはいませんでした。
なお、このあたりの話はあくまで雑魚戦で中級魔法を使うモチベーションがないというだけで、全体を通した戦闘バランス自体は中盤でも良好に感じていました。上手く戦略を組み立て、各キャラクターの役割を機能させて戦うボス戦や強敵戦は歯ごたえがあって好きです。
あと個人的に好きなところは、前半は普通に殴る技が強く、中盤になると低コストで防御貫通できる弓に魅力を感じ、終盤になるとバフを乗っけた火力を好むようになるという変遷です。この当たりの火力の取り方の移り変わりが、上手くグラデーションしているような感じがありました。
やや戦闘の話から外れますが、ボスの好きな点としては戦闘前のカットイン演出もあります。こういうのがあるとテンションが上がりますね。
最後にめちゃめちゃ細かくて好みの話をすると、 敵の状態異常がメッセージでしかわからないのは若干辛めではありました。可能ならアイコンが欲しく、できれば継続ターンも欲しいですね。
続いて、シナリオとかキャラクターの話をします。
シナリオは一本筋の通ったハイファンタジーという感じで、この長編を最後まで貫き通す一本の柱として機能していました。謎の少女とその因縁を軸としつつ、上手く中心となる話題を入れ替えていきながら、最後までシナリオの牽引力を持たせています。
まず大前提として、このベースとなるシナリオが骨太に機能しているからこそ、以下で話す枝葉のキャラの関係性を成り立たせる会話パートが上手く働いているという面があります。
キャラクターについては、物語が進むにつれて愛着が湧いてくるタイプです。具体的に言うならスキットを通して少しずつ人となりを理解していき、キャラクター同士の掛け合いによってその魅力が増幅されていくイメージです。終盤まで来れば大体のキャラクターを好きになっています。
なお、個人的に好きなのはガントスでした。あのナリと軽薄さを備えていながら、常識人大人枠なあたりが好きです。苦労人ポジションが好みなのかもしれません。
ただ、キャラクター同士の掛け算で魅力が増していくタイプの良さをしているので、キャラクターの元の魅力値が分かっていない序盤ではまだキャラクターに魅力を感じにくいです。なので、どうしても立ち上がりよりは終盤のほうが面白いと感じてしまうゲームでもありました。レジギガスみたいな感じ。
全体16時間の私のプレイ時間のうち、すごく面白くなってきたなと感じたのは12時間時点くらいでした。そこから先は止まりませんでしたね。最後までやれば間違いなく面白いしキャラクターを好きになれるとは思うんですが、フックとしては弱いのかもしれません。
ただ、キャラクターが揃ってきた頃から始まっていく、相互にキャラクターを立たせ合うその関係はまさに関係性の神砂嵐みたいな感じがあります。つまりこれ。
この辺のキャラクター同士の関わり合いは本当に良くて、エンディングまでちゃんと機能しています。何より、全員に愛着が湧くからこそ、最後にみんなで集まって敵を囲むシーンには熱いものを感じられました。
余談ですが、エンディングのグラフィックは立ち絵のそれに比べて解像度が高く、おかげで色々と知ることができました。個人的にはリク君が思ったよりイケメンなことに驚いていました。
特に立ち絵だと省略されたディティールが描かれているのが良かったですね。
なお、ここは個人差がある所かもしれませんが、折角ファンタジー然とした世界観を構成しているので、あんまりメタっぽいネタはない方が良いかもしれません。最初の最初に少しだけ離す程度なので気にならないレベルかもしれませんが。
あとは最後の話に入る前にめちゃくちゃ余談なんですが、宿屋で暗転が入る時に、おばちゃんがその前にいるので、暗転の中おばちゃんだけ見えているのが笑いを誘いました。なんかシュール。
最後に全体的な話を少しだけ。
最初にも触れましたがシナリオが一本通しつつ、10時間を優に超えるRPGを破綻なく築き上げているというのが素晴らしく、ここまでちゃんと作り込まれているなあと感じながら最後までプレイすることができました。
一切の手抜かりなく、徹頭徹尾RPGを遊ばせてもらえたのは感謝の念に堪えません。楽しかったです。
05. 怖がらないでよ僧侶さん

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 探索ADV | WeakRabbit |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 4時間 | 1.00 | 全ENDクリア |
良かった点
- 行動や選択肢に応じたバリエーションが豊富です
- 徹底的にいろいろなネタが仕込まれています
- 一度見たエンディング行きの選択肢を選ぶと適切な場所まで戻してくれるので周回が捗ります
- キャラクターの個性が良かったです
気になった点
- ややエンディング回収に対する諸々の導線は弱いです
- 良い意味での古典的ADVっぽいとも言えます
レビュー
めくるめく分岐ADV
怖がらないでよ僧侶さんは、様々な分岐を経て様々なエンディングを迎えるアドベンチャーゲームです。
魔王の部屋の目前までたどり着いた勇者一行は、そこで最大のピンチを迎えます。パーティの一人である僧侶が怖がってしまい、先に進めなくなってしまったのです。勇者であるリュウジを操って、上手く選択をして僧侶を説得し、魔王の元へと向かわせましょう。
プレイヤーが挑むのは、いくつもの選択肢とそれを踏まえた分岐です。豊富に取り揃えられた行動から様々な分岐を試し、様々な未来を迎えていくことになるでしょう。
その多様な選択肢に相応しく、そこから派生していくエンディングのバリエーションは多彩です。コメディ調の多種多様な終わり方を迎えながらも、僧侶を説得する道筋を模索していきましょう。
そして、そういった数多くの分岐に対し、とにかくリアクションが網羅的に用意されているというのが、このゲームの圧巻となります。たとえエンディングに関係ないような小ネタであっても、全てがケアされてネタを返してくれる設計となっているため、色々と試したくなること請け合いです。
なお、一度見たエンディングは直前の選択肢からやり直したり、最初からやり直したりといったことが可能なので、周回も容易となっています。気軽に様々なパターンを試していって、エンディングリストを埋めていくのも一興でしょう。
この作品は、強烈なキャラクターと強いコメディ色が人を選ぶように見えて、その実は様々なエンディングを経て物語として締めてくる王道の風格も湛えたADVとなっています。色々な分岐を巡り、物語の終わりまで突き進みましょう。
RPGで同じNPCに何度も話しかけるような人にお勧めの作品です。
感想
選択肢分岐型ADVに付きまとう組み合わせ爆発にものすごく対応されているADVです。
魔王の妄想で44パターン全て用意した上にコンプリートイベントがあるあたりからも分かる通り、とにかく遷移する分岐を網羅してネタが仕込まれています。
後半パートは本ルートでそれが発生し、手抜きENDと呼ばれているものが用意されていますが、これも全部名前変えたりネタが突然突っ込まれたりと手の込んだ手抜きを披露してきました。イベントがないだけで手抜いてはないんですよ。
そうして用意された各種分岐に対するネタの豊富さも凄まじく、選択肢ごとの行動バリエーションもかなり広めです。まず「アホなテンションでゲームを始める」かどうかから聞いてくるゲームは中々ありません。実質ゲームが始まる前から分岐が発生しています。
このアホなテンション、じゃあ通常のテンションはアホじゃないのかと言えば、通常のテンションでも十分にアホです。ただ、アホなテンションはそれを上回るアホなだけです。上には上がいるんですね。
加えてミニコーナーで漫才始めるし、エンド終わったら度合付けコーナーが始まるし、とにかくネタが詰まったゲームです。ハリ抜いたらケーンあたりで笑ってしまったのはある意味悔しいかもしれない。
雑談コーナーで誰を主人公だったかを何回か選んでいたら、順番まで考慮して話し始めた時はどこまでやってるんだこのゲームと思っていました。おまけにまでパターンが仕込まれています。
しかも、ただ分岐が用意されているだけではなく、その様々な分岐を効率よく巡れるシステムも良く出来ています。すでに見たことのあるエンディングに到達した時、直前に戻ることもできますし、最初の選択肢から始めることもできます。分岐チェックには前者、いったんリセットしたい時には後者が便利でした。
特に序盤におけるED回収は結構難しく、色々な分岐を当たっていく必要があるんですが、この仕組みのおかげで効率よく回ることができたように思います。
そうして条件を満たした先のシリアスルートともいえる後半ですが、シリアスルートっぽい始まり方をしておいてほとんどの場合はシリアスではありません。やっぱりコメディです。あのフリからまだコメディが見れるあたり、コメディの底が見えない。
しかしそういったコメディ調のEDすらも伏線めいた回収をしつつ、ちゃんとシリアスルートに合流させている手腕は剛腕と言って良いレベルでした。膨大な量のネタで押し流すことで伏線を巧妙に隠しています。
その中で最後のTrueへの道筋はこれまでのすべてを上手く合流させつつも、それぞれの芯というかアレなところは最後までブレさせていないのも好きです。
主人公は最後まで役立たずに近い状態でも、その中でやれることをやり切りますし、毒は毒ですし、ゲンは自分の最強の奥義にレイカさんの名前つけちゃう辺りにちゃんと気持ち悪さが残ってますし、レイカさんは何だかんだずっとレイカさんです。
それだからこそ最後のイベントバトルの一つ一つの行動に価値が与えられ、戦闘が物語として構成されているように感じます。最低のパーティ、言い得て妙でした。
各ENDの話もやっておきたいのでやるんですが、全部インパクトがあります。その中でも毒々サイダーあたりのプレイヤー置いてけぼり感が好きです。理解できない人たちが、理解できないことをずっとやっているカオスがそこにあります。漫才もなんだかんだ好き。
ノリそのものは人を選ぶと言って良いほど振り切れているとは思うものの、筆者は割とこのノリが好きなので大いに楽しんでしました。そもそもこのノリが好きでなければ魔王の44パターンを試しません。
その上で、この数多あるインパクトのあるENDに対してシリアスルートの特殊ENDが引けを取らないように、特殊演出を付けて差別化を図っているのも良いところです。明らかに空気感が違うというところも察せられますし、ちゃんと演出に入ったんだなということが分かります。
このゲームは狂人が多いですが、抜けているのは毒に見せかけてゲンなのかなと思っていました。No.13 のENDとか、端々にその片鱗が見えます。その根っこというか、回答編みたいなパートである彼の過去はそういう意味でも印象に残りました。
このゲームにおいては、レイカや毒は立ち位置的に、リュウジはメタ的な意味でも主人公というか主要キャラとして動いていますが、ゲンがその中では役割的には一つ後ろにいるところがあります。しかし、その分を補って余りあるインパクトで主要キャラに割って入って印象を残しています。素晴らしい気持ち悪さだ。
ADVとしての話をもう少しすると、前半は完全な選択肢分岐型にした上で、後半は探索とアイテム使用に近いプレイ感にきっちり分離しているあたりが作り込まれているなと感じていました。
前半と後半でプレイ感が違うので、シリアスルートに入ったなという印象以外でも新鮮な気持ちで取り組むことができます。この辺の丁寧さが最後まで徹底されているからこそ、安心してネタの濁流を楽しむことができるゲームです。
繰り返しになるかもしれませんが、後半パートも分岐による組み合わせはかなり用意されています。そして、その組み合わせ全てに対してちゃんと反応が返ってきます。
前半パートで数多の選択肢を通して培われた、何をしてもこのゲームはちゃんと先回りして反応を用意していてくれるという信頼感が、後半パートで探索を色々として見るモチベーションにもつながっています。ADVを楽しくやるには、何を調べても何かリアクションしてくれるだろうという信頼感って大事ですね。
ともかく後半パートまでが神髄なので、前半の分岐パズルを抜けて後半に辿り着いていただきたい気持ちはあれど、割とちゃんと分岐を追わないと入れないのが難しいところです。一応ゲーム外ですがヒントはあるので、多分後半パートに入るのはそんなに苦労しないはず。
06. メリカと野菜の剣士たち

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| デッキ構築ローグライト | サカモトトマト |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 2時間40分+3時間40分 | 1.01.0 | 全キャラクリア |
良かった点
- チュートリアルが手厚く、操作性も良好でした
- 初見でも突っかかりなく最後まで進めました
- デッキ枚数が固定かつ入れ替え自由のため、緩いデッキ構築ローグライクを楽しめます
- 能動的な不運を引かない限りは負けなさそうな良いバランスでした
気になった点
- タイトル周りのアウトゲームはややわかりにくい印象でした
- 主に要素解放周りですが、やっていくうちに慣れるレベルです
- 現状何が解放されていて、この解放にはどういった恩恵があるのかというのが不透明なあたりが一番気になっていました
- 通信待ちが明示的に入るため、体験にロスを感じました
- ウディタではできないのかもしれませんが、開発側のための情報収集は裏のスレッドで動かすのが体験に悪影響を与えなさそうです
レビュー
野菜を組み合わせてコンボを作ろう
メリカと野菜の剣士たちは、野菜をデッキに構築し、そのシナジーで敵を倒していくデッキ構築型ローグライトです。
伝説の野菜を求めて、パートナーと共に様々なエリアに挑んでいく構成となっています。
基本的な部分はノンフィールドRPGのような進行をしていきますが、戦闘面では野菜からなるデッキの構築が鍵となります。
エリアを進むと出現する雑魚敵や、最後に待ち構えるボスに打ち勝つためには、野菜同士のコンボを念頭に入れて上手くデッキを作っていく必要があるでしょう。
| 戦闘画面 |
|---|
戦闘では、まずデッキから野菜が5つ補充されます。この中から最大3つの野菜を選ぶことで、一ターンの行動が完了します。相手の行動は開示されているので、その行動や相手の体力なども加味して野菜を選んでいきましょう。
野菜には様々な効果がありますが、攻撃/防御の上昇と、SPの回復が基本となります。攻撃と防御はそのターンのダメージと被ダメージに影響し、SPは攻撃の度に消費されて0になるとピンチになってしまいます。上記の画像ですと、にんじんを食べればSPが10回復したうえで攻撃力が6上がります。一方で、斬撃という攻撃を行うため、このターンの終わりにSPが30消費されることになる、という次第です。
ただし、闇雲に野菜を与えていれば勝てるほど敵は甘くありません。そこで大事になってくるのが、野菜の特殊効果とそれを組み合わせたシナジーになります。
毎ターンそれ自体の攻撃力が3ずつ増えていく野菜に、そうして付与した効果を2倍にする野菜を重ねる、状態異常があるほど強い野菜に対して、自分が状態異常になる代わりに強い野菜を先に食べる、そういった自分なりのコンボを作り出していくのが肝要となってきます。
エリアのイベントでランダムで手に入る野菜から上手くピックして、その時々で強いコンボを生み出していきましょう。デッキが8つの野菜のみで成り立つことで回転率が良いのもあって、どんどんコンボを決めて楽しむことができます。
また、このゲームではエリアに挑む前にパートナーを選ぶこともできます。パートナーによってその特徴は異なるため、それぞれの性質にあった戦略を考えていくことも大事です。その人に合った野菜を模索していきましょう。
なお、デッキから外した野菜はロストせずに保持されるため、いつでも好きな時にデッキを組み替えていくことができます。
コンボしやすい野菜の性質、8つという少ないデッキ制限、いつでも見直せる構成など、あらゆる面で緩くローグライトを楽しむことができるため、デッキ構築型ローグライトに慣れていない方にもお勧めできる作品となっています。
感想
かなり緩めに振ったデッキ構築型ローグライトという印象です。カード制限による時々の取捨選択はなく、カード取りすぎてデッキが薄くなって弱くなることもありません。いつでもデッキを組み替えられるし、それぞれのシナジーを割と気軽に試せました。
その分難易度はだいぶ易しめになっているようには思うんですが、ラストダンジョンはしっかり難しいところも良かったです。まあこの調子ならいけるやろで進んでいたらボコボコにされました。最後がギミックボスとは思わなんだ。唐辛子はもらったそのターンに全部捨ててしまった。
後から実績の唐辛子の項目を見たらヒントっぽいのが書いてはあったんですが、クリア前にここは見ないので難しかったですね。
なおクリア時間は、ヨハンでクリアするまでに3時間弱で、そのあと全キャラクリアするのに4時間弱になります。ヨハンでクリアできたし、クレアなら2時間で行けるかなと思っていたら、想像より苦戦しました。クレアでの戦い方が苦手なのか勘所をつかめていなかったのか。
反対に、ペペロはものすごく手になじんで一度もゲームオーバーになることなく最後まで行きました。状態異常というデメリットをあえて背負って上手くコントロールするのが性に合っていたのか、たまねぎやにんにくを駆使してクリアまで漕ぎつけています。ある意味ではやるべきことが明確なので戦いやすいのかもしれません。
ローグライトとしての操作性は良好で、大体何をすれば何が起きるのかは分かります。
最初の内は慣れずにダメージ表記を信用しすぎて微妙に足りなくて焦ったり、さっき使った野菜を何故か忘れてこの睡魔消えたっけなと考えたりしていましたが、大体プレイしていくうちに慣れてきます。ダメージ表記、厳密には相手の防御値とかMissの存在があったり、相手の逆襲の関係で火力が伸びたり、こちらの調味料コンボで結界が張られて逆に落とせたりするので、最終的にはちゃんと計算してやる必要があります。
また、敵の行動パターンも色々とあって敵ごとのちょっとした攻略要素や手持ちのデッキとの相性要素もありつつ、ボスは特殊パターンなども散りばめられていて、全体的に丁寧なバランスに感じていました。
最初がだいぶチュートリアル風の簡単目なダンジョンで、終わりの方に行くまでは変わり種の要素はありながらも攻略的には何とかなるレベルに仕上がっていて、最後の方はちゃんと難しいという綺麗なレベルデザインです。
システム面で見ると、最初にも言及した良い意味での緩さのおかげでオレオレコンボが作りやすくなっています。
手札は常に完全補充、手札5枚に対してデッキ8枚なのでコンボを引けない確率の方が低いし、仮に引けなくても次には揃うバランスはかなりプレイヤー有利なんですが、その分自分の考えた最強のコンボを叩きつけやすいです。
もちろんそれだけだとプレイヤーが強すぎるので、左側の野菜を消したり全体を腐らせたり、長いコンボをする上での障害的な技が敵側に用意されていてバランスはとられています。丁寧。
デッキ構築ローグライトの一部というかカードゲームでは、デッキ圧縮が何よりも強いのはポケカとかをやっていると分かる方もいるとは思うんですが、このゲームではプレイヤー側が理解してそれをやるまでもなく、あらかじめデッキ圧縮されているようなものなので、初心者でも気軽にコンボが楽しめるようになっています。
反対に、デッキ圧縮やろうとしても圧縮されすぎているので、あんまり意味がないという、ドローソース方面にカードプールを広げられない設計にはなっています。デッキに一枚しかないナスを使ってナス引いた時は笑いました。これだとドローは基本的に弱いですね。一応、カードを育てるという面では選択終了時のカード枚数が多い方が有利になるケースもあるんですが、たいてい育てるのは一極集中なのでそこまで恩恵は無かったりします。
その分、カードプールは特殊な効果や状態異常、能力上昇に振られていて、その辺の効果を上手く扱えるかがカギになってきます。単独で強いカードはもちろんないわけではないんですが、それよりは組み合わせが意識されてるようなカードが多い印象です。やっぱり、コンボ推奨っぽいデザインなんですかね。自分だけのオリジナルコンボを見つけよう!と題されてますし。
その辺のインゲームの完成度は高いゲームで、個々のパートはずっと楽しく遊べるんですが、一方でタイトル周りのループの体験はやや険しいところがありました。
要素解放が奥まっている上に開放要素が分かりにくく、どう強くなったか判然としなかったり、そもそも開放しきってもグレーアウトしたりしなかったりで、何となく解放の楽しさが薄く感じます。多分、項目完了時にCompleteとついたり、横に開放したもののアイコンが並ぶなどのリアクションがあるだけでも楽しい気はします。
また、エリアアタック終了後にタイトルに戻されるのは多分新要素解放などのサイクルに入ってほしいからだとは思うんですが、再び同じパートナーをいちいち選択して始め直すのも若干手間です。パートナー選択くらいは記憶しているか、クリアできているなら強化は不要と見てそのまま次のエリア選択に行かせるなども良いのかもしれません。この辺は好みだとは思います。
エリア選択というかシェフスキル選択についても、エリア選択時に挑戦するの下にあるというのがあって、しばらくどこにあるか分かっていませんでした。
エリア選択でエリアを選択したときはほぼ挑戦する気持ちになっているので、そこで準備に当たるシェフスキル変更を行おうというモチベーションが弱いのが印象に残らなかった理由なのかなと思っています。とはいえ、パートナー選択とセットにするとエリア選択で思い立って変えたくなったら戻らないといけないし、エリア選択でエリア選択以外の項目を作るのもなんか気持ち悪いですし、エリア選択時に強制でシェフスキルを選ばせるのは冗長な感じもします。難しい。
あとこれは完全に筆者がせっかちだからなんですが、通信で微妙にプレイのループがシームレスにならないのがずっと気になっていました。
累計時間で言えばもう本当に微々たるものではあるんですが、ゲームをしているという気持ちが切れるところでもあります。これは多分、ロード中とあって何かアニメーションしていたら倍の時間でも気持ちは切れないので、作者さんが誠実に通信のことを説明してくれていることに起因しているのかなと思います。
一般に販売されているゲームでも開発側に情報を通信で飛ばすのは良い手法らしいので、バックグラウンドで隠蔽するとか、ロードと偽ってみるとか何か手を打った方がむしろプレイ体験は良くなるのかもしれません。
しかし誠実さによる信頼も得難いものなので難しい話ではありますね。ここまで行っておいてなんですが、黙って送信も先述の方法でやろうと思えばできるのに、ちゃんと諸々確認を取って行う誠実さそのものは好きです。悪いのは筆者がせっかちなことなので。
最後に1111を出した時のスクショ張って終わります。
これくらいの、ちょうど良くプレイヤーが上手くやってやった感のあるミニゲームを作るレベルデザインの妙が素晴らしかったです。鳩ノ巣原理はドツボにはまると20秒くらい本当に見つからない時がありましたが。上手く見つけると1秒くらいになるので楽しくなれました。
| 1111 |
|---|
07. 群像物語~タコ型宇宙人と残された七日間~

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ADV/RPG | フィールMX |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 2時間 | 7/16 | 100% |
良かった点
- オープンワールド風に仲間を集めていくのが楽しいです
- 序盤にシナリオパートを挟むことで主要キャラに愛着が湧きました
- サクサクと進行していくゲーム性でした
気になった点
- 戦闘後に控えも含めて大量のレベルアップ演出が見えるのがやや冗長に感じました
- 控えがレベルアップするのは仲間の入れ替えが捗って良かったので、しれっと上がってほしい気持ちがあります
レビュー
自由に仲間を集めよう
群像物語~タコ型宇宙人と残された七日間~は、前半がADV、後半がRPGとパートごとに分かれた体験が楽しめる作品です。
前半のADVパートで進行していく物語に対し、後半のRPGパートで決着をつけていくという構成になっています。
ADVパートでは、3人のキャラクターから1人ずつ選んで進めていく群像劇風の物語が繰り広げられていきます。
騎士団長、新聞記者、盗賊と一見相互に縁のなさそうなキャラクター達が、ある一つの事件に巻き込まれていくというものとなっています。
そして、その事件を契機として、後半のRPGパートでは世界を周って仲間を集めていくことになります。
オープンなフィールドを駆け回り、23人にも及ぶ個性豊かなキャラクターを仲間にしていきましょう。モヒカンも集めることができます。
そうして世界中から集めた仲間の内4人を選んでパーティを作り、RPGの醍醐味である戦闘に臨むことになります。控えにも経験値が入るため、レベル差に悩まされる心配はありません。スキル構成やパラメータを加味して、とっかえひっかえしながら進めていきましょう。
待ち受ける強敵に対しては、こうして組み上げた自分なりのパーティを組んで挑んでいくことになります。敗北してしまったら、パーティを入れ替えて再戦するのがお勧めです。
オープンな世界で仲間をたくさん集めて敵を打倒していきましょう。
感想
最初に思った感想は、タコピィで語尾がッピはツーアウトだなあというものでした。何なら宇宙人でスリーアウトかもしれない。
ある意味最初にリアリティラインというか、物語のベースが引かれた瞬間でもあるので重要な所なのかもしれません。どんなにシリアスな展開になろうと、でもこいつらの計画タコピィなんだよなと思うだけですべてが吹っ飛んでいきます。
まだタコピィの話をするんですが、前半パートでは割とシリアスっぽい展開を続けているんですが、タコピィが絡むのもあって良い意味で茶番であり続ける展開でもありました。一番主人公っぽいポジションのキャラがそこそこまじめな性格をしているのに、これだけコメディに振れるのも凄い。
そもそも1年かけて構想した計画がタコピィなあたり、ラスボスや大臣に対する感情が迷子になりがちではあるんですが、そういう不調和を楽しめる度量をプレイヤーに求めているのかもしれません。
というかこれだけガバガバな計画立ててるんだったら、リューコは反乱を計画しないでとっとと王様に報告して上手くとりなしたほうが良かったんじゃないかとすら思います。愚王じゃないですし。王様のジジに対する信頼が意外と厚かったんでしょうか。それにしては王様の聞き分けの良さは結構なものだとは思います。
単純に、ジジを告発しても黒幕を引っ張り出せないと判断していたのかもしれませんし、それなら最終的には目的を果たせていそうです。
ずっとタコピィの話をするわけにもいかないので、ゲーム後半のオープンっぽいパートについて触れます。
仲間が各地に散らばっていて、それを自分の意志でいろんなところに行って仲間にしていく、という体験は良かったです。かなり自由度高く回れるので、自分の足で向かって仲間にした、という感覚が強くあります。
それぞれの仲間になるまでのエピソードはだいぶあっさりしていますが、そのあたりはテンポ感との兼ね合いなのかなと感じています。
その分、前半のADVパートで主要キャラクター周りの物語を割とがっつりとやります。このパートの存在が大きくて、後半パートであっさり目に集合するかつての敵だったり仲間だったりに対しても何らかの感情を持つことができます。
主役級のキャラクターとしての印象を強めるのはもちろん、サイドのキャラクターもあの時のあいつねと思わせることで仲間にしていく過程を楽しませてくれます。さすがに、ぽっと出のドラゴンとかレオとかあの辺に対するキャラクターにはあんまり思い入れはありませんでしたが。
後半パートの好きな所としては、仲間以外にも強化イベントみたいなものがあったり、モヒカン集められたりと、仲間集め以外にもいろいろとモチベーションを持てるところもあります。仲間集め一本槍ではないので、適度に気分を変えつつプレイできました。
戦闘のバランスやシステム自体はサクサクと進めることを念頭に置いているのか、ある程度易しめで、こちらが十分に準備できていてれば苦戦しないレベルです。普通に弱点を殴っているだけでも火力が出るので、器用に戦わなくても大体勝てます。
裏ボス周りはやや苦戦するところもありますが、分かってしまえば倒すことも容易となっています。
個人的にはサムが強くて、高い素早さから挑発でタゲを取りつつ、昼寝である程度回復までこなせます。特に二人で挑む闘技場では一人でいろいろできるので重宝しました。
全キャラ使ってみたわけではないので、他にもいろいろ面白そうなキャラはいるかもしれません。世界をどう回ったかによっても仲間のパターンは違ってきそうですし、プレイヤーの数だけチーム編成がありそうです。組み合わせが豊富。
08. ギフテッドワールド

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| RPG | はげ納豆 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 5時間 + 19時間 | 1.0.3 | エンドロールまで |
良かった点
- あらゆるプレイヤー不利益を先回りして潰そうという親切なゲームデザインでした
- 耐性や敵のギミックを軸とした頭を使ったボス戦が楽しめます
- 終盤になるにつれ歯応えが増していく良いバランスでした
- 緩い人物描写で各キャラクターのエピソードが描かれていました
気になった点
- ダッシュが撤廃されている割には、ダンジョン等は広めの空間に思えました
- ベースの歩行速度は十分早いので、単に広いなという印象なのかもしれません
- 特に図鑑においてページ単位のスクロールが欲しくなりました
- アイテムドロップの確認のために下キーを押し続けるのが割と手間です
レビュー
敵を知り、己を知れば百戦危うからず
ギフテッドワールドは、プレイヤーの感じる不便さや不安要素を徹底して取り除いた、あらゆる配慮が行き届くRPGです。
その徹底さたるや、取り返しのつかない要素は無く、離脱メンバーがいないことが明示され、いつでもセーブもワープもできます。戦闘面においても、高速化やオートは当然のように存在し、ステータスや行動内容はいつでも確認でき、状態異常の継続ターン数が常に見えているような完備さです。
徹頭徹尾貫かれた遊びやすいデザインにより、ゲームを楽しむことに集中できるゲームとなっています。
加えて、その親切さに比例するように温かなシナリオもまた魅力の一つでしょう。
ベースとなるRPG的な戦闘の楽しさのテンポは崩さないまま、主要キャラクターの成長が気持ち良く描かれています。
ただし、シナリオは優しくても戦闘はそう易しくありません。
敵のギミックを基軸としたボスとの戦闘は、十分に歯ごたえがある難易度となっています。序盤こそ立ち回りを整えれば初見でも撃破できますが、終盤に向けて段々と難易度の上がっていくボスに立ち向かうには、事前の準備が欠かせなくなっていきます。
装飾をはじめ装備品を組み立ててボスの技にメタを張りつつ、相手の行動に対するその場その場における戦略の組み立ても駆使して並みいる強敵に打ち勝っていきましょう。
バフとデバフを駆使して有利な状況を作り、敵のギミックを封殺していなし、最大火力を構成して叩き込む。そんな考えて戦うボス戦が、徹底したユーザビリティに下支えされて楽しめます。
敵の攻略法を考えて戦うのが好きな人にお勧めの作品となるでしょう。
感想
思いつく限りの不便さを先回りしてことごとく潰しているゲームです。不便さというか、プレイヤーの不安と言った方が適切かもしれません。
フリーゲームに限った話ではないんですが、プレイヤーにはゲームに対する信頼というものがあると思っていて、大体知らないゲームの場合は信頼がゼロから始めます。この状態で不具合っぽい挙動に出会ったり、なんとなくやりにくいものに出会うと信頼度が低下していって、その結果不具合に見せかけた演出みたいな外連味のある行為に対しても疑問を感じるようになってしまいます。
要するに、ゲームが提供する全てのものを享受して楽しむためには、そのゲームを十全に信頼する必要があります。その点で言えば、おおよそ最初の方からこのゲームには信頼しかありません。
取り逃し要素がないことはかなり良くて、実際廃村で後で回収できるのかなと思っていたら綺麗に宝箱が並べられていたのは笑いました。律儀すぎる。
また、取得物UP系アクセサリによる占有は本当にJRPGの因習だよなあとは思っています。FF16のことです。
物凄い細かいレベルで言えば、船や飛空艇が早かったり、イベントが終わったらキャラクターがすごい勢いで退場したり、ものすごい広いマップで敵に遭遇するのが大変だから最後の地点に全員のシンボルが置いてあったり、とにかく色々と配慮の鬼になっています。ここまでくると不便さへの恨みというか執念すら感じますね。
ダッシュ廃止については、ボタン押しっ放し辛いよねは同意でして、長い時間やっていると指がつりそうになります。一方で、ダッシュそのものには意義があるなとは思っています。エリアを高速で移動してスキップしているという感覚的なものを得られるだけでも、心理的に楽なところがあるからです。
加えて全体的にエリアが広いのもあって、歩行速度は速くてもダッシュが欲しくなってはしまいました。だからと言って押しっ放しは嫌という我儘な気持ちもあります。
エリアの広さに対して地味に効いてるのが、宝箱を全回収する必要が原則的にある、シンボルエンカウント間の距離が離されていて戦闘を意識的に行うのがやや面倒、あたりもあります。
宝箱については、全回収の報酬自体は必要度が高いが、宝箱そのもののアイテムには大体魅力がないというのも辛くて、一つ一つを開けるモチベーションが弱いまま全てを開けようというモチベーションだけで動いていました。これだと一つの宝箱に対する嬉しさが一切なくて、最後にアクセサリもらう時だけ嬉しくなります。
シンボルエンカウントについてはアイテムドロップがランダムなのも相まって、割と同じ敵と連戦したいけど距離が離れているから効率的にやるのが難しいというのが厳しい所でした。天使のたまご拾うためにずっと天使全滅させまくっていたのは中々の虚無。
また、シンボルエンカウントは部分的には相互が接触しようとするから成り立っている節があるので、相手に会敵の意思がないとすり抜けが多発するのもちょっと難しいところです。結構頻繁に移動するから、というのもあるかもしれません。
なお、一応会敵するシンボルには全部一度は当たりに行くプレイをしていたところ、全部集まるケースは稀、大体半分集まる、ものによっては一つも拾わないこともある、くらいの温度感でした。耐性装備集めるのが一番しんどかったかもしれない。
ここで話はそれるんですが、最後の強雑魚に関してはドロップ率100%で良くないですかと思ってました。鉛筆削りだけ5個もよこすな結婚指輪が欲しいんだ。
続いて、戦闘バランスの話をします。
雑魚は基本的にオートで片づけるもので、強い雑魚はちょっとだけ手動をかまして片づけるもので、ボスは全力で対策を積んで戦うものです。思い切ったバランスで好きでした。
序盤というかいったんクリアまで行くくらいのレベルだと、ざっくりした対策を積めば勝てるんですが、終盤までくると相手の行動に対する回答を出すための耐性パズルと戦略性が要求される歯応えのあるギミックボスバトルが楽しめます。
個人的には宝物庫のシカあたりからその傾向が強くなったと感じていて、ここ以降はとにかくちゃんと対策しないと負けるバランスでした。気を抜くと1ターンですべての命が刈り取られます。
アクセサリを組み替え相手の攻撃に耐性をつけ、回復タイミングと障壁タイミングを適切に行いつつクールタイムを管理し、数ターンに一度の攻撃チャンスで最大火力を出せるようにバフデバフを撒いていくのは楽しいです。
とはいえ、相手の行動はほとんどのケースで全て見えますし、能力値やら何やらはすべて開示されているので、理詰めでだいぶ詰められるというのも良いバランスでした。初見未対策で挑んで一瞬で壊滅し、これどうやって倒すんだろうと思ってからがスタートラインです。
ちなみに最も苦手だったのはシカで、こいつだけ3回くらいゲームオーバーした上で倒しました。耐性の強さをまだあまり理解していなかったのもあるんですが、こいつだけギミックより火力で押してくるタイプなのもあったのかもしれません。それ以降のギミックボスはギミックを封殺すれば大体勝てるので。
全員耐性0にして挑むイモミズクリ、百見でパターンを見切るジーニアス、あえて属性耐性マイナス反転を受け入れ、序盤はとにかく戦闘不能になっても立ち回れるようにして反転解除後に一気に責め立てるチュートトあたりは実質初見で抜けられます。
ブーステッドは超火力魔法に対しての属性耐性パズルに苦労しましたが、ループが短いので障壁の使い分けやタイミング次第で突破できます。最後のギミックは眺めてたら複製反罰が光ってたので迷わず押した。
シスターズはさすがに強敵でしたが、耐性パズルで全属性43以上、ユキダルマの毒と気絶以外、全員状態耐性100、マリモやスマーテストに至っては全属性50を超え、ヨチヨチも無属性64とする構成を組み上げて封殺しました。耐性は大事。一人の毒だけ防ぎきれませんでしたが、ここは即発キュアー打てばいいので割と簡単に解決できます。
思い返しても慣れてなかったのもあってやっぱりシカが一番強かった気がします。人によって苦手なボスが分かれそう。ちなみに補足として、全ボス勿論強くて難しいのですが、これは全部心地よい難しさです。理不尽でない。このバランスは本当に素晴らしいなと感じていました。
戦いにおいては基本戦術がバフデバフを撒きつつマリモの超強化を基点に高火力技を何度か当てて倒す、という道筋が一貫されています。
こう書くと、ともすればワンパターンに見えそうですが、実際のプレイ感は全くワンパターンとは思いませんでした。相手の行動ループに合わせてこちらが適切な行動をとる必要があり、回復のタイミング、強化のタイミング、アイテムを切るべきタイミング、それぞれを常に思考しながら戦うので全然ワンパターンで戦えません。思考を回し続ける楽しさがあります。
この辺のバフデバフの大事さはらんだむダンジョンで学んだところがあるので筆者は慣れていましたが、慣れていないとちょっと難しいかもしれません。さすがにバフデバフが切れたら即座に負ける、というレベルではありませんが重要なのは確かです。ユキダルマに先陣一献のかんざしを常に装備させてたくらいには大事です。
このゲームの戦闘システムの良い所としてもう一つ、大ダメージを受けると特殊攻撃を打てるTPが回復するというところがあります。
これは一気にダメージを受けてピンチになった時の逆転要素としても十分機能しますが、それ以上に壁を張り続けて守りに徹するとかえってジリ貧になるということにも効いています。
適度に大ダメージを受けて一気に回復したほうがトータルでは得という設計のおかげで、相手の攻撃性能を見極めて、ここまでは受けていい、ここからは防ぐ、といった線引きを常に考えるようになります。ギリギリの戦いをしたほうがかえって勝ちやすいので、ちょくちょくわざと攻撃を食らいつつ、それを上手く転用していくのが楽しいです。
なお、最後の切り札と言っていい貯金趣味ですが、絶妙な強さをしています。500000エストが意外と遠い。でもちゃんと強い。実質冒険者の心の下位という立ち位置ながらも、4つあるので色々と応用が効きます。
稼ぎについては、なんとなく即死が通るあの強雑魚をひたすら狩るのが楽な気はしていました。ユキダルマでワンパンした後にリピートし続けよう。
余談ですが冒険者の心というアクセサリは結構好きで、クエスト達成ごとに強くなるのでずっと愛用していました。面白い機能。
シナリオ面でも少しだけ話します。
基本的に良い人しかいないタイプの物語なので個人的には好きです。全員前向きで、それぞれの成長エピソードもしっかりと差しはさまれます。この冒険を通じて色々と成長したということが分かるのが良いですし、最後の最後にギフテッドワールドを再解釈してくるのも良かったです。それはそれとして、なんでマリモという名前になったかは気になります。このゲーム、イモミズクリを始めとして由来が分からない名前がちらほらあります。気になりますね。
また、システムを絡めたストーリーが好きなので、宝物庫のイベントバトルからの流れは好きでした。ただの便利機能というだけではないのが良い。
ちなみに、一番好きだったキャラクターはユキダルマでした。一番良い子なので。
世界観も面白くて、ギフトというそこそこの脅威に対してある程度の自助で成立している絶妙なバランス感で成り立っている世界です。
ギフトの力で簡単に国がひっくり返りそうですが、その中でも大陸を統べる王国が築き上げられています。この理由付けとして、外にある自助的なギルドがある程度個の脅威をコントロールしているとしているところも面白いですね。
じゃあギルドが腐ったら終わりなのかという話に対しては、ギルドの長があの人だからで片づけてきます。哲人政治で成り立ってませんか。それは後継選びに慎重にもなりますね。
細かいところですと、クエストの鹿の駆除が割と印象に残っていて、このタイトルでナンバリングされることあるんだと思いながらやっていました。何なら先述の理由で一番シカに苦戦したのもあって、このゲーム全体を通してもシカの印象が強いかもしれません。
20時間以上もゲームを遊ぶと色々楽しかったことがあって筆が止まらないんですが、そろそろここで書き終えることにします。
とにかく倒し方を考えることのできる良いゲームでした。考えて倒すボス戦って楽しいですよね。
09. みかど出現

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 戦略シミュレーション | zabumaru |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 4時間 | 1.01 | クリア |
良かった点
- 敵を分断して大将首を取る独特な戦略が楽しめます
- ずっと世界観がゆるいです
気になった点
- 特に終盤は大将が隙を晒すことを期待するお祈りが必要に感じました
- 移動先をマウスで決めますが、この時に段差に落ちると再度登れなくなります
- 特に、移動が始まる前にカーソルが落ちる方向にあると、ターンが回った瞬間に落ちます
- 移動原点に基づいて移動可能範囲が算出されるか、テンポを損ないますがクリックなどの工程が挟まれるとケアできそうです
レビュー
わちゃわちゃパクパクSLG
みかど出現は、わちゃわちゃと動く友軍と敵軍がぶつかり合うシミュレーションゲームです。
一画面に収まるクォータービューの地形の中、両軍が衝突して戦うことになります。
このゲームが単なる戦略シミュレーションに留まらない特徴的な点として、敵軍がピンピンしていて友軍が虫の息だとしても敵の大将首を獲りさえすれば問答無用で勝利する、というシステムが挙げられます。反対に、主人公がやられればどんな状況でも問答無用で敗北です。
すなわち、主人公が倒されないように立ち回りつつ、何とかして大将を打ち倒す策を練るのがクリアのカギを握ります。囮で敵を分断したり、遠距離攻撃で肉癖を抜いたりして、上手く大将まで攻撃を届けさせましょう。
戦闘に勝利して倒した敵は、きびだんごをあげることでどんどんと仲間になっていきます。この、どこか緊張感のない緩い世界観も魅力の一つとなります。
そうして徐々に大所帯になっていきながら、さらなる強敵に挑んでいきましょう。
感想
前作では個人的に理不尽に感じていたアバウトな移動スタイルに対し、一部の指示を受け付けなそうなやつは自動で動き、そうでないのは手動で動かせるという折衷案的なシステムになっていたのは、これまた個人的には良かったです。
ある程度はこちらで、囮やら切り札としての温存やらを考えられるので戦略性が上がりました。
その一方、SLGとしてちゃんと操作できるようになったことで、前作にあったとりあえずマウス動かしておけば勝手に終わる独特のテンポはなくなっています。トレードオフという感じ。
沢山のキャラがわちゃわちゃ動いているのを眺める楽しさは健在で、攻撃の時のちょっとしたモーションも含めて見ているだけでも楽しめます。
幕間パートでたくさんの仲間を引き連れて動けるのがその中でも好きで、最後の方になると色んな敵と戦って仲間にしてきたなあと感慨を得ることができます。
難易度に関しては前作同様にまあまあハードに感じていて、特に終盤はかなり難しいです。
前半こそ上手く打ち合えば全滅も狙えますが、後半は絶対に無理なので何とかして大賞首を晒させる必要が出てきます。それでもラスボスまでは囮を左右に配置して分断するモーセ戦術が効いていたんですが、ラスボスはしばらく向こうから手を出してこないのでこれがかなり難しいです。
最終的には何とか勝ちましたが、正直なんで勝ったかは分かりません。大将がたまたま射程圏内に来たから殴ったら勝った。勝ちに不思議の勝ちありですね。
前作においてもマウスを動かして相手大将が良い感じに動く導線を探すゲームではあったので、その辺のプレイ感はそんなに変わっていはいません。
また、細かい話をすると見下ろしの仰角が割と小さいので、射程のカウントがちょっと難しいところがあります。これのためなのか分かりませんが、思ったのと違う技が出て負けたこともあります。私が見た感じでは強力な攻撃が出る方の射程だったんです。
そも相手の行動範囲や射程も一瞬しかビジュアル的には出てこないので、その辺は雰囲気で察するくらいのムーブが良いのかもしれません。
個人的に一番しんどかったのは段差による移動障害に対し、段差から一度でも落ちると段差の上に戻れなくなるところでした。
主に籠城っぽいことをしているステージで、相手の上を取るために頑張って速度の速いキャラで段差の上に動かしたのに、マウスが下にある時にその手番が回ってくると川の底に落ちて戻れなくなります。
マウス位置に勝手に動き、かつそれによって移動可能判定を兼ねているというシステム自体は面白いんですが、動く前にワンクッションないとこういう事故が起きそうです。特にきつかったのは、下方向にいる別キャラを動かしていて、その次のターンで段差上のキャラを動かそうとしていた時です。約束された落下。
シナリオというか世界観の話をすると、かぐや姫ベースかと思えば戦国武将が出てくるけど、それでも何となく納得してしまうような緩い世界観が面白いです。最後にロケットが飛んでも受け入れられるような懐の深さがあります。
加えて、どんな敵でもきびだんごを食べさせれば仲間になってくれるのも緩いですね。それ桃太郎印じゃないですか。さっきまで激闘を繰り広げていた相手だろうと、お構いなしに仲間にしていけます。どうせなら引き連れてた人達も引き抜いて欲しい。
どうやらアップデートで色々遊びやすくなっているらしく、自動装備がついたり装備制限が緩和されていたりしているようです。この辺の調整があれば難易度も緩和されていそうなので、現行バージョンなら大将首を獲りやすくなっているかもしれませんね。
10. オミくじ

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| クイズ | ビッワリアンチョコ |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 10分 | 1.00相当 | エンディング |
良かった点
- シールの種類が豊富です
気になった点
- シールリストがもう少し見やすい形式だと一覧性が上がりそうです
- 各シールを横キーで順繰りに見れると見やすいかなと思いました
レビュー
オミくじを引こう
オミくじは、くじを引いてシールを集めるゲームです。
AI生成された様々なシールを集めては眺めてみましょう。色々なキャラクターが描かれたシールには、それぞれ新型コロナウィルスに関する知識も書かれています。
そうしてシールを集めてコロナの知識を獲得したら、マップのどこかで新型コロナウィルスにまつわるクイズに挑戦することもできます。
全問正解目指して解いていきましょう。
感想
キャラはAI生成っぽいんですが、某チョコっぽい背景はなんとなく後からレタッチしているなり付け足しているなりしているような気がしていました。レア度合によってちゃんと区分されているので。
結構はっきりと線が出ているのもありますし、大分濁った印象を受けるのもあるので、本当に玉石混交というか、石が多い感じもあります。石は石で見た目が割と良いのもあるんですけどね。GANで作っていた時代ぐらいの歪みを感じます。
具体例だと、V2891Iくらいのはっきりさなら実用上使えそうで、V483Aみたいな変なやつはある意味好きです。重なった状態で出力されたのかな。
この作品のシールのように、なんか大量に絵が欲しい場合はAIが割と強い選択肢に入ってきている気配はあります。
ウディコンの規約を始め世間の風潮が出展元の著作物明示化の流れになってしまっているので、Fireflyとか一部のサービスしか使えなくなるかもしれませんが。Adobe Stockに流し込めばロンダリング出来るみたいな話もあるので、結局のところどこまでうまく制御できるのかはグレーっぽいですね。LoRAを自分の絵柄でやる分には良いのかとかその辺の話もありそう。
コロナあるいは変異株については想像よりかなり詳しめにバリエーションしているので、まあまあ知らない情報が多かったです。
よっぽど丁寧に追っている人か専門家でもないと、この辺りカバーできる人はいないんじゃなかろうかと思ってしまいます。D614Gを言わずと知れたスーパースターと呼んでいますけど、言わずと知れているレベルなのかは分かりません。強毒化したアレだよと言われてようやくピンとくるレベル。
そういう意味ではクイズはかなり難しく、常識的なところはともかく、マニアックっぽいのは初見では通せませんでした。シールの説明を見て回答するにしても、シールの説明を順繰りに見るのがまあまあ面倒なので、その辺はあんまりやっていません。
シールについては色々説明があるので、アイテムの流用ではなくてカードリストとしてのUIで構成されていると色々と便利だろうなとは思いつつ、ちゃんとやろうとするとステータス表記みたいなUIが欲しくなりそうで、コスト高くなりそうだなとも思っています。変異株のステータス表記、それはそれで面白そうですが。
11. 竜と黄金の梨と焼け残り
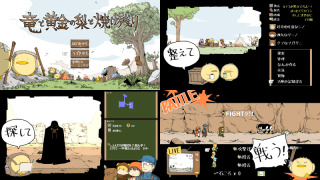
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ローグライク | スミスケ |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 5時間 | 1.07 | クリア |
良かった点
- 細部にまで凝られたグラフィックが素晴らしいです
- ステータスなどがファジーに表現される仕組みも相まって、緩い世界観が醸成されています
- 体力を雰囲気で管理しているので緊張感もあります
- ローグライクとして安定した作りとなっていました
気になった点
- すべての演出が丁寧に作られている分、テンポ感が悪い印象を受けました
- 毎回ちょっと待つなあくらいの温度感です
- ※アップデートで対応が入った模様です
- 製作について、適当に作ると何もできない上にかなり嫌なSEが鳴るのでモチベーションを削ぎます
レビュー
ゆるグラローグライク
竜と黄金の梨と焼け残りは、微に入り細を穿った高品質なグラフィックが特徴のローグライクです。
3Dで表現されたダンジョンを進み、敵と戦ったりアイテムを拾ったりしながら階段を探して最下層を目指す、オーソドックスなローグライク体験が楽しめます。
| 戦闘画面 |
|---|
ただし、ダンジョンで遭遇する敵との戦いは、自分のキャラクター達と敵がぶつかり合う一風変わったものとなっています。
3人のキャラクターにそれぞれ指示を出しながら、にぎにぎしく動く様を眺めていきましょう。折を見て石ころなどの投擲物を活用したり、厳しい相手には逃走を図ったりと、柔軟に対処をしていくのがダンジョン攻略のカギとなってきます。
また、ダンジョン攻略においては各キャラクターのパラメータも重要になりますが、その全ては曖昧に表現されています。
戦闘やイベントを経て成長していくパラメータは何となくの強弱をつかめる文章によって、キャラクターの体力はそれぞれのグラフィックのやられ具合によって判断できます。感覚的にパラメータを俯瞰して、直感的な判断をもとに選択していくことになります。
ボロボロになったグラフィックを見つつ、どのタイミングでどの回復までを必要とするかを見切ることも重要となってくるでしょう。
とにかく、全体を通して高い品質のグラフィックと、ぶつかり合いによる見目の楽しさに裏打ちされたローグライク体験が楽しめる作品です。
適度に敵を倒しつつ、アイテムを活用してダンジョンの深くまで下っていきましょう。
感想
常に画面が愉快なゲームです。特に戦闘画面が愉快で、左右でぶつかり合っている見た目も愉快なら、良く分からないキノコが爆走しているLIVE中継がなぜか流れているTVも愉快でした。
この辺の見た目が飽きない絵作りは高いグラフィック力に裏打ちされていて、ずっと楽しい感じの画が作られ続けていました。ダンジョン挑戦中に3人が色々とリアクションを取っているのが好き。
ローグライクとしてみるとオーソドックスな作りで、前半である程度強化して後半は逃げ切り体制に入ると楽なタイプです。
序盤のダンジョンならそのまま進めても良いかもしれませんが、後半は普通に敵が強いので上手く成長させていない限りはとっとと下るのが正解なのかなと思っていました。
作りや遊び方自体はそういう普遍っぽさがあるんですが、3Dダンジョンとぶつかり合いの戦闘という特殊な仕組みもあって、その一方で印象としては結構特殊なゲームだなというものにもなります。
ここから先は全体のテンポ感の話をするんですが、アップデートで改良されている雰囲気があるので、現バージョンでは問題ないかもしれません。予めご了承ください。
良く言えばすべての演出が丁寧、悪く言うと毎回ちょっと待つなあというのが全体の印象です。例えば、拠点に入るとしばらく待ってから選択肢が出ますし、拠点からエリア選択に行くとフェードアウト、しばらく暗転、地図画面でしばらく待機してようやくひよこが現れて動けるようになります。このように、全体を通して操作できるようになるまでの時間が長めに取られている印象です。
特に拠点や地図の、要素としてはすべて見えているにもかかわらず何も操作できない時間、というのがそこそこ辛く、ロード待ちでもなければ画面上の変化も大きくないので何で待たされているのか分かりにくくなっています。
インゲームというかダンジョンで言うと、3Dダンジョンの操作は非常に軽快です。簡易マップや向き固定移動も完備されていて、かなり動きやすく階層を周れます。通路でダッシュも可能ですし、ちゃんとその場合は敵にエンカウントするリスクも背負います。
その一方で、戦闘面ではこちらも演出が丁寧な分、テンポは遅めです。戦闘開始と同時に「まあまあちょうどいい相手だ」のような文字表示に、Ready Fightまでちょっとだけ時間を取ります。倒すとスローが入り、その後SEが何度か鳴る時間があって、勝利のマークが出てから戦闘が終わり、敵の消滅演出が入ったのちに「敵をねじ伏せた」文字表示が出て動けるようになります。場合によってはここでキャラクター強化の文字列も順繰りに表示されます。
ダンジョン1階層ごとに敵とのエンカウントは2~4回程度あることが多く、20Fあるとだいたい60回くらいこれをやることになります。重要な演出や意味の感じられる間ならともかく、何度もやることになるこの要素で待ちがそこそこ発生するのは若干辛くはありました。
個人的な印象としては、スローは演出的に好きで、勝った感覚を得られるので良かったように思います。SEを鳴らすタイミングをスロー中に混ぜて文字表示もやってしまう、最初のテキスト表示もReady Fightに混ぜつつ命令操作くらいはできるようにする、敵の消滅演出中についでにテキストも出す、みたいな感じでまとめてやると多少待ちが少ない印象を覚えるかもしれません。
ただ、順繰りにやることのメリットもあって、それぞれのテキストがプレイヤーにちゃんと読まれるし、それぞれの演出がちゃんとプレイヤーに見られることになるんですね。この点も踏まえると、どこを単独で見せたくて、どこまでは複合的に見られても良しとするかの線引きの話になるのかなと思います。演出も大事だし強くなったことも分かってほしいなあというオーダーなら、今の形がベストっぽいですね。
なお、罠を踏んだ時の一瞬待つ演出は個人的に好きです。あ、踏んでしまったヤバい、みたいな間があるのでドキドキします。演出としての間って難しいですね。
さらっと流してしまった3Dダンジョンの操作の軽快さについてもう一個触れておきたいんですが、個人的に好きなのは敵が近づくとSEが鳴るところです。
3Dダンジョンゆえに敵を見つけられないことは必ず発生し得るんですが、この仕組みのおかげで近くなったら必ず分かるようになっています。この辺の配慮が素晴らしい。これに命を救われたこともありました。
ランダムイベントについても結構面白く、ゆるゆるとしたグラフィックにあったゆるゆるとしたイベントが色々とあります。
容量拡張が一番嬉しいところはありますが、地味に食料をもらえると有難くなります。10F連続で食料を拾えず、クタクタの状態でイベントで食料をもらえた時は中々感動しました。
パラメータのファジー表現についても触れておくと、個人的にはおおよそ好きでした。
特に体力がファジーなのは良くて、今はどのくらいの回復をしてやるべきなのか、今戦闘にどの程度耐えられるのか、といったものが常にファジーな状態で進めることになるので結構緊張感があります。
もともと体力は結構ファジーに見て管理することが多いパラメータなので、こういう表現と相性が良さそうに感じます。グラフィックによる表現というのも、高いグラフィック力も相まって可愛らしくて良いですし。
一方で、あらゆるものがファジーであるがゆえに、厳密にやりたい部分も曖昧で良く分からなくなっている、というのもありました。
個人的には所持数制限がこれに該当していて、例えばプレイ中に何かを拾ったら急に制限がかかり、この後に4つほど作るでぶっ壊しても解決されませんでした。各アイテムに重量パラメータが設定されている故なのか、それともまとめて持てるアイテムがあるのか、といったようなことが不明瞭なため、解決法が見えないのが辛かったです。
体力と違って所持数制限はギリギリを攻めるのが一番強く、そうしたいが何をもってそうできるかが分からない、というのが厳しかったのかなと思います。
この辺の何を厳密にやり、何を曖昧にやっているか、というのはゲーム側でコントロールできるものなのかもしれませんし、個人によって変わり得るものなのかもしれません。もし前者ならファジー表現を采配するのが良さそうですが、後者ならトレードオフになるのかなと感じています。
なお、その辺のデメリットを考慮しても、ファジーにいろいろ表現されているのは、そのテキストの面白さも含めて結構好きでした。
製作というシステムについてもちょっとだけ話します。
製作それ自体は、いらなくなったアイテムを良い感じに処分したかったり、ダンジョン中で分解と共に上手く活用して生き残りやすくしたりと応用の利くシステムで楽しかったです。
ただ、SEが本当に辛かったです。めちゃくちゃ悪いことをした気持ちになりました。しばらく我慢してたんですが、後半からはもう辛くなったので製作せずに全部売ってました。これは多分個人的な好みです。
最後に何度か言及したグラフィックの話をするんですが、本当に良いグラフィックです。
タイトルを見れば大体察するところだとは思うんですが、キャラクターが上手いのみならず、背景とかその辺の質感までもが調和しています。ここ読んでいてタイトル見てない人なんていないとは思うんですけど、とりあえずタイトル見てください。
あとは焼け残りの「り」のフォントが焼け残りっぽく煤なのか何かが零れ落ちているのも細かくて好きです。
キャラクターもそのグラフィックのおかげでゆるく魅力的に描かれていて良い雰囲気を作っています。
食料の略奪が平然と行われるくらい資材不足が深刻そうな世界なのに、コーヒーを飲んで落ち着いている几帳面な人が好きです。そのコーヒーはどこから仕入れたんだ。
後は言わずもがなにひよこが良くて、あらゆるメニュー画面のフレーバーとしても出てくるので、常に画面がこのゆるさで固定化されています。一番好きなひよこは中断周りのひよこです。あなたの好きなひよこは何ですか。
しかし怪しい洞窟、クエストは受けたけど遠征先に見つからなかったので結局挑戦できずじまいでした。交流を始めたら、特にイベントも発生せずに情報だけ出てきてしまっていたのが、もしかしたら不具合だったのかもしれない。
12. 不屈のスペラ

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| デッキ構築ローグライク | テイク |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 2時間 | 1.02 | HARDクリア |
良かった点
- 最初に選んだ妖精のパッシブを軸にデッキビルドしていくのが楽しいです
- 程々のランダム性と戦略性が備わっていました
- ピンチをチャンスに、というシステムにより、意識的にハイリスクハイリターンの選択が取れるようになっています
- プレイヤーが選択する要素を極力省いているため、サクサクとゲームを進行できます
気になった点
- デッキ枚数に対してややカードプールが薄く感じました
- HARDクリアまでならそれほど気にならないレベルではあります
レビュー
ピンチをチャンスに変えろ
不屈のスペラは、RPG風の戦闘をカードで行って進めていくデッキ構築型ローグライクです。
戦闘やイベントで増減するHPというリソースを上手く活用して、40層からなるステージを攻略することになります。
| ステージ | 戦闘 |
|---|---|
挑戦するステージは手前3マスから発生するイベントを選択する形式となっています。
敵と戦ってカードを集めるもよし、ショップでHPを消費してカードを買うもよし、特殊なイベントで何かを得たり、回復するといった手段も取れます。現在のデッキの状況や自分のHPと相談しながら、最適な行動を選択していきましょう。
先の状況が前方5層まで確認できるため、先々のマスを見てプランを定めるのも肝要になってきます。
ステージを進む上で避けられない戦闘においては、それまで集めてきたカードによるデッキで挑むことになります。
現在のMPを消費してカードを選択し、敵に攻撃していきましょう。カードは、消費するMP、状態異常や攻撃対象、攻撃性能が異なってきます。特にMPを多く消費するカードは強力ですが、MPは原則毎ターン1ずつ増えていくため、強力なカードばかり集めるとデッキが重くなってしまいます。コストとバランスを意識して、自分なりのデッキを構築していきましょう。
また、デッキ構築にあたっては最初に選択する妖精のスキルも重要です。
被ダメージ軽減や回復スキルから状態異常の強化まで、それぞれの妖精が持つスキルに合わせたデッキ構築を目指すことで、高いシナジーを得ることができます。
そうして取捨選択してデッキを構築しつつステージを攻略していくと、当然ながらHPは消耗していきます。そうなった場合、回復マスやカードの効果でHPを回復させることで継戦していくことになりますが、このタイミングは慎重に見極める必要があります。
このゲームにはピンチをチャンスにという仕組みがあり、こちらの被ダメージが大きいほど攻撃性能が倍化していくためです。HPがギリギリになるリスクと引き換えに、高い火力を得ることができます。特にボスなどの強力な敵を相手取る時は、どのタイミングで回復し、どのタイミングで強いカードを切るかの戦略性も求められてくるでしょう。
こうした様々な要素が一体となったシステムは一見複雑に見えますが、手厚いチュートリアルとテンポの良いゲーム設計で、プレイしていくうちに自然とマスターできます。
言葉を尽くすより遊んでみた方が分かりやすく楽しいものとなることは請け合いなので、安心して妖精に合ったデッキを上手く構築し、最後のボスまで打倒していきましょう。
感想
序盤丸々チュートリアルに使っている思い切りの良さも含めて、かなり導線が丁寧なゲームだなという印象がありました。シナリオもそれに沿って動いていますし、難易度解放時にちゃんと要素解法演出もついているので、一貫した気持ちのまま最後の難易度まで挑戦できます。
デッキ構築型ローグライトとみると、DungeonMakerとかその辺に作例はあるんですが、この分岐型カード選択による行動の選択はやっぱり面白いです。先のプランをある程度こちらで決められるという戦略性と、不測の事態があった場合のリカバーも効くという即時性もどっちも加味されています。
ここに加えて、マス配置の都合上ある程度のランダムと決定性をどちらも付与できるので、要所のイベントは制御しつつも何度か遊べるリプレイ性も同時に担保していました。
また、マスが戦闘、強敵、ショップ、イベントとシンプルなもので揃っているのも良くて、ある程度簡単に予測できつつも、イベントというランダム性の高いものも含めて幅を持たせているように感じました。
デッキ構築の面で言うと、正直な話カードプール自体は狭めな印象を受けたんですが、妖精というパッシブ要素を軸に組み立てられるところで掛け算的な広がりは担保されていました。
特に妖精を最初に決められるのは面白くて、最初に自分でどういう方向性にビルドしたいかある程度考えて進められます。何もない地平から考えるのも面白くはあるんですが、軸が一つ定められているほうが迷いが少なくて助かりました。
妖精解放タイミングについても良くて、ある程度ゲームが分かってきたら増えて、大分理解が進んだらさらに増えます。応用タイプみたいな妖精が後に回されるので、その能力を使うイメージが湧きやすくなっています。
続いて戦闘システムの話をします。
全体的に余計な選択を省いたデザインになっていて、これがゲーム全体のテンポ感の向上にかなり寄与している印象があります。
カード選択時に対象を選ぶ工程がないというのもありますし、序盤はカード入れ替えが勝手に行われていくというのもあります。これによって、40層程度あっても30分もあれば辿り着けるようになっています。リプレイ性の高さには、このテンポの良さが間違いなく効いていました。
また、前作にもあった最大MPが溜まって徐々に強いカードが使えていくシステムも、かなりうまく機能していました。
雑魚との戦いは大体序盤のMPで終わりますし、ボス級との戦いでも、序盤は状態異常を撒いたりカードを補充したりと明確にやることがあります。低コストカードでも明確な役割があるので、どのターンでも考えて行動することが必要になってくる良い仕組みとバランスでした。
細かいところだと敵のタイプ表記が出ているのも良くて、初見の敵であったとしても、どういう順番で倒すのが理想かをある程度組み立てやすくなります。
対象選択の工程は省いても、そこにカードごとの特性を持たせるあたりや、この辺のタイプ表記あたりからも感じられるんですが、可能な限り考えて戦えるように制度設計されている印象を受けました。
簡単に操作できて、テンポを良くして、その上でちゃんと思考を回す余地を残すのは割と難しそうですが、その辺が上手くカバーされたデザインです。
個人的に好きだし発明だと感じたのは、ピンチをチャンスにという機能です。平たく言うとダメージを受けてるほど火力が伸びるんですが、これにより低いHPでも敵に挑むことのインセンティブが確保されていました。
特に序盤において、回復に傾倒せず出来るだけ敵を狩ってカードを取得するチキンレースをして手札を集めていく、というのがデッキ構築型ローグライトの強いパターンですが、システム的にこれをプレイヤー側に後押しする仕組みだなと感じています。
また単純に、ボス戦などでピンチになった時に最大火力のカードを温存しておくと勝てる、という熱い要素でもあります。どこで大火力カードを切るかの駆け引きも生まれますね。筆者はラスボス相手に2桁残したギリギリの状態で全火力を投じて勝った時が一番気持ち良かったです。
その分ダメージ計算が難しくなる面はあって、確定一撃とかの計算はちょっと難しくなるかなとは思うんですが、ゲームの設計上数値が大きい上にぴったり合わせるタイプでもないのでマージンをとれば調整できるようにはなっています。予想ダメージ表記も出ますしね。
全体的な難易度はやや易しめかなというレベルで、HARDで(自分のミスで)1回敗北はしましたが、それ以外はそのままクリアできるバランスです。通した印象としては、クリアできるように作られたバランス、くらい。
よっぽど不運を引くと怪しいのかもしれませんが、序盤でデッキ構築に失敗しない限り中盤以降は安定する感じはあるので、失敗するとしても序盤の範囲に収まりそうです。序盤ならリトライも楽ですね。
| NORMAL | HARD |
|---|---|
筆者のプレイ履歴としては、NORMALはシルフ、HARDはバンシーで突破しました。
シルフクリア時は悪魔契約、ヘブンズウィング、救済による回復可能な設計で突き進んでいます。持久型にはめちゃんこ相性が悪いんですが、継戦能力は極めて高く、回復マスはほぼ踏むことなく最後までたどり着くことができました。大ボスで火力が足りず、オーバーライブラリーアウトしかけたのはご愛敬。
バンシークリア時は、とにかく強力な5コスト以上のカードで埋めてぶっ放すデッキを構築しています。救済などの5コストカードはあえて合成しないくらい徹底しました。その性質上被弾は多めになるんですが、そこはグングニルによる大量回復でしのぎつつ進めています。被弾が多いのを逆手に取って、ラスボスではギリギリまで被弾してからウンディーネをぶっ放して蹂躙しました。
このデッキ構築は性質上カードが揃わない序盤が一番しんどく、そこで無理した結果の一敗でした。
シナリオの面にも触れておくと、ストーリーが必要ラインでちゃんと描かれていて、ゲームのテンポを損なうことなくモチベーションにはなるレベルの塩梅に落とし込まれていました。
特にオープニングから開始までの流れが良いです。ここでキャラ紹介とばかりに会話劇が入るとゲームに入るのが遅れるんですが、ここをチュートリアル中に会話で進めていくことでカバーしています。実際にゲームを遊ばせつつ、キャラクターからのアドバイスを通じてその性格を描写していました。
色味的にも性格的にも某っぽいアレなのかと思っていて、そのくらいのテンションと世界観なのかなと考えていたら、まあまあなシリアスをお出しされて驚いたのも良かったです。あの入りで、腕切るレベルのシリアスが来るのは意表を突かれました。
このゲームについては、個人的にはHARDまでちゃんとやらせるゲーム性としての完成度が高いと感じています。
冒頭で触れた導線の丁寧さもあるんですが、NORMALがクリアできないとHPが増える仕組みがあるらしいことや、そこから先ではシナリオ面でここで止めると後味の悪いところで切るようにしているところなどにより、とにかく最後まで遊ばせる牽引力が仕込まれています。もちろんこれは全体的なテンポ感の良さ、それにも関連したリトライ性の高さなどの総合力からなせる業でもあるんですが。
現に、NORMALクリア時に作者さんの想定はここだろうしHARDはいいかとなりがちな筆者が、何の疑いもなくHARDを即時に始めてクリアまで遊んでいます。あそこで止められないですからね。
13. 煽り時計の誕生の旅
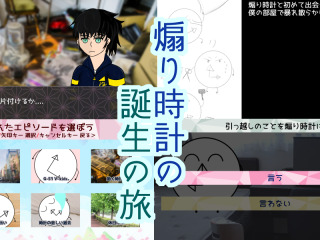
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 分岐式ノベル | んどどど |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 50分 | 1.04 | 読了 |
良かった点
- 煽り時計にマスコット的な可愛らしさがあります
- クリア特典がダウンロード式なのは面白かったです
気になった点
- キャラクターの台詞と地の文で内容が重複していることが間々ありました
- キャラクターが「電気工事の実習あったこと完全に忘れていたよ」と発言した後、地の文で「電気工事実習があることを完全に忘れていた」と書かれる、等
- 煽り時計について、特別煽っていた印象はないので名づけの由来が気になりました
レビュー
煽り時計の旅を追体験しよう
煽り時計の誕生の旅は、煽り時計と主人公の少年にまつわるノベルゲームです。
煽り時計と呼ばれることになる喋る時計との交流、そしてあることを契機に始まる旅路を描いています。
ホームドラマのような温かなやり取りを軸に、物語はいくつかの場面の元展開していきます。
その中では、煽り時計のマスコット然とした一挙手一投足を見ることができるでしょう。
物語を読み進めていき、煽り時計の旅の行く末を見届けましょう。
感想
タイトル通り、煽り時計の旅を見届けるゲームなのかなと思っていました。パートとしては旅をしていると言いそうな時間は僅かかもしれませんが、あるいは拾われてから戻るまでのすべてが旅路ともいえるのかもしれません。
煽り時計の構造は時折気になっていて、鼻提灯出せるし、はさみ持てるし、コントローラを持ってゲームができるらしい構造になっています。どういうサイズ感なんだろう。
鼻提灯を出せるということは息をしているということなんでしょうか。この辺を考えるのは野暮なのかもしれませんが。コントローラを持ってゲームができるなら指があるのかいやしかし、みたいなことを考えながら読んでいました。
後は、この世界の母親はかなり起きている現象に対して素直で寛容でした。自分の子供が喋る時計を持っていて、一日でそれを理解したり支援したりしているの、なかなかに肝が据わっているというか受容能力が高いというか。良い母親ですね。
オイルショックと時計が売れなかった相関関係が不透明だったり、新幹線で時計を落とすほどの人ごみになるのかなと思ったり、プログラマーの説明がアバウトだったり、なんやかんや引っかかるところはあれど、その辺は多分オマケで言及されているあたりによるものなのかなと思っています。
個人的に気になっているのは句読点の位置とか、台詞と地の文のバランスとか、どちらかと言えばそういうあたりでした。
筆者もこのレビュー、特に感想では徹底できてない所はあるんですが、句読点はダイレクトに読みやすさに影響を与えるので、長い文章を読むことになるノベルでは結構気を遣った方がいい分野なのかなと感じています。句読点がない長い文章、意味をとるのも難しい上に、結構文字による圧迫感もあるので。演出としてそういう意図があるなら構わないとは思います。
序盤あたりから抜粋すると、「こんな、コーナー初めて見たなぁ」の句点がある一方で、「誰も居ないし何も動かしていないのに」あたりに句点がないのは違和感がありました。「いいか、煽り時計しっかりと俺の~」あたりもでしょうか。
「こんな」がかかっているのはコーナーなので、この間に句点が入るのは違和感があったのと、中者は長い文章だったのでどこかに句点が欲しい気持ちになりました。後者については、文の区切り的には煽り時計の後ろに読点が入るか、「いいか煽り時計」までつなげて句点でもいいような気もします。呼びかけを明示化したいのなら、いいかの後に句点があるのが適切っぽくもあります。
地の文については、キャラクターの台詞の繰り返しがちょっと見られていて二度手間に感じることがありました。上記以外にも、「アメ ヤムマデ マツ」の直後に「雨が止むまで待つことにした」とかも該当します。
多分、地の文をそこからつなげるための役割があるんだとは思うのですが、その場合は台詞側をバタバタして何か探しているだけのものにするなどすればバランスが取れるかもしれません。
ちなみに筆者は物書きを嗜んでいたことはありますが、別に文系出身とかではなくバリバリの理系なのであんまり正しくないことも言っているかもしれません。ここまでのことは話半分で良いと思います。
さらにここからは個人的なお勧めになりますが、こういう文章の見直しをするときはボイロが便利です。入力した言葉をしゃべってくれるので、何となく違和感があると気付きやすいです。誤字脱字もチェックしやすい。
宣伝になって感想でなくなってしまったので閑話休題。
クリア特典がダウンロード式になっているのは面白い試みだなと思いました。ZipのパスワードとかURL提示は見たことあるんですが、確かにこれなら何が降ってくるかもわからないし、手に入れるのはゲーム内で完結していて楽ですね。
最後に、このゲームの一番の謎は煽り時計の名前の由来かもしれません。そんなに煽ってましたか。
加えて言うと、誕生の旅でもない気がしてきました。いや、煽り時計の旅をゲームとして作ったそれ自体は誕生の旅と見なすべきなのかもしれません。その場合は、煽り時計がここまで辿った道筋それ自体が煽り時計というキャラクターの誕生の旅と解釈すればいいんでしょうか。
14. プリティアックス外伝 ~斧姫~

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| AXE | HOT・W |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 5分+25分 | 1.1.1 | クリア/おまけクリア |
良かった点
- 脳みそを空っぽにしてAXEに委ねられる作品でした
- 戦闘においても、とにかく爽快感に振っていて気持ちいいです
- ツクール2000風の完成度が高いです
気になった点
- 特にありません
レビュー
AXE!!
プリティアックス外伝 ~斧姫~は、ひたすらAXEし続けるAXEゲームです。
ツクール2000風のタイトル画面から始まり、冒頭のイベントからも察せられる通り、全てがネタと勢いに振り切れた作品となっています。その勢いはエンディングまで留まるところを知らないので、思う存分AXEを装備してAXEし続けていくことができます。
このAXEは主に戦闘で力を発揮し、全身に装備すれば装備するほど連続でAXEしていけるようになります。全身AXEで身を包み、6連続攻撃を叩き込んでいきましょう。
また、エンディング後のおまけでは、リソース管理風のゲームにも挑戦できます。
制限化の中で、AXEやほかのスキルにも頼って上手く得点を稼ぐスコアアタックに挑むのも一興でしょう。
ひたすら頭を空にしてAXEのことだけを考えられるように、ゲームとしての作りも導線も丁寧かつシンプルな作品となっています。
心行くまでAXEに体を委ねましょう。
感想
今ウディコンにおいて最もタイトルで笑えた最高のゲームです。
ツクール2000でゲームを作ったことのある身としては、これ以上ないほどに見慣れた景色でした。エミュレートとしての完成度があまりに高すぎる。ネットミームのカニの画像を思い出していました。
その温度感のまま、最後までAXEで突っ走っていく本編も良いです。AXE一本槍で勢いを殺すことなく最後まで走り切ってくれます。AXE一本槍って変な言葉ですね。
AXE AAAAAXE あたりは叫んでいると解釈できるんですが、AXE PAIN あたりはもう良く分からないままノリで楽しんでいました。
なお、個人的に好きなところは木をなぎ倒して進める箇所で、敵を倒す以外にも爽快感を感じる仕掛けが用意されているあたりが良いです。
とはいえやはり真髄は戦闘で、ドリル装備っぽい感じで全身斧人間になって連続攻撃をぶち当てていくのは強い爽快感をもたらしてくれます。病みつきになりそう。
敵が障害というより斧を当てる的みたいな扱いになっている気がするんですが、とりあえず楽しいので満足できます。この規模感なら戦略性とか考えることとか要らないのかもしれません。気持ち良ければそれでいい。でも、ちゃんと魔王はちょっと強いあたりのバランス感もあります。
このあたりの小ネタとか、勢いを殺さないようにしている一画面マップとか戦闘テンポとか、ちょっとした敵のバランス感とか、勢いだけで構成されているゲームに見えてかなり丁寧に作られているあたりも個人的には好きでした。
そもここまでツクール2000に寄せて作るのは逆に大変に思えるんですが、それでも作り切っているあたりがすでに丁寧と言えるかもしれません。
なお、敵のパラメータまでツクール2000のデフォルトパラメータになっていると面白そうだなと思いつつ、手元にツクール2000がなく確認する手段がなかったので諦めました。HPくらいはそれっぽそう。
リソース管理っぽいおまけ要素についての話もします。
何ならこっちの方がプレイ時間が長いんですが、何度かゲームオーバーになったからです。
かなり運の要素が強いリソース管理ゲームで、AXEなり有効択を引いた後にひたすら強い敵を倒していくことになります。敵がランダムだったり、そもそもスキルなどもランダムだったりするので運によっては厳しいですが、引き直しもあってコツをつかめばクリアは割といけそうな印象を受けました。
さすがにスコアアタックをちゃんとやれば運の要素も強くなってきそうですが、それにしても上位陣のスコアは良く分かりません。何をやったらそんなに高くなるんだろう。
ツクール2000っぽさ、AXEで押し通すインパクトの強さと、とにかくプレイした後に強い印象を残す作品でした。この短さなのに、印象が心に叩き込まれています。
15. ウラミコドク

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 謎解きRPG | なごみやソフト |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 7時間30分 | 1.06.1 | 全エンドクリア |
良かった点
- 状態異常をギミックとした思考を使う戦闘が楽しめます
- レベルの概念は無いので戦略で勝ち切る必要があります
- 推理ものあるいは論破ものとしてのシナリオの完成度が高いです
- ヒントが用意されているので詰まることもありません
- その時のメンバーに応じた会話の変化など細かいところも作り込まれています
気になった点
- 最後のオチに関して、ギミックとしては素晴らしいですが展開としては若干強引なものを感じました
- この辺りは好みだと思います
レビュー
矛盾する言葉を祓え
ウラミコドクは、高い戦略性を備えた戦闘と、正しい証拠を突き付けて事件を解決に導く推理パートが融合した、RPGあるいはアドベンチャーです。二つの異なる方向性で頭を使っていく作品となっています。
基本的なゲーム進行は、会話のやり取りからなるストーリーとマップの探索を経ていくような、アドベンチャー然としたものです。デスゲームめいた展開の中、続発する事件の真相に迫るため、正しい証拠を選び出す推理パートに挑んでいくことになります。
推理パート中は証言の矛盾あるいは発展性を指摘し、その根拠となる証拠を提出する流れで進んでいきます。それぞれの発言を吟味し、既出の情報との矛盾や、より深めることのできる証言の選出などを通して、容疑者を絞り込んでいきましょう。証拠はアイテムのみならず、ゲーム中の様々な要素からも選出されます。あらゆる情報に目を配り、推理の糧としていくのが大事になるでしょう。
この推理フェーズをけん引していくシナリオもまた良質なものとなっており、次々と起こる事件と渦巻く不信感、その中での主人公やバラエティ豊かなキャラクターたちの行動が周到に描かれています。
また、その多彩なキャラクター達は全てプレイアブルとなっており、パーティを組んでダンジョンに連れていくことで好感度を上げつつ主人公との会話を見ることもできます。気になるキャラクターや気に入ったキャラクターがいれば連れ回すのも良いでしょう。
さらに、良質なシナリオからなる推理パートに引けを取らず、むしろ本丸と言って遜色ないのが戦闘パートです。ストーリーが一区切りつき、マップを探索するタイミングになったら、好きな時にダンジョンへ挑んで戦闘に臨むことができます。
ダンジョンはコンパクトながら簡易なギミックも搭載されており、それらを突破しながら進んで雑魚敵を倒していき、最奥に待ち構えるボスを倒していくのが目標となっています。挑戦することになる各ダンジョンはストーリーを阻害しない程度に短く収まっていながら、その攻略は一筋縄ではいかない壁としても成立しています。
ダンジョンひいてはボスの攻略に重要となってくるのは、状態異常の理解と運用、そして各キャラクターのスキル仕様と敵の攻撃の性質の把握です。
戦略のベースとなる状態異常は基本的なものでも十種を越え、特殊なものを含めればそれ以上となります。敵味方のスキルも状態異常に密接にかかわるものが多いため、状態異常を制したものが戦いを制することとなるでしょう。
状態異常を熟知していけば、一部状態異常が重複しないことを利用して自身にデバフがかかるスキルをあえて多めに運用するなど、トリッキーな戦い方を選ぶこともできます。ボスに挑んで行動パターンや状態異常を捉まえ、こちらのスキルでどう対応していくかを考えていきましょう。
おおよそいつでもパーティーを変更することができるため、どうしても勝てなさそうなら組む相手を変えてみるのも良いかもしれません。
このように、証言と証拠とにらめっこして推理を導くストーリー、強力なボスをいかに攻略するかの戦術、その双方が別ベクトルの頭の使い方を要求するため、思考の交互浴のような体験を得られる作品となっています。
並みいる強敵を打ち倒しながら、事件の真相を解き明かしていきましょう。
感想
ギミックバトルも好きだし推理ものも好きなので、好きと好きが掛け合わさって、すごく好みの作品です。
双方ともクオリティが高いというのがそれに拍車をかけていて、どっちを摂取しても楽しいゲームになっていました。
とりあえずギミックバトルの方の話をします。
雑魚戦はダンジョンの賑やかし、あるいはこちらの技を含めた予習としての役割を担っていて、それを完遂する程度のボリューム感で良かったです。多すぎず少なすぎずの良い塩梅。
もらえる巫の総量からしても、全部倒さなくても良いバランスにもなっている印象でした。そもレベルアップがないので、倒さないこともある程度推奨されていそうです。
真打というか真髄はやはりボスとの戦闘で、状態異常を軸とした戦略性の高い戦いが楽しめます。
相手のギミックをつぶし、こちらのギミックを通すための立ち回りを考えて動くのが楽しいわけですが、これは敵の多様なギミックと、それに負けない味方サイドのバラエティ豊かな技構成によって下支えされています。
基本的な概念としては状態異常とフィールドと考えるべき対象は少ないながらも、そこから様々な方向へ広がっていく多様性は相手にしていても自分で使ってみても楽しいものとなっています。
個人的に好きだったのは実際のBGMのテンポも変えながら攻守をコントロールする歌と、こちらの有利を押し付ける天気の制御でした。フィールドの制圧が好みなのかもしれない。
反対に、トリルと鈴による行動制御と回復や、結界術あたりのテクニカルな所は上手く使えなかった印象があります。特にトリルが難しかったですね。結局キヨヒメをトリルパーティーで倒すのは諦めて、慣れていたクルハとユミヤのタゲとって高火力で押しつぶすパーティーで攻略しています。パワーでごり押せる余地があって助かりました。
他のメンバーについても、盲目というシンプルな状態異常を最初に持ってきつつ、異常を自身に付与するアタッカーやら回復性能が高いキャラやら特定ターンに強いキャラやら未来に攻撃するキャラやら、それぞれの特徴を上手く使って戦えると楽しいキャラが多いので、こちらから戦略を仕掛けていく楽しさが十分に担保されています。
相手のギミックを攻略するという側面自体ももちろん楽しいんですが、こちらのやりたいことを通すという戦略性もまた楽しく、この両輪が上手くバランスされた戦闘なのが良いです。
相手のギミックという点で言うと、ボスの中で楽しかったのは最終決戦感が強かったのもあってラスボスでした。ほとんど使っていなかったピンキーとマナエを軸に据えて戦わないといけないヒリヒリ感もあって良かったです。下記のリザルトからも分かるんですが、最後ということを差っ引いても一番苦戦している気配を感じますね。
一番難しかったのはキヨヒメで、前述の通り最初に挑んだパーティーで何度か負け、パーティー構成から考え直して倒しています。特にクリティカルがしんどく、相手の残り体力僅かの所でクリティカルが連発しなければ勝ちという盤面までは行けたんですが、クリティカルが連発して負けました。
なお、遭遇率97%なのはなんとなく引っかかるので何とかしようとは思っていたんですが、図鑑から出現個所が推察できなかったので断念しました。
多分敵をスキップできるあの迷宮なんじゃないかとは思うんですが、自信がないです。あの迷宮ならほぼすべての敵をスキップした記憶があるので可能性が高いんですが、いなり寿司の可能性もちょっとだけあります。
| ボス | 仲間 |
|---|---|
続いてシナリオの話をします。
設計としては変則的な密室推理もの、あるいはデスゲームっぽい雰囲気です。インシテミルが印象としては近いでしょうか。状態異常や技能を含めた特殊な設定を加味した推理劇というあたりは、折れた竜骨やアンファルを彷彿とさせます。
ともかく、変則密室デスゲーム特殊設定付き推理ものという色々盛りだくさんな内容になっていて楽しめます。
シナリオの運びも綺麗で、 何かしそうなやつを先にどんどん殺していきます。加害者ポジになりそうな奴から潰していっている印象で、被害者が明確に選ばれている感覚を覚えました。作劇が上手い。
ゲームシステム的に推奨というか想定されていそうなメンバーの入れ方とその退場のさせ方も上手いので、メンバー構成をいじらなければキャラクターについて知ることが出来た上で推理に突入することができるようにもなっています。上記仲間の信頼度を見ても分かる通り、大体満遍なく信頼度が上がり、そこから退場していきました。
推理ものとしては徐々に証拠が出そろってくるタイプなので事前に推察するのは難しいか不可能ではありますが、その分論理と共に証拠が出てくるので推理そのものは筋道立てて行いやすくなっています。
さっきまで仲間にしていた彼女、そういえばああいう特性があったよな、みたいな戦闘パートの情報も使えるあたりも面白いです。戦闘で色々触っていたことがシナリオにもつながっている感覚を得られます。
なお、推理システム的にはダンガン□ンパなんだろうなと思いつつ、それほど該当作品を知らないので詳しいことは分かりません。
個人的には祓いと倣いがあるのが良くて、一方的に論理の破綻を突くのではなく、時には論理から発展させていくことも思考に入れる必要があるので、考えに奥行きが出ます。
証拠提出については、おおよそ議論を追っていれば推測できる範囲のもので、ちょくちょく誤解はありましたが大体は一発で通せる納得感があります。誤解と言っても、水の話があったからリアのアクアバレットで穴をあけるんだと思ってた、とか、血の所在を血封居断で血がついたのかと思ってた、といったレベルで、そうでないなら別の方に思考を飛ばせる程度の勘違いです。
とにかく全体を通して先が気になる謎をちょくちょく撒きつつ、一つ一つの事件を完成度高く組み立てることで各シーケンスのレベルでも満足感の高いシナリオとなっています。その情報がそこにつながるんですね、と膝を打ちながら楽しんでいました。
ここからは個人的なシナリオに対する感想になるので、蓋然性も客観性もへったくれもない話になります。
インシテミルやそして誰もいなくなったといった作品に触れていた影響もあって、頭の片隅にジュジュが残り続けていたゆえに最後の展開を十全に驚けなかったのが若干心残りになっています。あの辺の記憶を消せればもっと楽しめたはず。
あとは、最後の最後のシステム的な大オチは凄い好みで、叩きつけるべき対象が明瞭であり、かつそれは第4の壁を壊してみれば違和感しかないものである、というのはかなり良かったです。一方で、物語の展開としては第4の壁を登場させる導線が弱い印象で、やや唐突な感じを受けていました。
最後に、ゲーム全体の話をします。
ゲームとしては戦闘パートとADVパートがある程度明確に分かれていて、ADVパートから戦闘パートを参照することはありますが、基本的に関わりはありません。技能についても、説明だけなら戦闘パートが必要とも限りません。
そういう意味では、分岐としての意味はあれど、それほど密接なつながりはない設計という印象を受けます。
しかし、それぞれのパートが独立して完成度が高いゆえに、戦闘パートをやって頭を使ったギミックバトルを楽しみ、それが終わったらADVパートで別の頭を使った推理劇を楽しむという交代浴みたいなことができて、これが個人的には好きな体験でした。
どっちもやり続けると飽きか疲れがきそうなんですが、適度に交互に楽しむことでずっとプレイし続けるモチベーションが継続します。双方高いレベルで完成されているからこそ成し得る技なので贅沢ではあるなと思いつつ、RPGにシナリオがあると嬉しい理由の一つなんだろうなと納得していました。
ボスを攻略していく戦闘が楽しめる方ならお勧めですし、推理もの好きな方にもお勧めですし、両方好きなタイプには間違いなくお勧めできる作品です。
16. めっちゃ危険なダンジョンだろうとみんなで潜れば怖くない

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| デッキ構築型半自動戦闘 | Qbit |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 3時間 | 1.01 | エンディング |
良かった点
- 演出が少なく淡々と進行するのでテンポが良く、ゲームに没入できます
- 数の暴力に対して、より多い数の暴力で蹂躙していく楽しさがあります
- 各ダンジョンごとに特色があって面白いです
気になった点
- カードの種類が少ないため、ビルドは単調になりがちです
- ただしデッキ構築だけのゲームではないので、戦闘面で単調になるといったことはあまりありません
- 戦術書が始め何のことだか分かりませんでした
- 緩い用語説明が本棚なりのどこかにあると嬉しいです
レビュー
みんなで戦えば強敵も怖くない
めっちゃ危険なダンジョンだろうとみんなで潜れば怖くないは、自動戦闘をデッキ構築と数の暴力で攻略していくゲームです。次第に難易度の上がっていくダンジョンに挑むにあたり、適宜ユニットを雇って数に頼めるような兵の運用を上手くこなしていくことになります。
ゲームはいたってシンプルに、ダンジョンを攻略し最下層まで到達することが目的となっています。
いくつかのイベントが待ち構える部屋とそれをつなぐ通路からなるダンジョンを探索し、ユニットが全滅しないように気を配りながら進んでいきましょう。
各部屋で発生するイベントは敵との戦闘のほかに、カードを集めたり、トラップがあったり、回復ポイントであったりと様々です。これらを見極めて訪れる順序にも気を付けたいところですが、あまり長く探索すると食料が底を尽きかねません。バランスを保った探索が攻略のカギとなるでしょう。
| 自律したユニットの戦闘 |
|---|
そうして探索していく過程で発生する戦闘においては、事前に組んだユニットの編成とダンジョンで入手したカードが大事になってきます。
戦いは、一画面のエリアを各ユニットがほぼ自動で動き回ることで進行します。敵と味方のユニットがもみくちゃになって戦う最中、プレイヤーは大まかな移動指示と、デッキから引いたカードを用いてスキルを発動させることで干渉することができます。
特に後者は指定のエリアに強力な効果を与えるため、ダンジョンを巡ってカードを集めて、そうして得たスキルを効率よい位置とタイミングで発動させていくのが勝利への近道です。例えば、上記の画像のシーンにおいては敵の密集地に攻撃スキルをかければ、近接攻撃を仕掛ける味方も多いため効率よくダメージを与えられます。
こうした戦闘の趨勢を握る味方ユニットの位置取りや編成、初期に持つカードのデッキ構成は事前に組むことができる一方、それぞれのユニットの成長やカードの拡張、強化はダンジョン攻略中に行う必要があります。
自分なりの構成を見つけた上でダンジョンを上手く立ち回ることで、初めて戦闘に向けた編成は熟達し完成へと近づきます。準備とアドリブの双方の力で、階層を進むにつれて強力になっていく敵を攻略していきましょう。
また、どれだけ強い敵でも数の暴力の前には膝を突きます。ダンジョンの攻略が難しい場合は、数に頼んでユニットを整備するのが重要な一手となります。反対に、どれだけユニットとスキルを強化しても敵の数が多すぎると押し負けるため、増やしたユニットに欠員が出ないように立ち回ることも大事です。
デッキ構成、ダンジョンの探索加減、戦闘の塩梅を上手くコントロールし、みんなの力を効率的に運用していきましょう。
感想
色々とそぎ落とされてゲーム性だけが高純度で抽出されたようなゲームなので、気付くとずっとやってるタイプの作品です。慣れると色々効率的に回せるようになるのもあって、無心で上手くパーティーを回していけるようになります。
ともすれば淡泊とも取れそうなくらい華美な装飾の一切を排している印象を受けるんですが、個人的にはそれがゆえにのめり込める面もあるので好きです。テンポが良いとかそういうレベルの一つ上で、プレイしていて阻害される感覚がないというイメージ。
最初は敵の数の暴力に圧倒されがちだけど、ちゃんと目的をもってプレイして数を増やせば逆に数の暴力で圧倒出来るあたりはタイトル通りのコンセプトで楽しいです。もちろんデメリットもあるので一概に最良の策とは言えないのかもしれませんが、それもパーティーバランスさえ考えれば大体カバーできます。とにかくみんなで潜ればどれだけ敵がいても怖くない。
個人的には物持ちが良くてもどうせアイテムは使っていくことになってポーションくらいしか運ばないことを考えると、キャリアーの優位性は低く感じました。キャリアー入れるくらいなら豚入れたほうが良いかもわかりません。
操作性も良くて、マウスによる簡単操作とWASDによる移動もあって、キーボードと併用するとかなり軽快に動けます。利便性が高い。
最初のルールや独自の用語に対して惑うことはあるかもしれませんが、慣れてくれば大して気にせずに諸々のシステムを使っていけます。中でも、戦術書が最初に見た時に一番困惑しました。要するにランダムカードが封入された初期デッキではあるんですが。
戦闘面で言うと、最初の内は色々指示を出しつつカードを使っていき、慣れてくれば8倍速と一時停止を駆使するターン制みたいな戦い方に落ち着いていくことになります。結局カードが使えないとアドリブはそんなに効かないので、必要なタイミングで静止するゲームではあるんですが、状況に応じた選択は依然必要なので色々考えながらプレイできます。
8倍速でも軽快に動作してわちゃわちゃと動く仲間を見るのも結構楽しいですね。
一方でカードに関しては種別が割と少なく、ビルドは単調になりがちな印象があります。デッキに入れられるカードも多く、取得時の選択肢も多いのがこれをより強めています。当意即妙にやるというよりは、強いカードを集めていく形が多い印象です。
ただ、ビルドの方向が単調になっても、戦闘自体がカードが軸であってもカードに強く依存したものではないので、ダンジョンの攻略自体の楽しみはあんまり損なっていません。そういう意味では、ビルド構築要素は時々のフレーバーというか、味変くらいの感覚として楽しめます。
個人的なビルド構成としては、フラッシュの強化を2枚くらい入れて、あとは怨返しをできるだけ入れつつスマッシュの強化版で埋めたデッキを目指していました。適度に強化型火事場の馬鹿力で火力を強くしています。
ここに遺物の中でもお気に入りのコスト+1効果を持つ指輪を付けることで、1ターンでかなりの行動が打てるようになります。雑魚の殲滅は早期解決が鍵なのでかなり強い。
遺物についても触れておくと、個人的には上記の指輪がだいぶ強い印象を受けました。単純に常時動ける選択肢が増えるわけなので、弱いわけはありません。この手のゲームでは、大体行動回数の増加は最強の効果になります。
他の遺物が弱いというわけではありませんが、この遺物が強すぎて手に入れてからはこれを使っていました。検証したわけではないので、ちゃんと使うともっと強い遺物があるのかもしれません。
ついでに個人的な攻略のやり方についても触れておくと、ダンジョン探索はできるだけしたほうが良いと思っています。
お腹が空くデメリットはあれど、戦闘によるポイント稼ぎの方が遥かに重要になってきます。
レベルアップで割と強くなれるので、これを積極的にやっていきつつ、焚火は極力強化に使っていけると伸びていきます。血のスキルは回復が狙い目で、上手く使えれば戦闘前より体力が回復していることもあります。序盤に拾えたらラッキー。
あとは、ダンジョンにいろいろとパターンがあるのも良かったです。ギミック面で緩い個性があるので、同じことをやっている感覚が薄くなります。
演出が極限まで省かれているので、倒壊した家に巻き込まれてダメージを受けていたことにしばらく気付いていないなどはありましたが、この辺が差っ引かれているおかげでテンポが物凄くよいという側面もあります。
プレイしていけば分かることではあるので個人的にはこの割り切りは好きなんですが、演出がないと分かりにくいという点は否めないかもしれません。
ダンジョン内における戦闘へのシームレスさや、ダンジョン内のイベントのシンプルさ、直感的で利便性の高い操作性の要素が重なり合って、意識を大きく割くことなくゲームに集中できる設計の作品でした。
ダンジョン外のエンディングまでのループでも、ダンジョンに潜って仲間を増やして、またダンジョンに潜っていく一連の流れが上手く動いていて、途切れさせない仕組みになっています。
とにかく無心でエンディングまで続けられるゲームでした。
17. 前進中の迷い人他四種のミニゲーム
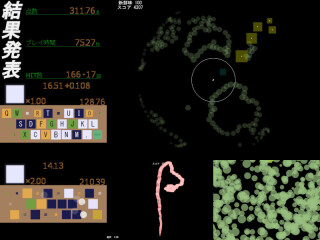
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ミニゲームオムニバス | ブ瓶 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 20分 | 1.0 | 3922 / 15050 / 202700 / 60812 / 199.89 / 250.99 |
良かった点
- 色々なミニゲームが遊べます
- 表題作では、思ったよりまっすぐ進むことを意識するのが難しいことが分かります
気になった点
- 特にありません
レビュー
ミニゲームを遊ぼう
前進中の迷い人他四種のミニゲームは、そのタイトル通りミニゲームが取り揃えられたオムニバスです。
操作も画面もシンプルなゲームをサクッと遊ぶことができます。
表題となっている前進中の迷い人では、何も指標のない中で直進することのままならなさを味わうことができるでしょう。ただ前進し続けるというのも意外と難しいものです。
それ以外にも趣旨の近いゲームからそうでないものまで、5種のゲームを短い時間で遊べます。漫然と遊んでプレイの軌跡を眺めるもよし、性質を捉まえてハイスコアを目指すも良し、好きなやり方で取り組んでみましょう。
感想
前進中の迷い人、まっすぐ進んでいるつもりがいつの間にか変な方向に向かっているあの感覚を思い起こさせて良いゲームでした。
現代というか現在はスマートフォンもあるので、地図を見ながら進めばそんなことはないんですが、子供時代にそういうのがない時に家に帰ろうとして良く分からなくなった経験があります。真っ直ぐに見えるのに微妙に斜めになっている道とかが鬼門。
前進中の迷い人に関して言えば、道のような分かりやすい目印もないので、暗中模索な気分になれます。多分真っ直ぐ進んでいるだろうと思いつつ、若干不安になる気持ち。
最後に進んだ距離だけでなく道が図示されるのも良くて、明確に道を誤ったタイミングとかが見えてきます。50mプールで目をつぶって泳いでいたら変に曲がるのにも近いのかもしれません。
エンドレスまでくると、落ち着くことにもやや意味が出てくるのも良かったです。複雑な地形に阻まれたら一回止まるのも割と良い選択肢な気がします。
緑を求めては、迷い人と割とプレイ感は近いです。こっちの方が、ミニゲームとしては素直によく見る形式な印象。
いわゆるイライラ棒かつ操作性に癖があるタイプなんですが、ある程度前進中の迷い人で慣らされているので、意外と攻略できるようになっています。エンドレスはこの練習だったと捉えられるかもしれません。
手回し世界旅行は最終的には留まる選択肢をどこまで取れるかのチキンレースっぽかったんですが、そこまでは詰めていません。常時チキンレースするのは、それはそれで楽しそう。
これも最終結果が図示されるので、それを出来るだけ綺麗な円を描くようにこだわっていました。それでも十分ボーダーに乗るように目標スコアを定めてくれていたので助かります。
いろおとしは地味に難しかったです。手元にあるキーボードが軸のタイプなので、流れるように押すのが難しかったように思います。タッチスクリーン対応デバイスを引っ張り出してこようかと思いましたが、調子が悪かったので断念しました。
余談ですが、何がいろおとしなんだろうと思っていたらちゃんとあとがきに書いてあります。そういう設定だったんですね。
一つ一つはさっと終わるものの詰め合わせなので、飽いた時間にやるのに向いていました。
スコアがあるとハイスコアを目指したくなる人にとっても色々楽しめるんじゃないでしょうか。筆者はあんまり詰めるタイプじゃありませんが。
18. ビャッコーギャモン
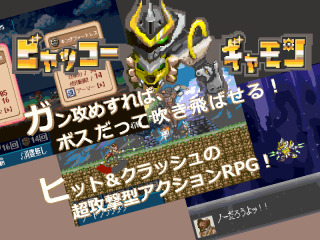
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| アクション | こげ(ヒワイロボ) |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 5時間 | 1.45 | クリア |
良かった点
- ドット絵のクオリティが非常に高く、美しく世界とキャラクターが描かれています
- 芝居がかかった台詞回しと、それに遅れを取らない熱い展開を持つシナリオでした
- 適切なガン攻めが最適解となるアクションの設計のおかげで、ボス戦が非常に楽しいです
- 回避によるクールタイムのリセットのおかげでガンガン前に出る意思が働きます
気になった点
- 最初のネームドボスであるメズルが他と比してもかなり強い印象を持ちました
- 何となくモーションからの猶予時間が長いために拍が合わない印象があります
レビュー
振りかざす太刀の下こそ地獄なれ 一と足進め先は極楽
ビャッコーギャモンは、熱いシナリオと高い難易度のボス戦とプラットフォーマーがないまざったアクションゲームです。
敵の攻撃にむしろ向かうような行動に対してリターンが大きいシステムが備わっているため、常にリスクを取ってガン攻めし続けて脳内麻薬が出るような戦闘を味わえる作品となっています。
ゲームの基本的なデザインは、プラットフォーマーとボスを軸とした戦闘寄りのアクションです。雑魚敵を打ち倒しつつ進行していき、エリアの奥地で待ち構えるボスと戦うというのがステージの構成となっています。
ステージの道中で戦うことになる雑魚敵は雑魚と言えども癖がある敵も多く、ボスまでたどり着くにはそれなりに攻略法を見出す必要があります。加えて強化アイテムを見つける探索要素もあるため、ボスまでの道程も気を抜くことはできません。
とはいえ、この作品の圧巻は間違いなくボスとの戦いとそれを支えるゲームシステムにあります。
ボスが備えるバリアバー、プレイヤーが備えるヒートゲージとその取扱いによって、ボスとの戦いはスピーディーかつリスクとスリルのあるものとなっているからです。
ボスが持つバリアバーは怯みの耐久値のようなものです。これを全て削り切ると一定時間攻撃に対してノックバックするようになります。これを利用することで、手痛いダメージを一方的に加えるチャンスが得られます。
バリアバーは放っておくと回復するため、これを狙うにはとにかく攻撃を絶え間なく浴びせる必要がありますが、ただ攻撃ボタンを連打していれば良いというものではありません。ここで登場するのがヒートゲージです。
プレイヤーは三種の武器を使い分けて攻撃を繰り出していくことになりますが、この度にヒートゲージが溜まっていきます。これが最大まで溜まると一定時間攻撃できなくなってしまいます。
ヒートゲージを適切に保つためには攻撃頻度を調整するのが安全ですが、バリアバーを削り切るためによりリスクの大きい行動も取れます。相手の攻撃を上手くローリングで回避することで、ヒートゲージを減らせるというシステムを使い倒すことです。
畢竟、バリアバーを最大効率で削り取りたいのであれば、攻撃を間断なく加えつつ、適切なタイミングで回避行動をとって敵の攻撃をすんででかわしていくことになります。
もちろん機会を伺ってタイミングよく攻撃を与えていくヒットアンドアウェイも良いですが、敵の攻撃は被弾せずに済ますのが難しい程度には苛烈です。戦闘が長引くほど不利になりやすいので、敵の懐に入り込んで息つかせぬ攻防を繰り広げることが攻略において大事になってきます。一歩前に踏み出る方が、むしろ有利です。ガンガン前に出て戦っていきましょう。
このシステムの上で相対することになるボスは、その戦う地形から使ってくる技までバラエティに富んでいます。リトライ性は高いので、何度も挑戦して地形に即した立ち回りの学習や、それぞれの行動の予備動作の熟知、対する自分が行うべき攻撃パターンの用意をしていきましょう。
攻め続けていれば、一戦一戦の時間はそれほど長くなりません。テンポよく再戦し続けてコツをつかむのがお勧めです。
そして興奮が最高潮に達するような戦闘システムに相応しく、ステージ進行とともに紡がれるシナリオもまたテンションを最高潮に上げるものとなっています。芝居がかった台詞回しをもって進行していき、やがて全てを巻き込み雪崩れ込んでいくその展開は、否応なしに感情を掻き立て、強力なボスにリトライを重ねて打ち倒す原動力となることでしょう。
加えて、美しいドット絵とそれに裏打ちされた演出力をもが合わさることでシナリオはより高次元へと引き上げられ、大きく魂を揺さぶるものとなるでしょう。
とにかく、気持ちを最高の状態へともっていく熱いシナリオと、脳を焼き切るような戦闘が楽しめるゲームシステムにより感情を引き上げてくれる作品となっています。
並みいる強敵を打ち倒して、ぜひともそのシナリオの終わりを見ていただきたいです。
感想
全編通して素晴らしい作品であることはもはや疑い得ないんですが、私個人の感想に限って言うならば、終盤のすべての展開と演出が最高の作品でした。終わりの方はずっとプレイできることに感謝しながらやっていました。序盤で洗脳能力で語尾がゾだと食峰っぽいですねとか考えていた雑念が全部吹き飛んだ。
本当に終盤のシナリオの運び方と演出に関しては、過去やったゲームの中でも一つの最高峰に位置しています。巧さも勿論あるんですが、何より熱さという観点では比肩するもののない物語でした。
このままシナリオについて無限に話す前に、アクションゲームとしての話をします。
プラットフォーマーのような側面は多少ありますが、基本的には差し合いが楽しめるアクションです。道中でも割と歯応えがあり、きっちり対処できる動きをマスターしていなければ突破するのは難しくなっています。
このあたりの難易度の塩梅は絶妙で、地理的要件で上手いこと雑魚を強くしている印象でした。落下一発死亡+竜は中でもだいぶ強敵で、忍者龍剣伝みたいなやられ方をします。
そうした難易度は高い一方で、長い面ではショートカットが開通するなど、ある程度のラインにまで習熟できていれば突破できるように上手く抑えられてもいました。稼ぎ要素もある程度の救済措置として機能していて、自機能力を引き上げればかなり有利に立ち回れるようになっていきます。
武器の変更は積極的に行ってスタンスに合う武器を見つけていったほうが良いですが、ある程度良い武器に出会えたら性能につっぱするのもアリです。
この武器のバラエティもかなり良く、それぞれがピーキーな性能を持ちつつも、どれも使いこなせば強力に作用するようになっています。どの武器も十分に一線で活躍できるがゆえに、プレイスタイルに合わせたチョイスが楽しめる作品でした。
個人的には近距離ガン攻めが好きなので靴と斧が好みで、ここに距離を取らざるを得ないところでちょっかいをかけられるアンカーを入れた構成を主に使っていました。
殊に斧は強武器だと感じていて、火力も反射も取れる優秀なパーツで色々と助けられました。その一方で、このゲームにおける最強行動のローリングに合わせるとやや弱体化するのが本当に良いバランスとなっていて、ローリング即攻撃でない最大を取りたい時は細かいテクニックを要します。
靴もそうですが、闇雲に振るとかえって不利状況に陥ることもあるので、近接でボタン連打するのではなく、ある程度テクニカルに立ち回る必要があるのが面白いところです。
他方で盾やバイクはあまり使いこなせませんでした。盾に関しては防御性能がある上に遠距離攻撃手段があり、一部ボスでは刺さったかなという印象ですが、どうも待つのもカウンターもあまり向いていないようで被弾が増えてしまっていました。難しい。
バイクに関しては移動特化の武器と思いきや割と実戦的でもあって、上手く使えると割と重宝するところもあるのですが、使用難度が高い印象でした。これを上手く使える人は凄い。
そして、このゲームのアクションとしての圧巻であるところのボス戦ですが、どのボスも歯ごたえがありつつ、スピーディーで対応力を要求される戦いが堪能できるようになっています。
話が取っ散らかりそうなので、まずはシステムに即した話をしようと思います。
まずは武器の耐久制限があることにより、残数に応じて異なる立ち回りを要求されるのが面白いです。
残数を把握して打ち込みつつ、現在使える行動をもとにボスの行動に回答していくことで、早いゲームスピードのもとで常に思考を回した戦闘が楽しめます。耐久制限自体はそこそこネガティブな仕組みですが、比較的早く回復する点と、最後の一撃が強化される点で上手くポジティブな要素が混ぜられている印象でした。最後の一撃を上手く当てられると気持ち良い。
加えて、バリアバーの存在とヒートゲージの仕組みが、ボス戦における戦闘のテンポを劇的に上昇させ、密度の濃い体験を提供してくれます。
バリアバーを削り切れば特大リターンが待っているので、可能な限りコンスタントに攻撃を当てることに強いインセンティブが生まれ、思考が攻撃よりの構成に傾いていきます。結果、ある程度被弾しても上手く殴ることができればトータルで得なので、ガンガン攻めていく気持ちが形成されていきます。
一方で、闇雲に攻撃してもヒートゲージが溜まって攻撃できなくなってしまう都合上、どこかで攻撃を上手く避けて回復するタイミングも必要です。このため、こちらから敵の攻撃をローリングで迎えるように戦うのが良い選択となってくるため、前へ前へというモチベーションも作られていきます。
この二つの攻めることを肯定するシステムにより、否が応でも死線の中にいることになります。「振りかざす太刀の下こそ地獄なれ 一と足進め先は極楽」という宮本武蔵(もしくは柳生宗厳)の言を思い起こさせるゲームシステムです。一歩踏み込む方がむしろ生存率は上がる。
そうしてバリアバーを削れば、相手をノックバックしてある程度ハメられるような攻撃優位な設計をしていながらも、立ちはだかるボスに勝つのは難しいという難易度もまた素晴らしい完成度となっています。
ボスごとにバリエーション豊かな攻撃手段とパターンを持っているため、それぞれに対するローリングや攻撃といった回答を用意しておきつつ、時には位置関係や武器の残数に応じたアドリブを上手くこなしていかないと満足に勝利することはできません。
敵の攻撃は苛烈を極めるため、攻撃に対する反応の精度を上げていくことが重要になってきます。ローリングは強いけど万能ではない。
個別具体のボスの話をしていくと、個人的に強かったのは最初のボスと最後のボスです。後は憤怒にやや苦戦したくらい。最初のボスで若干心が折られかけました。
なぜかメズルの攻撃に対する拍というか呼吸が合わず、攻撃に対するローリングのタイミングや後隙の狩り方を指が覚えるまでにかなり時間を要していました。後々のボスはある程度リズムが合ったことを考えると、単純にメズルのモーションと私の感覚との間にズレがあったような気がします。この辺はもはや個人の感覚ですね。
最後のボスは最後に相応しく強かったんですが、ここまでくるとシナリオの暴力により諦めるという選択肢が脳内から排除されていたので無心でリトライしていました。あそこまで進めてクリアしないのはノーだろうよ。
絶妙に戦いにくい地形をしているのもにくいところで、立ち位置に応じてかなりアドリブが求められるのが楽しかったです。攻撃手段のパターンだけでなく、どこで何をしてきたらどうするべきか、くらいの判断力と経験値が必要になります。
この辺りでグラフィックにも触れておきます。
ドット絵のクオリティについては比類無いといって過言とならないレベルで、精緻でもありながらアクションゲームとして落とすべきところはそぎ落とされて分かりやすく、外連味と派手さを両立させた美しいものとなっています。
これを一言で言い表すなら商業レベルなんですが、その言葉に押し込めておくには役不足の凄まじい力を持った画で構成されていました。
開幕いきなりのアニメーションを伴った演出からステージを抜けた先の壮大な風景まで、圧倒的なグラフィックの力でもプレイヤーをけん引してくれる作品でした。一切の隙が無いですね。
シナリオが良いことは言うまでもありませんが、そのシナリオの熱が十全に表現されたグラフィックと演出があるがゆえにその魅力が幾倍にもなっているであろうこともまた疑い得ないでしょう。
なお、FF6プレイヤーとしてキャラクターが高笑いするドット絵のモーションがある作品は名作だと思っているので、こちらの作品は当然名作です。間違いない。
最後にシナリオに言及しておきます。
魂が熱くなるシナリオです。
もちろん、バディものっぽい雰囲気で進行していきながら適度に謎や伏線を撒いている序盤から中盤についても構成力が高い作品となってはいますが、何といっても圧巻は終盤の展開でしょう。
それまでに積んできた伏線を最大限に活用し、かつ最大限のテンションで収束させていった手腕には脱帽としか言えません。
そうしてメズルがその身一つで乗り込んでいく展開に至ってしまえば、そこからは常に最大の熱量をもって物語が展開していきます。
高難度のラストダンジョンを抜け、最後のボスを打ち倒すに余りある熱量を抱えたままエンディングへと流れ込んだ先でOPの反転を示し、ビャッコーを打破するその画の決まり具合といったら最高以外の言葉が見当たりません。
ナールジャメルの戦いも、虚数空間での流れも、そして最後にすべてが収束する流れまで、あらゆる面で完璧でした。拾い集めた虚飾がすべて反転して仮初の主が真なる主として帰還するのはあまりにも熱い。
ここに至るまでにメズルがめちゃめちゃ弱いことが分かるアクションパートが挟まれているのもシナリオに強い影響を与えていて、それがゆえに王の帰還に感情が乗ります。ゲームシナリオとして美しい設計をしていますね。
プレイ後の感覚としては、あまりにも良いものを見たという気持ちで支配されていました。
細かいシナリオというか掛け合いの話としては、言い回しが好きというのもありました。
個人的に芝居がかった語り口が好きなので、他愛ない幕間でも気分が上がります。この言い回しから展開される熱いシナリオを読むために、苦難に満ちたアクションに何らの躊躇なく突っ込めるというものです。
さらに細かい話をすると、武器に一つ一つフレーバーがついていたり、進行度に応じて拠点の会話が若干変化していたりと、細かい世界観の配慮も欠けていないのも良いゲームだなあと感じていました。神は細部に宿りますからね。
グラフィックは完璧でシナリオは魂を揺さぶりゲーム性は骨太のガン攻めアクションが楽しめる、何一つ抜けのないゲームです。難しいことは難しいですが、それを超えるモチベーションもあれば達成感もある作品となっているのでぜひともプレイしてほしいゲームですね。
19. その日暮らしの冒険補償
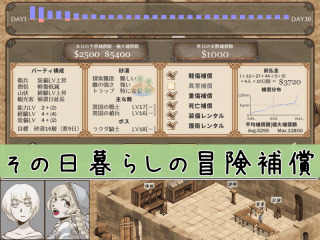
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 自転車操業系保険会社経営SLG | ハッピーエンド過激派 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 40分 | 1.06 | ノーマルクリア |
良かった点
- 保険というシステムを上手くシミュレーションに落とし込んだ作品でした
- 操作性が簡単かつ良好なのでサクサクと進めます
- パラメータだけの文字情報しかありませんが、それぞれに対して徐々に感情が湧いてきました
気になった点
- 実際に結果が分かって補償が確定するのが数ターン後のため、どの判断でミスったのか分かりにくいと感じました
- 現在進行中の冒険者のデータがどこかに出ていれば分かるかもしれませんが、情報の優先度を鑑みても入れられる箇所はあまりなさそうです
レビュー
保険を与えてリスクヘッジ
その日暮らしの冒険補償は、冒険者に保険を与えて経営を上手く回す自転車操業系保険会社経営シミュレーションです。
遊ぶことで保険の仕組みのその一端が分かることでしょう。
ゲームのシステムは保険をシミュレーションに落とし込んだものとなっています。回復薬を満額で買うことができない先立つもののない冒険者からあらかじめ安めのお金をもらい、もし必要になったら回復薬のコストをこちらで負担する、といったようなシステムを運営していくことになります。
確率的に怪我しなさそうな相手には安めのお金をもらえば割に合いますが、明らかに無茶した冒険者には多額のお金をもらっても割に合わないこともあります。確率的に見極めて、適切な対処をしていきましょう。
| 保険内容の一例 |
|---|
そうして保険の成約をし続けていくと、保険の中身は拡充されオプションが追加されていくことになります。冒険内容を鑑みてオプションの付け外しをしたり、どうしても無理そうなら拒否したりと、得られるお金とリスクを天秤にかけ続けていきましょう。
ただし、オプションの割り振りや拒否には気力が必要なので、何度も拒否したり割り振りをむやみに変えると気力が枯渇してしまいます。そうなるとどんな依頼でも受けざるを得なくなるため、相応のリスクを背負うことになるでしょう。場合によってはある程度のリスクを受け入れる覚悟をしつつ、どこまでのリスクを受け入れ、どこまでの利益を確保していくかの判断が重要となってきます。
例えば上記の例なら、パーティに対してダンジョンが難しく、結果平均保証額が高い割に前払い金が少ないため、あまり進んで契約したくはありません。一見拒否したいところですが、オプションで装備レンタルを付ければパーティー強化により平均補償額を抑えられ、かつ前払い金も高くなるので契約する価値が出てくるかもしれません。気力に余裕があればその手段もあり得ます。
このように、気力と保険内容とを常に見極めながら判断を連続でこなしていくゲームとなっています。
こうして保険内容を見て連続で契約を成功させていくと、ストーリーが進行していきます。保険の後ろ盾を得て活発となった冒険者活動の一端を、合間のパートで短めのシナリオとして楽しんでいきましょう。また、契約の冒険内容を眺めることでも冒険者活動の広がりを感じることができるかもしれません。
連続して契約を成立させるためにはある程度不利な条件を飲む必要があるため、リスクをケアしきれるように資金に余裕がある時に挑戦してみてください。
シンプルで分かりやすく、それでいてサクサクと進むUIも相まって、ゲーム進行は非常にスムーズな作品となっています。
保険を上手く与えてリスク管理をして、大きく損をしないように自転車操業を続けていきましょう。
感想
保険というシステムが綺麗にゲームシステムに落とされていて、遊んでいて感動を覚えていました。経営シミュレーションっぽくまとめられるものなんですね。保険会社も経営しているのだから、当然と言えば当然なんですが。
加えて、保険というシステムが持つ、確率的に安全であるときに前もって支出を共用してリスクを上手く分散するという、発明的な設計が伝わってくるシナリオでもありました。リスクをとれるようになると活動的になって、全体的にはある意味リスクが低下しているので上手い設計ですね。
ゲームとしての操作性も良好で、サクサク保険をかけながら進められます。カーソルで説明が出る仕組みもあるので、初期のルールが分からない内も遊んでいれば大体理解できていくのも良いです。最初はチェックをポチポチ切り替えて気力を一気に落とすみたいなこともしていたのですが、説明が出るおかげで早めに原因を理解できました。
演出も最低限度で、文字と数字を相手にどんどん進めていけるテンポの良さも良いですが、個人的には遊んでいるうちにこの辺の文字情報にも一定の感情が発生するのが好きでした。
その貧弱な装備で火山に行くのはやめなさいとか、子供が一人で危ない森に入らないでくれとか、素晴らしい装備でずいぶん危険な賭けに出ますねとか、そのメンバーでこのダンジョン行くの保険要らないんじゃないですかとか、慣れてくると情報から色々考えることが増えます。
一方で、シナリオとしてのネームドはリヴと勇者くらいですが、リヴは無理な提案を蹴ったのもあって固有イベント見そびれました。
それ故に追加イベントは知らないのですが、勇者のパートを見る限りでも、最低限シナリオや世界観のフレーバーは担保しつつ、あくまでゲームを阻害しない程度に調整された良い塩梅のイベントとなっていると思います。
フレーバーはないと寂しく、ありすぎるとゲームのメイン体験を阻害するので配分が難しそうですが、ちょうどよく世界観に浸れる良いデザインだったように思います。
ゲームシステムの話をすると、実際に結果が分かって補償が確定するのが数ターン後なのはドキドキして良かったです。判断が即時に下されないので、資金をだぶつかせつつちょっと自転車操業っぽいことをやっている気持ちになれます。
その反面、大量のお金が消費されたであろう演出が来た時に、どの判断でミスったのかは分かりにくいなと感じました。所詮ある程度は運ではありますが、どこのリスク管理を失敗したかが良く分からないので、反省のしようは無い印象です。そもそも、いっぱいお金をもらってそこそこ払ったなら、トータルプラスと見る向きもあります。
とはいえ、現在冒険中の冒険者がどこかに出ればいいのかと言えば、UIを入れるスペースもなければ基本余計な情報でもありますし、このテンポ感を損なうくらいなら現状のほうが良いのかなとも思っています。
ゲーム全体の話をすると、ハードモードじゃない限りは、よほど変なことをするか悪運を引かない限り何とかなりそうなバランスです。装備や護衛を押し付けつつ、平均的に得になるように組んでいけば、よっぽどのことがない限り資金に余裕は出ます。
筆者は割と拒否してえり好みするスタイルで、契約290に対して拒否90くらいのバランスになっていました。最後の評価でも慎重に分類されていたので、想定ではもう少し冒険してもクリアできそうです。
この最後の評価システムも良くて、自分のプレイが客観的にどういう特徴を持ったものだったのかを知ることができます。
別の視点というのは得難いもので、少なくとも一人でプレイしているうちには与えられにくいものでもあります。これがゲーム側から提供されることで、自分では気づけていない傾向を知ることができて楽しいです。
前述した慎重さについても、筆者はそこまで気を付けていたわけではなく、ある程度心の赴くままに進めていたら自然とそうなっていました。ある意味、性格診断に近いのかもしれません。
20. ECO2クエスト

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| アクションRPG | 僕はネット民 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 4時間 | 1.4 | クリア |
良かった点
- 無双系のような敵を倒しまくる楽しさがあります
- 図鑑要素のおかげで収集するモチベーションがあります
気になった点
- 誤字脱字が目立つ印象があります
- 村から戻るボタンがキャンセルのボタンに割り当てられているため、店などでキャンセルを使うと暴発することがありました
- 汎的なボタンである必要は無さそうなので、専用のボタンが割り当てられていると有難いです
レビュー
たくさんの敵をなぎ倒せ
ECO2クエストは、ダンジョンのあまねく場所に湧いた大量の敵を倒していくことで進行するアクションRPGです。
ステージ内を上手く立ち回り、多数の敵を各個撃破していくことになります。
操作方法はシンプルなものとなっており、移動はキーボード、攻撃はキーボードかマウスで行います。多くの敵を上手くさばくには、キーボードとマウスを併用するのがお勧めです。
そこそこ広いステージの中を縦横無尽に動き回り、多くの敵をサクサクと倒していくことで無双的な楽しみを感じられるでしょう。
その一方で、エリア後半に出現するボスや終盤の敵は癖がある相手も多く、ただひたすらに動き回って攻撃すれば良いというものでもありません。
大量に出現する敵、あるいはそういった強敵に立ち向かうには、ステータスの強さが重要となってきます。
そのためにはまず、ステージに点在する敵を倒すことで得られるアイテムから、装備を合成していきましょう。装備はステータスを強化し、属性などの特殊な要素も同時に付加してくれる優れものです。上手く選んで装備して挑めば、攻略の助けになるでしょう。
加えて、合成素材を集めるために繰り返し戦うことはレベルアップにもつながり、こちらでもステータスは上がっていきます。攻略に失敗する時は、とにかくダンジョンに挑むのが得策です。
さらに、そうして倒した敵や得られた装備などは図鑑に残ります。これをコレクションしていくのもまた一興でしょう。条件を満たし、各地で水場を見つけることができれば釣りもできます。
合成やコレクションのために、色んなところに向かうのも楽しみの一つです。
ダンジョンに挑み、素材から装備を合成したりレベルアップしたりと自身を強化し、より難しいダンジョンに挑むことでサイクルが回るゲーム性となっています。
そうしてステージを攻略するごとに進行する、ECOにまつわる物語を読み進めていきましょう。
感想
敵の数がとにかく多いアクションです。ひたすら敵をなぎ倒し続ける楽しさがありました。無双系のアクションが近いような気がします。
感覚的にはVampire Survivorsに近いんですが、このゲームでは攻撃やアイテムにはマウスなどを使っています。攻撃にデメリットが原則無いので攻撃し得で、それならと押しっ放しになりやすいので若干指を痛めるかもしれません。適度に休憩を挟もう。
敵の量が多いため一体一体に対する駆け引きの要素は少なめですが、厄介な状態異常を持つ敵を先に倒すとか、ボスに関してはちょっと引いてヒットアンドアウェイを試すという小回りは利きます。
とはいえレベルを上げれば被弾も下がる上に確定攻撃数も減るので、なんだかんだごり押しも効きました。ボスの攻撃の判定が厚いなら、避けるのを諦めて回復薬を飲みながら戦うという戦術も取れます。回復薬の価格があまりにも低いので、割と効率の良い戦術となっている印象です。
また、戦闘全体のバランスは、ステータスがかなりの領域を占めているのかなと感じました。
レベルや装備によるステータス強化がかなり支配的で、立ち回りはあくまでサブくらいの印象です。とりあえず殴り続けていると負けるくらいの相手だったら、レベルなり装備を見直したほうが良いような感じ。
とはいえ、ちゃんと進めていればレベル上げ作業必須みたいな苦行にはなりません。ちょくちょく歯応えのあるボスがいるくらいの塩梅でした。
個人的には図鑑要素が好きで、空いていると埋めたくなってきます。素材を集めつつ合成でアイテムを作っていくのは結構楽しく、強敵に負けたら強力な武器を揃えて行こうというモチベーションにもなります。
合成システム自体は、素材を全く持っていないのか足りていないのかが一見して分かりにくいので、現存数があると便利だろうなと感じながらやっていました。頭の中で計算していたので、日をまたぐと忘れそうですね。もっと欲を言えば、店で買えるなら合成屋で買ったことにして合成したい気持ちもあります。面倒くさがりなので。
なお、ドロップ自体は渋いので、ちゃんと合成を完遂しようとすると結構時間がかかります。筆者はある程度集めつつ、さすがに周回する時間が長そうなものは後回しにして強化に全力を費やしていました。それでも結構集まるので楽しい。
とりわけ最終ウェーブしか出ない敵からの回収は、中々骨が折れました。
コンプ要素と言えば忘れてはいけない釣りも、無心でやってしまう味があります。水を探していくという探検めいた楽しみもあって良かったです。個人的にはあんまり優秀な餌がいらない気がしていて、下位と上位の中間をとれるだけなイメージがありました、優秀な餌限定の魚もいたんでしょうか。
システム面で言うと微妙に引っかかるところはあり、画面上の違和感で言えば村のカメラが一番大きかったです。端の辺りで進行方向前方にマージンを取ろうとして失敗しているような、なんとなくそんな動きをしている気がします。
後は、村でもキャンセルが戻るに割り当てられているので、店をキャンセルして戻ると村から出ることになります。一応はX->Zの順序で押せば暴発しにくくはなりますが、余計な一手間がかかるなあという感じです。マップへ戻る機能自体はかなり便利なので、割り当てがもう少し特殊なキーでも良かった気がしています。
シナリオについてはゆるゆるながら独特な世界観が表現されていて、色々と奇想天外な展開が巻き起こっていくものです。オリジナルのキャラクターが大量にいるのも相まって、奇妙な世界観が表現されていました。
誤字脱字はちょくちょくあるんですが、何となく緩い感じで進む物語なのもあって、意外と気にせずに読むこともできます。雰囲気が得。
しかし結局、この地図はどういうアイテムだったんでしょうか。問題を起こしているモンスターを特定する機能、なかなか謎だったので伏線か何かかと思っていたら何事もなく終わったので謎のままでした。
21. 九色カーズレボリューション

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| RPG | プルゲーム |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 4時間 | 1.04 | ノーマルクリア |
良かった点
- ガチャの演出が凝っています
気になった点
- 道が狭い中でランダム移動するキャラクターが多く、移動の妨げになっていました
- 半歩移動で完全ブロックされるのが特に厳しいです
- ダッシュとスキップが同じキーに割り当てられているため、ダッシュしながら会話するとスキップが誤爆します
- 会話のスキップ開始はトリガー判定のほうが良いかもしれません
レビュー
強キャラ引くまでガチャ回し
九色カーズレボリューションは、ガチャで味方を引き当てるRPGです。
そうして味方を集めて戦闘に挑み、勝利を重ねることでクリアを目指していきます。
メインとなる戦闘のシステムは、やや複雑な属性相性を軸として構築されています。敵とこちらのメンバーの属性相性いかんによっては苦戦を強いられることもあるでしょう。
しかし、ガチャを引き、相性的に有利なキャラあるいは強力なキャラを引き当てられたのであれば話は別です。前者なら相性で有利に進め、後者ならキャラパワーでごり押せます。
特に、ガチャで運良く強いキャラを引けたのであれば、そのキャラを中心に戦略を構成するのがお勧めです。
なお、相対することになる敵の大部分はガチャで引けるキャラクターでもあります。このため、終盤は手持ちの高レアリティが敵として登場し、難易度は上がっていきます。
そういった強敵に対応するためにも、ガチャを積極的に引いていきましょう。レアリティの高いキャラクターのステータスは極めて高く、強敵と渡り合うには欠かせません。運悪くダブったとしても、重ねてそのキャラを強くすることもできます。
勝てない相手が出てくるようであれば、リソースを集めてガチャを回すのが良い選択です。
そうして敵を倒し、ボスを攻略してストーリーを進めれば、陰謀論風味のバックボーンを持った物語が展開していきます。
ガチャを回して強いキャラを集め、物語を先へと進めていきましょう。
感想
ガチャの演出がやたら凝っている作品です。それ以外の演出も色々と凝っている部分があるんですが、ガチャのそれが持つソシャゲ系を彷彿とさせる演出力は見目も含めて一番楽しかったです。
種族ムービーも含めて、好きなところに好きなだけこだわったという意味ではかなり尖った作品だなと感じていました。
戦闘システムは属性相性による戦略性のあるバトルという名目ですが、その実としてはレアリティで殴るカードゲームです。そこもソシャゲっぽい。低いレアリティのカードは序盤くらいしか使わず、最終的には最低でも神は欲しいくらいの温度感になってきます。
一応属性相性はありますが、それより格の高いカードのスペックを使い倒したほうが強い印象です。ソシャゲ踏襲のエミュレート力が高い。
与太ですが、どうせソシャゲに寄せるなら敵に応じて特攻のカードとかいたらバリエーションが出たかもしれません。
戦闘バランスについては序盤はやや難しくてサラヲがそこそこ鬼門で、それ以降はさほど難しくなくラスボスだけめっぽう強い、くらいの印象です。
サラヲはガチャのカード運が悪いと突破は困難ではありますが、運である程度戦えるところもあります。特にこのゲームは回復ですら必中でないので、運が悪いとそれだけで負けることもありました。試行回数を重ねるのも大事。
ラスボスについては毒をいかに通すかと、会心でワンキルもあるのである程度のお祈りがいるようなバランスに思えました。毒が強いゲームだ。
シナリオは諸々突っ込みどころのあるキャラクターがいろいろ出てきてくるタイプです。キャラ造形が偏見のそれで固められているようなイメージで、何となくネットミームっぽいものも多く練り込まれているような気がしました。
個人的には主人公が他責思考強めであったのが、いまいち感情移入しにくいポイントでした。資本主義がどうのと言っている相手に対してトラウマを打ち倒すという目的で倒し、その舌の根も乾かないうちに働け無職と言っているあたりの一貫性の無さも辛い。口調もころころ変わるので、多重人格持ちを中盤くらいまで疑っていたところがあります。
ただ、トラウマというか心の敵と戦った後に晴れ渡る演出はその前の鬱屈した演出も相まって爽快で良く、その爽やかさでもって次のステージに進んでいけるのは好きでした。すっきり気持ち良くステージを終われるというのは大事ですね。
後は、ダッシュとスキップが同じキーに割り当てられていて、ダッシュしながら会話するとスキップが暴発するところや、2マスの道にランダム移動するキャラが半歩移動で配置されてブロックされるところなど、細かいところで引っかかりを覚えていたのも個人的には若干辛いポイントでした。
イベントとその先の戦闘がメインのゲームなので、それとあんまり関係ない所でちょっとずつ体験が阻害されているような印象です。
22. SIBLINGS
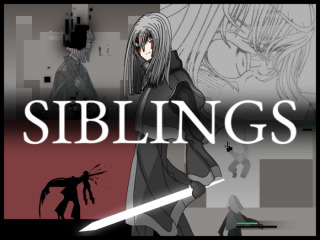
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 剣戟アクション | 九乃頭虫(ここのずむし) |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 1時間30分 | 1.0.4 | クリア |
良かった点
- アクションの差し合いだけを抽出したような楽しさがあります
- 殊に弾きのSEが良く、上手く防げると気持ちよくなれます
- 演出が美しい上にテンポが良いため、戦闘のテンポの良さを少しも欠いていません
- スピーディーで息詰まる戦闘が楽しめます
- 特にボス戦では専用の攻撃シーンも含めて、極めて高い完成度の演出を享受できました
気になった点
- 3面ボスより2面ボスのほうが強い印象を受けました
- 個人の慣れの問題かもしれません
レビュー
スピーディーに差し合え
SIBLINGSは、アクションにおける差し合いの美味しい部分が詰まった剣戟アクションです。
相手の攻撃を見切り、パリィを重ねていくことでクリアへの活路が見い出せるゲームとなっています。
基本的なゲーム性は強くアクションに寄っていますが、戦闘システムの内実はあくまでコマンドバトルです。
こちらが「斬撃」か「整える」のいずれかのコマンドを選んで実行した後、相手の攻撃ターンが始まるターン制のアクションが楽しめるようになっています。
ターン制であるが故に、相手の一連の攻撃を受ける前に一息ついて心の準備ができるでしょう。
| ターン制コマンドバトルの形式 |
|---|
こちらのアクションが完了した後に相手のターンで行われる攻撃は、いくつかの固有モーションの中で特定のタイミングにダメージを与えてくるというものです。
ここでプレイヤーが取れる行動は、防御、回避、そして防御の特殊例としての弾きがあります。
防御は、特定のキーを押し続けている間に常時成立しています。基本的な攻撃を全て防ぐことが可能ですが、攻撃を受けるたび戦意に傷が付いていきます。
戦意ゲージが溜まり切ると大きく隙を晒すことになるため、全てを防御で済ます訳にもいきません。相手へ攻撃する斬撃の代わりに整えることを選択して戦意をある程度回復するという手もありますが、それを続けるのではジリ貧です。
これを避けるため、相手の攻撃の瞬間に防御ボタンを押すことで、弾きと呼ばれる行動ができます。タイミングはそこそこシビアですが、成功すれば相手の戦意を削り、こちらの戦意が回復する恩恵を得られます。
ただし、弾きは少しでも遅れるようならダメージが直撃するハイリスクハイリターンの選択です。狙いどころはプレイヤー自身の腕と相談して決めましょう。
また、強敵の繰り出す一部の攻撃については防御も回復もできないことがあります。この時は左右キーによる回避、上下キーによる前進と後退で対処することになります。
どの方向に避けるべきかは相手の攻撃によるため、相手のモーションを見極めて適切な方向へ回避していきましょう。
これらの行動を適切に選択し、各フロアに存在する敵やボスを攻略するには、それぞれが備える独自のモーションと攻撃タイミング、攻撃方法を知悉することがカギとなります。
防御だけではジリ貧になりますし、回避できる行動を見極めることができなければ確定でダメージを負ってしまいます。
モーションとタイミングを学び、弾きを増やして戦意の喪失を防ぎ、回避を反射で出せるようになることで勝利がぐっと近づきます。どうしても苦手な行動は防御でしのぐ、というのもまた良い選択でしょう。
戦闘のテンポは非常に良く、一戦が適度な長さで片付くためリトライ性は担保されています。たとい敗北したとしても何度でも挑み、戦い方を学んでいきましょう。
加えて、スタイリッシュで美しい演出もまたこのゲームの見どころの一つとなっています。
攻撃モーションの作りは素晴らしく、タイミングを取りやすいダイナミックさと戦闘が素早く進んでいくスピーディーさを兼ね備えたものとなっています。攻撃を弾くと鳴る小気味良いSEもあって、爽快感をもって戦えることでしょう。
さらに圧巻となるのは、ボス系統の固有行動を食らうことで発生する演出です。この演出は一見の価値があり、このためだけにあえて受けてみるのも一興かもしれません。
戦闘のテンポの良さを一切損なうことなく、カットインの妙で高速に演出される様は芸術的とすら言えます。
とにかく、アクションにおける気持ち良い部分だけが抽出されたようなゲームとなっています。テンポ良く戦闘に挑んでは行動を観察し、そうして相手のモーションを完全に見切って弾き続けられた時の爽快感は格別のものです。
強敵に何度でも挑み、見事打破していきましょう。
感想
世の中にはいろんなゲームがありますが、ノンストップで楽しい所だけ入ってるゲームは中々に稀です。このゲームはその稀なゲームの一つであり、雑魚戦一つとっても楽しみ続けられる作品です。気付いたら1時間30分経っていてクリアしていました。キングクリムゾンだ。
特筆すべき点が多いんですが、とりあえずテンポの話をします。
戦闘がメインとなりますが、とにかくあらゆるところのテンポが物凄く良いゲームです。戦闘という繋がりで見ても、負けるにしてもすぐ負けるし、勝つならかなり短く勝てます。
ただでさえスピーディーで息詰まる戦闘ゆえに時間を短く感じるのに、加えてちゃんと敵の耐久もそこそこ低めに設定されてそうな気配を感じます。
ここに加えてコマンドが極限まで単純化されていることで、コマンドバトルだということを忘れるレベルでアクションの感覚で戦えます。慣れてしまえば整える必要はほぼないので、本当にアクションゲームっぽくなってきます。
この手のゲームならスキルとか回復が入っていても不思議はありませんが、そこが削ぎ落とされているがために思考がシンプルに研ぎ澄まされていきます。下手にそういったコマンドが入ると、それを使うかどうかの判断に思考が取られますからね。このあたりの選択性の無さはわざとやっていそうな感じがします。
さらに、そのテンポを一切欠くことなく、最大限に強い演出を魅せてくれます。カットの切り方が完璧に近く、ゲームに合ったスピード感で素晴らしい演出を叩き込んでくるのには感動を覚えるレベルです。
ボス戦におけるつかみ攻撃に関しては、モーションとアニメーションが格好良すぎるので、何ならわざと食らいにいきたくなるまであります。そうでなくても初見はとりあえず食らっておきたい。
その上で、3面ボスでひょろい方を倒そうとするとでかい方が庇う演出を見せるなど、細かい配慮も完備しています。隙が無いですね。
そして何よりも、戦闘における差し合いの感覚が極めて洗練されたデザインで用意されているというのが素晴らしいポイントです。
殊にボス戦は圧巻で、ずっと緊迫感のある戦いを楽しむことができます。
一度戦いを通してしまえば、そのモーションから行動を一意に定められるようになってくるので、そのパターンを体に覚えさせて弾き続けましょう。そも、SEから敵のモーションまで納得感の塊なので大体は初見で弾けますし、 そうならなくても被弾に納得できます。
後半ボスになってくるとさすがに初見で防げるかは50:50という感じですが、慣れれば完封はできるはずです。
筆者は2面ボスにまあまあ苦戦し、ラスボスにそこそこ苦戦したのちクリアとなっています。
ドラゴンについては、最初はその突破ですらひーこらやっていたにもかかわらず、クリア直前は一発でも被弾したらミスったなというレベルにまで至りました。慣れの力は凄い。
アイはクリア時点でもなお結構難しく感じていて、どこまでいっても択一をミスることはありましたが、何度もやることで択一の成功率を上げられ、それ以外の攻撃でミスりにくくなったので薄氷の勝利をつかめました。「卓越とは技ではない。単なる慣れだ。繰り返し行うことで体得する。」というやつです。
また、筆者の戦闘スタイルほぼ弾きで戦うものでしたが、弾きが難しい技には守り続けるという戦略も有効という裾野もあります。回避を合わせるという択もありますし、場合によってはそっちの方が強いこともありました。
筆者は払い行動をガードで割と誤魔化しつつ、覚えられたら適宜回避を混ぜる方針で進めていました。
この弾き主体の戦闘は本当に楽しく、弾きのSEが良いこともあって非常に気持ち良く戦えます。
前述の通り敵のモーションについても無駄がなく、素早い中で無理筋にならない絶妙なラインを攻めているのでテンポよく攻守交替して進められるのが良いところです。
敵のあらゆる攻撃を完全に弾き切って仕留められるようになると、得も言われぬ快感がありました。
また、色々なものをそぎ落として極力シンプルに作られたゲームではありますが、さりとて世界観まで置き去りにはしていません。プレイヤーが必ず見るところでは多く語りはしませんが、好きな人は触れられるようにしっかりと導線だけは用意されています。そして筆者は文字が好きなので全部読んでいます。
コンフィグですら世界観になじませようというコンテキストの妙は強く、ここまで徹底することで描ける世界観というのがありました。
とにかく、差し合い好きなら間違いなくやったほうが良い作品でした。そういうのが好きな方が丁寧に作ってるような印象を持ちます。
アクションゲームの差し合いのトロの部分だけ楽しめるゲームですよ。
23. Alkersas

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| RPG | 逃げ足 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 2時間 | 1.07 | ED2 |
良かった点
- 攻撃優位で設計された良い戦闘バランスでした
- ネームドを倒した痕から情報を能動的に拾えるシステムが面白かったです
- ボス解説部屋のおかげで初見でも戦略を練ることができます
- 対象ボスの解説の前にワープしてくれる細やかさもあります
気になった点
- 最初の名前入力のフォントが小さいように思いました
- ボス解説部屋自体はありがたいのですが、盛大なネタバレともなっています
- エリアごとに区切られた解説部屋があるとネタバレにならないかもしれません
レビュー
短く良質なRPGを
Alkersasは、短い中でバランスの取れた戦闘が楽しめるRPGです。
シンボルエンカウントの雑魚敵がはびこるフロアを進み、ボスを攻略していくことになります。
全体を通して戦闘メインで進行するゲームとなっている中、戦闘におけるバランスは攻撃優位なものとなっており、サクサクと進めていくことができます。こちらの火力が高いため雑魚をスピーディーに処理できる反面、逆に手痛い反撃を受けることもあります。気を抜かずに戦いましょう。
ただし、戦闘に敗北してしまったとしてもゲームオーバーにはなりません。代わりに、即座に拠点へと返されます。この拠点では、敗北前に得られたリソースでアイテムを手に入れたり、永久強化を行ったり、従者と呼ばれるメンバーの編成も行うことができます。
敗北した場合は十分に準備してから、再度フロアに挑んでいきましょう。
そうして十分強化して歩を進めた先で出会うことになる、各フロアの最後で待ち構えるボスは強敵です。その攻略には入念な準備と、多彩な装備を上手く組み合わせることが肝要となってきます。
ある条件を満たせばボスの情報を事前に見ることもできるため、その情報を活かして、敵のギミックを上手く攻略できる装備を考えるのも良策です。攻撃優位なレベルデザインを利用し、あるいは徹底的に弱点を突いてギミックごと叩き壊すという戦略も取れるかもしれません。
敵のギミックを上手く攻略して、ボスやネームドの敵を倒すことにより、その痕からシナリオの一片を得ることもできます。この回収は任意となっており、クリアには影響がないので戦闘を重視するなら無視しても構いません。
しかし、物語を補完して理解しようとするのであれば、余すことなくチェックするのをお勧めしたいです。シナリオの裏にある世界観を堪能できること請け合いです。
たとえフロアに挑んで敗北しても、拠点で強化しつつ引き継いで進むことができるため、何度も挑戦すればいつかはクリアできます。
戦略を立てて最小回数の挑戦で倒すも良し、万全の状態を整えて力で押し切るも良し、好きなスタイルで攻略していきましょう。
感想
個人的にテンポの良い戦闘が好きなので、大分攻撃偏重なレベルデザインが好きな作品です。武器を揃えて、耐性を整えて、それでも受けに回るのではなく攻めをどう組み立てるかを考えるべきデザインが良かったところになります。
全て整えてちゃんと戦うことができれば相手のギミック発動前に倒すことができる、といったレベルのかなり攻撃優位なデザインはやりすぎなきらいもあります。ただ、攻撃偏重とはいえ状態異常はそれなりに怖いので、どこまで攻めに徹するかを考えないと痛い目に遭うというあたりでバランスを取っている印象です。
装備の数がゲーム規模に対してそれなりに多彩なのも好みで、ボスに応じて色々つけ変えていく遊びができました。その多様さもあっていくつか機能していない武器もありそうですが、純粋に武器を集めていくのもそれなりに楽しいので個人的には好きです。
ボスと戦う前の装備の吟味もまた、戦闘と同じくらいの醍醐味がありますからね。
また、ボスと戦う前にボスの説明が見られる解説部屋は非常に便利で、戦う前から戦略を練ることができます。解放要素なので縛ることもできるのが良いですね。ちょうど戦おうとしていたボスの説明の前にワープしてくれる細かい仕様も嬉しいところです。
一方で、本棚の存在自体が大きくネタバレになってしまっているのは若干気にはなっていました。知る気が無くても規模感で大分わかってしまう懸念があります。ボスごと固有の部屋とか、最低限エリア単位で区切ってあれば丁寧な気もしますが、まあまあコスト高そうです。
なお、このシステム自体は武器を上手く組んで敵のギミックを攻略して戦うゲーム性とかなり相性が良かったなと感じている次第です。
そして、ボスもそうですが、ゲーム全体の戦闘バランスも良い作品です。
雑魚がちょうどいい塩梅で、さっさと倒せるけどそれなりに強い時もある、くらいなのでテンポ良くそこそこの緊張感が味わえます。場合によっては周回が必要なデザインをしているので、このあたりのサクサクと進む感覚はゲーム性に合っているなあという印象でした。
シナリオの面では少ない情報で語るタイプで、より深く物語を理解するために能動的に散らばったピースを集めていける構造が好みです。ネームドボスを倒した痕から物語が得られるので、大ボス以外を倒す動機にもなり得ます。
痕の主張がかなり弱いのもあって、最初の方の中ボスは見逃していたんですが、これくらいの主張の弱さの方が強制感がなく自らの意思で物語を補完させている感覚を得られるので良いのかなとも感じています。分かってしまえば回収の旅に出られますしね。
なお、プレイを通してみれば戦闘面でもシナリオ面でも完成度を高めてあるRPGだなという感想に落ち着くんですが、その一方でタイトルがウルファールのサンプルゲームのままだったり、Dataが圧縮されていなかったり、名前入力の文字がやたら小さかったり、序盤に得られる情報が割と警戒心を上げるものだったのがもったいない印象がありました。
24. ウディダッシュ

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ランゲーム | いだてんバイク |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 15分 | 1.1 | クリア |
良かった点
- キャラクターが愉快でした
気になった点
- リザルトなどの画面について、おそらく上下左右キーを受け付けて遷移するのですが、それを示すものがありませんでした
- 決定キーなどの任意入力を受け付けるか、何らかの送りを示すアイコン等があるとわかりやすいかもしれません
- ステージごとの変化が少なく、加えて一ステージのボリュームがやや長い印象を受けました
レビュー
走れ!!
ウディダッシュは、迫りくる障害を左右に避けてゴールを目指すランゲームです。
挑戦するステージは5つのレーンから成り、それぞれのレーンから向かってくる敵を上手く避けて進んでいくことになります。上手く避けられず障害物に衝突すると大幅に時間をロスするため、適宜レーン間を移動することで回避していく必要があります。
ただし、レール間の移動という行為自体もまたやや時間のロスとなるため、頻繁に移動するのは効率が悪くなります。必要なタイミングを見極めて適切に避けていく、チキンレースの様相を呈してくるでしょう。
そうして上手く走りきり、ゴールまで到達すればステージはクリアとなります。
全5ステージを走り切ることで、物語はエンディングを迎えます。最後まで走り切ってみましょう。
感想
いわゆるひとつのランゲームというタイプに近く、レーンを切り替えつつ障害物を避けていくゲームです。
ランゲームとの違いはコインなどの報酬がなく、明確にゴールが存在するところです。なので、レーンを移る理由は障害物を避けるほかになく、回避のゲーム性になっています。チョコボと魔法の絵本のミニゲームに近いゲームがあった記憶もありますが定かではありません。
基本的に避けに徹することになり、道中に報酬なども特にないので、多くの面で我慢するゲームとなっています。障害物というストレス要素をひたすら避けていくことになるので、性質的にはイライラ棒っぽいゲーム性とも言えるかもしれません。
ゴールまで報酬と呼びうるものがなく、そこそこ長いのもあって、ミニゲームと言ってもモチベーションが続きにくいのは若干気になっています。上手く避けられたらスピードアップくらいの気持ち良さが欲しいなと感じていました。スピードアップしたら難易度上がりそうですが。
また、ランゲームとして見てもレーン変更の度に速度が落ちるので爽快感にやや欠ける印象があります。殊に後半の怒涛のレーン変更もあって、牛歩の進行感覚は拭えませんでした。たまにレーン全部が敵で埋まって轢かれることもあるので、割と運要素も強く感じます。
そういう意味でも、あまり深く考えずに、さっと遊べるミニゲームとして楽しむのが良いのかなと思っています。
なお、個人的には何やら愉快なキャラクターが織りなすシナリオは好きで、ゲームの牽引力となっていました。テンションで舗装して突き進んでいくタイプの運び方で、このミニゲーム然とした印象を受ける物語となっています。
しかし、何度轢かれても立ち上がり歩みを止めないのは、紛うことなきヒーローですね。
25. コトノリ
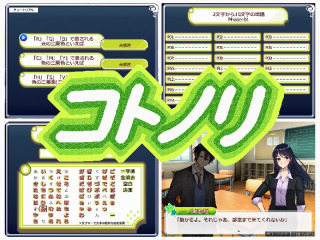
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| クイズ/語彙力パズル | はるしし |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 45分 | 1.03 | クリア/59 |
良かった点
- 文字を制限することで多答系クイズの面白さを一答で表現していました
- 文字をやりくりするパズル的な楽しさもあります
- チャレンジで語彙力パズルにも挑戦できます
気になった点
- 決定にすぐ飛べる機能が欲しくなりました
- 文字の表示方法は多く使う機能ではないので、そちらを別途のオプションにしてサブキーで決定に遷移が好みです
- 問題全体の解答確定もサブキーなので整合性は取れていそうです
- 文字の表示方法は多く使う機能ではないので、そちらを別途のオプションにしてサブキーで決定に遷移が好みです
レビュー
クイズのパズル、語彙力のパズル
コトノリは、同じ文字を使うことができないという条件下で複数の多答クイズを完答する、パズル的なクイズゲームです。
それぞれの問いで答えるべき回答は一つですが、各々の回答バリエーションについてある程度精通していれば、文字を都合しやすくなっています。
ゲームシステムを簡便に説明するために、架空の問題を例に挙げてみます。
「トライアスロンの種目の一つといえば」、という問題と、「名前に動物の入る都道府県といえば」、という問題があったとします。
この時、前者でマラソンを答えとして使うと、「ま」の文字が消費されるため、後者は鳥取しか使えなくなります。そして、これら以外の問題で「と」が使われるような場合では破綻が起きるため、その時は水泳などの別解を答えとして用意しなくてはなりません。
文字の重複が無いように回答をコントロールし、全ての問いに対して適切に答えるためには、それぞれの問題の多答の一つ一つに対する知識と、それを上手く組み立てる力が求められます。
詰まった時は、正答数が少ない問題や、思い出せる答えが少ない問題をベースに組み立てるのが得策です。頭を使って解きましょう。
また、シナリオ付きのこのクイズ形式のモードに加え、文字を重複することなく単語を列挙し続けるチャレンジモードも搭載されています。こちらでは、語彙力という別の能力が求められることになります。
先のことを考えて使わないであろう文字を消費しつつ、上手く言葉を挙げていきましょう。こちらはこちらで、別のパズルが楽しめます。
文字をパズルのように組み合わせる、二種の遊びが盛り込まれたゲームです。
前者は多答クイズの面白さが上手く落とし込まれたパズルであり、後者は語彙力の限界に挑めるパズルです。制限時間などは無いので、ゆっくり考えたり思い出したりして文字のパズルを完成させていきましょう。
感想
各要素を一つだけ答える形式のクイズゲームなんですが、言葉の制約がつくことで変則的に多答のスキルも要求されていて楽しいゲームです。クイズとしての問題数はやや少なめではあるんですが、一問一問の完成度が高く、それぞれでコンセプトが変わってくるのも良かったです。
クイズとして見ると、それぞれの答えに対するカバー範囲がかなりケアされている印象で、とりあえず仮入れしていた答えが後続の答えを全滅させてしまうことが多々あります。安易に思いつくところが潰されていますね。正答数の少ない問題からトライしていくのが安定択だと思います。
このあたりの思考の流れは確かにある意味パズルでもありつつ、ちゃんと知識は要求されるクイズともなっていて良いです。
具体的に問題で良かった所を挙げるんですが、三大珍味でとりあえずキャビアを入れたら大陸が一気に消えたのは驚きました。おかげで、ほとんどの大陸に「あ」が含まれているという気付きを得ることができたというわけです。漫然と生きていると気付かないもんですね。
後は、デンマークを入れるとエレジーもプレリュードもレクイエムも塞がれていたのも良かったです。音の重なりについて、いろんな気付きがある。
また、宝石のルビーや干支の鼠など、とりあえず短いのを入れておけば何とかなるかなと浅慮したら、大体後ろでにっちもさっちもいかなくなるあたりの設計もまた綺麗でした。
このクオリティなら問題を作るのはさぞかし難しそうなので、それほど問題数が無いのはさもありなんという感じです。
なお、五大栄養素で脂質を入れたら弾かれたり、チャレンジで色々弾かれたりと、単語入力系故のカバーの難しさは出ているんですが、クイズ面では答えが限られるのもあって遭遇率は低かったです。チャレンジも結構いろんな語彙がある印象。
操作面では概ね使いやすいUIで思考の方に集中できるようになっていました。若干カーソルが滑る印象はあるものの、その分軽快に動作するので入力しやすい面もあって個人的には良かったです。
文字の表示方法変更がそれほど使用しない割にちゃんとしたキーに割り当てられているので、このあたり即解答決定に遷移するような使用率の高そうな機能に割り当てられていると個人的には好みでした。誤爆はしそうですが、チャレンジでもないとペナルティは大きくはないはず。
最後にチャレンジの話をするんですが、端的に言って語彙力が試されます。次いでそれをパズル的に組み合わせる力が求められます。
筆者は最初に濁点系を消費しようかなとやっていたら、後半思ったより濁点が欲しい場面が出てきて難しい状況に陥りました。意外と濁点って使われるんですね。プランを立てればもう少し消費できそうな気配はあるんですが、ほぼ全文字使うような詰めはかなり難しそうです。
殊に、小文字のあいうえおの消費はほぼ無理なんじゃないかと思っていて、辛うじて「ふ」の利用で一つ削れて、あとはドイツ語あたりに「ぇ」を探すくらいしか思いつきませんでした。難しい。
| チャレンジリザルト |
|---|
質の良いクイズで頭を使い、チャレンジで語彙力を試すといったように、似たルールで違う遊びが楽しめました。
ノベルパートでもゆるい雰囲気の先輩後輩関係が垣間見られて、短編として楽しめる作品となっています。そして何よりも、本当にこのクイズを作るのは難しそうだなあというのが偽らざる感想です。
26. マインのパズルでバトル

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| マインスイーパー | denden |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 1時間 | 1.01 | ノーマルクリア |
良かった点
- 高速でマインスイーパーの思考を回してコンボをつなげていく楽しさがあります
- ストーリーが明るめで良いです
気になった点
- マインスイーパーに失敗しないと強化せずに強敵と長時間戦うことになりそうなバランスでした
- ボスを倒したら強制的に帰して、アイテム購入に移らせても良いのかなと感じました
- 一応、初回安全がないために、本当の強敵に対して運次第では退場することになります
レビュー
マインスイーパーを高速で解いてコンボをつなげよう
マインのパズルでバトルは、マインスイーパーをベースとした戦闘を繰り返して進行するゲームです。
マインスイーパーが得意であれば、有利に戦闘を進められるでしょう。
戦闘システムはいたってシンプルなものであり、マインスイーパーを解いてマスを開けるごとに入る攻撃のダメージで相手のHPを削り切れば勝利となります。一方で、地雷を踏み抜くことで発生する相手の攻撃を受け続け、こちらのHPが無くなるとゲームオーバーです。
マインスイーパーを正確に行うことができれば被弾は最小に抑えられますが、ご存じの通りマインスイーパーには運の二択があります。加えて初回の安全保障もないため、最初のマス選択は常に地雷の危険性があります。
すなわち、戦闘が長引けばいつかは敗北を喫することになってしまいます。
これを避け、戦闘を素早く終わらせるにはコンボシステムを上手く使っていく必要があります。一定時間以内にマスを連続して開けていくとコンボが成立し、攻撃のダメージが増えていくというものです。これを重ねて攻撃力を増加させることによって、素早く相手の体力を削り切れるようになるでしょう。
ただし、コンボをつなぐために高速で考えて操作を行っていると、その分ミスが誘発されやすいというリスクも抱えています。思考を高速で回しつつも、コンボに固執してかえってダメージを受けないよう慎重にマスを開けていきましょう。
また、戦闘を重ねていくとレベルが上がり、基礎ステータスが向上していきます。加えて、敗北したとしても得たコインをもとにアイテムを買って、HPの回復や武器の調達も可能となっています。
これらを活用してステータスを上げていくことができれば、戦闘はより有利になります。勝てない場合や時間がかかりすぎる場合は、ステータスを上げて再挑戦しましょう。
マインスイーパーという思考のゲームを、さながらアクションのように高速かつ反射的に解いていくことで、脳みそをフルに使い切っていくのが楽しい作品となっています。
素早く解くマインスイーパーに慣れて、どんどんコンボを繋げていきましょう。
感想
パズル的なマインスイーパーを好む身としては、コンボで上手く時間制限を付ければアクションゲームというか高速判断ゲームとしても運用できるのだなと感嘆していました。マインスイーパーテトリスに近いんですかね。
マインスイーパー自体のゲームとしての完成度はあるにせよ、それに対するプラスアルファでも楽しめるゲームでした。
個人的な攻略としては、コンボ重視で武器を選んでいくのが強いなと感じていました。雑魚狩りがスピーディーに終えられるのもありますし、ボスであってもスイープ手前くらいで屠れる火力が出ます。
とはいえ、あまりマインスイーパーが得意でなかったとしても、単発高火力の武器を使うという選択肢が取れるあたりのケアが親切で、ちゃんとマインスイーパーの思考を回せれば攻略自体は可能なラインに感じました。
一方で、マインスイーパーに下手に慣れていると被弾が最初の一回にほぼ限定されるがゆえに、明らかな格上相手であってもなかなか負けないなという印象はあります。
明らかに減りが遅い相手に当たった場合は、わざと負けてアイテム購入してから挑んだ方が効率が良いのですが、それが自然にできないループ構造となっています。雑魚が固いことを了解した上で、わざとリタイアして帰還するというのもサイクルとしては成立しているかもしれませんが、どうしてもネガティブな印象を受けます。
ボスを倒したら疲れたから帰る、みたいな構造があればスムーズな進行になった気もします。
コンボの話に戻すのですが、最初に盤面を見てプランを固め、その後アドリブで繋げていく楽しさがあります。思考を高速で回して頭を使い切る体験は楽しく、適度にミスを誘発する仕組みでもあって綺麗なデザインでした。
コンボに明確にリターンがある武器が存在するのも良くて、コンボをより決めていこうというモチベーションにもなっています。
なお、コンボ成立にあたっては、盤面確定時のマーク以外は基本的にあんまりしないのがお勧めです。マーク自体が攻撃に寄与しないので、手が空いたらやってもいいですが、原則不要な処置となっています。
スイープに関してもマークは必須ではないので、頭に留めておくだけにしておくのが楽でした。
このあたり、マークが攻撃に影響を与える設計にしてしまうと、マークにリスクを付ける必要も出てきてしまうので、これをカットしているのはバランスとしては良く感じています。
マーク失敗でダメージあたりが落としどころのように感じますが、マーク成功がマスを開けることに比べて連続で行いやすいのもあってコンボとの噛み合わせも難しく、いっそ取っ払う判断は素晴らしいなと思っています。ルールがシンプルになりますしね。
後はストーリーが明るめなのも良いところで、これくらいの短編なのもあってサクッと遊ぶのに向いている作品となっています。
あくまでもマインスイーパーで戦うのがメインでストーリーはフレーバーとなっているため、それに合った適度な緩さが好みでした。
27. 一人非零和有限確定無情報非ゲーム
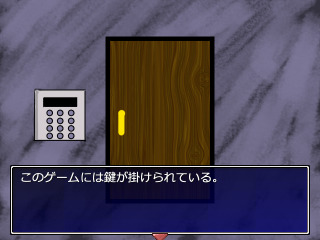
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| メタ謎解き | endo |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 15分 | 1.1 | クリア |
良かった点
- 良い問題が取り揃えられたゲームでした
気になった点
- 特にありません
レビュー
ネタバレしたくないのでここに書くことがあまりにも少ない
一人非零和有限確定無情報非ゲームは、メタ要素を含む謎解きゲームです。
あまり色々な情報を出すとゲーム性に深くかかわり、面白さを毀損させてしまうので多くは語れません。
ゲーム内の要素についても、またそれ以外についてもあらゆるものを使い切り、プレイヤーはいくつかの謎解きに挑戦することになります。
謎を解き明かすことができれば、物語と共にゲームは進行して、やがてエンディングへと辿り着くことができるでしょう。
とりあえず言及できるのはこの辺りまでなので、こういったゲームが好きな方はプレイしてみることをお勧めします。内容はコンパクトなものとなっているので、短い時間で遊べるでしょう。
感想
このゲームはどこに触れてもネタバレになってしまうので、あらかじめ以下の内容は全部ネタバレになることを示しておきます。
いわゆるメタゲームというか謎解きとして、問題数はさほど多くない中でメタらしいツボが押さえられていて楽しい作品です。体験として楽しいので、気になる方はダウンロードしてプレイしてみてください。プレイ時間も短めなのでさっとやれます。
個人的に好きなのは暗号化されていないことにすらちゃんと意味があったことで、ダウンロードしたタイミングで感じていた気持ちが綺麗に回収されました。伏線回収は楽しいですね。
また、この手のゲームが好きな方は同意していただけるかと思いますが、Base64エンコードについては見慣れているので見ただけでエンコードするべきことが分かりました。あの文字列を見た瞬間にエンコーダに入れたくなります。
個人的に一番苦戦したのはモールス信号で、やるべきことは分かったんですが参考サイトを間違えてしまい、存在しないモールス信号と戦っていました。ここだけ若干遠回りした形ですが、それでも全体で見ればそれほど時間はかからず、コンパクトにいろいろなメタを楽しめる良い体験を得られる短編だなという印象があります。
最後の最後、すべてのファイルが消えるかなとうっすら考えていたのですが、よく考えたらウディタでは出来なさそうな演出でした。
そしてそもそも、忘れないことが終わりへとつながる作品である以上、全てが遺されているのもまたゲームコンセプト的には正しそうにも感じます。
メタゲーム、後味が悪いか後ろ髪を引かれる結末に寄る印象がありますが、このゲームは後味良く終わります。短編ということもあるとは思いますが、清々しく終われて良い作品でした。
28. DayDreamDreamer

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| RPG | Rentalize |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 12時間 + 3時間 | 1.017 - 1.031 | トゥルーエンド |
良かった点
- 冒険していると感じられる雰囲気の良いJRPGでした
- フィールドは世界を感じるほどに広大で、探索できる要素も散りばめられています
- 後半になるにつれて歯応えのある戦闘が楽しめます
- 選曲が素晴らしかったです
気になった点
- 戦闘のUIについて、色々な要素があるために最初は取っ付きにくく感じました
- 特にリング式の選択UIについて、横の切り替わり時に見た目が変化しないのもあってやや使いにくかったですが、アップデートで改造が入りました
- 状態異常周りのアイコンについての説明が奥まったところにあります
- 強く戦略に直結するので、可能であれば戦闘中に説明が見られると嬉しかったです
レビュー
JRPGの原液
DayDreamDreamerは、RPG然としたRPGです。何よりもRPGというジャンルが似合うゲームとも言えるかもしれません。
広大なフィールドを思うがままに探索し、エンカウントする雑魚や立ちはだかるボスをサイドビューの戦略的な戦闘システムのもとで打倒していく王道的な設計となっています。
探索することになるフィールドは広がりを感じられるようなデザインとなっており、かつロケーションに合わせた変化がふんだんに盛り込まれているものとなっています。かてて加えて、この様々なロケーションのほぼ全ては地続きで存在しており、歩き回るだけで世界を巡っているという感覚を強く覚えることになるでしょう。
このロケーションの変化と確かな接続性が、RPG的な冒険をしているという空気感を印象的に演出しています。
加えて、そのフィールドはただ広いだけの殺風景なものではありません。各ランドマークにおいては、物語の進行はもちろんのこと、サブイベントなども充実しており、各地を巡る原動力がそこかしこに散りばめられたものとなっています。
探索しながら戦闘していくことになる広大なフィールドの疎性と、イベントのある各地点の密性の塩梅がちょうどよく、冒険する楽しさもシナリオ駆動で先に進む魅力も同時に感じられることでしょう。
そうして進行することになる本編シナリオ、あるいはイベントの中で避けては通れないのが強力なボスの数々です。
そのボス戦における戦略性を語る前に、このゲームはいささか特殊かつ戦略的な戦闘システムを抱えているため、まずはそちらを説明します。
| 戦闘画面 |
|---|
戦闘の基本システムはCTBに近く、左下の歯車にある待機時間とそれが示す順序でターンが回ってきます。この待機時間はスキルによって決まっており、強力なスキルほど次の行動が来るまでの待機時間が長くなりがちです。また、スキルによっては詠唱時間が別途あるため、発動までにラグがある場合もあります。
この行動順を上手く制御し、補助のタイミングや回復のタイミング、敵の攻撃の対策のタイミングなどを考慮して戦略を回していくのが重要となってきます。
また、各キャラクターは戦闘前にも戦闘中にもその立ち位置を変えることができます。立ち位置には主に二つの効果があり、その一つとして前衛か後衛かによって攻撃性能や防御性能が変化することが挙げられます。
前衛なら攻撃性能が上がって防御性能が下がり、後衛ならその逆です。このため、強い攻撃をする時だけ前に出る、相手の強力なスキルを受けるため全員下げるといった戦略もあり得ます。
加えて、必ずしもその影響を受けないキャラクターやスキルもあるため、それぞれのキャラクターの特性に合った位置に動くこともまた大事になってくるでしょう。
第二に、立ち位置は効果範囲に影響を及ぼします。多くの範囲攻撃は一定の大きさのサークルで表されるため、密集していると全てのキャラクターがダメージを受けてしまいます。一方で、分散していればダメージを受けるのはサークルに含まれる一部のキャラクターで済みます。
それと同様に、回復も範囲が決められているため、こちらは密集したほうが有利となるでしょう。
性能の上下や次に来る行動などを十分に勘案して、適切に移動を挟んで立ち位置を柔軟に変えていくのが攻略の上で重要な動きです。
この、行動順を管理し、移動により効果範囲をコントロールする戦略的な仕組みの上で、プレイヤーは戦い方を練ることになります。加えて、強敵として立ちふさがるボスに至っては、さらにもう一段ギミックが用意されていることも多いです。
ボスのギミックを攻略して勝利を掴み取るには、行動順や位置に応じた柔軟な選択と、活用するスキルが肝要になります。スキルは、各キャラクターの固有スキルに加え、事前に装備によって構成を変えられるものもあります。これらの組み合わせが、重要なウェイトを占めることになるでしょう。
使ってみたことのなかったスキルを採用するだけで、ボスに楽勝することもあり得ます。相手に対して有利を取れそうなスキルを考えて、戦略を嚙み合わせてボスを蹂躙しましょう。
そうして様々なボスを打倒していくことで、ゲームのシナリオは進行していきます。広大なフィールドを冒険し、仲間を増やし、ボスを撃破していくそのJRPG的な過程の先をぜひとも体験してみてください。
また、サブイベントも色々と存在するため、以前訪れた場所を再訪するのも一興です。何か新しい発見があるかもしれません。
ぜひとも世界中を巡って、色々な場所を訪れてみましょう。
広大な世界というフィールドを周り、装備を集めたり仲間を集めたりしつつ、強力なボスを戦略的な座組で打ち破っていく、その体験はまさにRPGそのものとも言えます。
JRPGに飢えている人にお勧めの作品です。
感想
一言で言うなら、まさにやりたかったJRPGです。こういうJRPGを遊びたいというJRPGの具現であり、RPGの原体験という琴線に触れる作品でした。
このゲームに対して筆者が非常に好意的であり、都度都度において感動しながらプレイしていたのはこういった個人的な事情もあるので、DayDreamDreamerなんでも褒める妖怪だと思ってご了承ください。やりたかったRPGをそのままお出しされたら楽しいのはそれはそうなので。
まずはフィールドのことに言及します。
かなり広大であり、何よりも地続きであることから冒険しているということを強く感じられるマップとなっています。
真の序盤はともかく、かなり最初の方から色々なところに行けます。関係ないダンジョンに乗り込むこともできますし、いきなり変なところに行くのも可能です。かなり高い自由度を備えています。
その一方で高い難易度のものは色付きで表現されるなどのケアもなされているので、実力から離れたところで深追いすることもありません。細かい配慮。
その高い自由度のもと、各地のロケーションは大きく様変わりし、雪国から腐敗した土地、遺跡から都市まで、見目という面でも大きく印象を変えてきます。
地続きでロケーションの変化を感じ取れるマップを歩き回っていくことで、より広い世界を巡っているという印象を強く覚えることになります。この体験は非常にRPGとして良く、常にわくわくした気持ちで世界を周りつくすことができました。
この地続きであるという体感はそのまま冒険しているという感覚に強く結びついていて、歩き回って実際に冒険しているんだという印象をダイレクトに感じ取ることができるようになっています。
ファストトラベルや鉄道という要素はあれど、各地点は確かにつながっていて、実際に歩いてそれをつないでいくことになるため、一切分断された印象を受けません。
そうした地続きで広いフィールドを有していながら、要所要所には探索する価値のあるものを配していたり、訪れた先にはシナリオ進行の他にもイベントを用意していたりと、小さな面でも大きなくくりでも程よく要素が散りばめらています。
この塩梅が非常に良く、広大なフィールドを歩き回っているという意識を失わない程度にはまばらで、何もないなとは感じない程度に密であり、ワンパターンだなと思わない程度に緩急がついています。
そうした探索要素の幅が広いのも良く、新しいダンジョンが顔をのぞかせたり、強力なアイテムがあったり、変なイベントが起きたり、仲間が増えたり、ファストトラベルの解放まであったりと、より取り見取りです。
様々な主要要素をクリアした後ですら、ウルカノを仲間にしていなかったり、もう一人の管理人がいたり、その他の細かいイベントがあったりと、いくらでも探検できる裾野の広がり方をしています。世界を冒険する楽しさは尽きることがありません。
こうした実際の広さと要素の充実さが合わさり、世界の広大さと奥深さの乗算によって圧倒的なまでのゲーム的な体積を擁している作品となっています。
続いて、シナリオの話もします。
ファンタジー風の世界観に対し、適度に現代的な銃器なども入った混合した世界観を形成しています。これは割と都合の良い世界観となっており、ファンタジー要素やテクノロジー要素で良い塩梅に物語を転がせますし、びっくりするほどユートピアのような変な要素を入れても、そこそこ親和性があります。
そして、この世界観にもきちんとシナリオ上の意味があるというのも素晴らしいですが、それに加えて各要素をきちんと拾って構成しているという点も優れています。
魔法や銃器、種族といった存在をただ設定するのではなく、実際にプレイアブルで魅力的なキャラクターとして配し、イベントやシナリオで上手く描写をしています。文字上の世界ではなく、表現として活き活きした世界が描かれていました。
加えて、展開は変則的ながらも王道的でもあり、ノーマルのラスボスは言わずもがなで気持ちがある意味では最高潮に達しますし、トゥルーはもはや言葉に表す必要すらありません。筆者の弱いところが全て狙い撃ちされているような展開です。というか多分、JRPG好き全員の弱点です。
展開に必要な要素自体は中盤あたりから匂わせているため、そこから終盤にかけての展開はある意味では予想できるものと言えますが、それ以上に求めていた展開と言えます。ラーメン屋のラーメンみたいなものです。
またシナリオを回すキャラクターも良く、それぞれが個性的で魅力のある性質をしています。
個人的にはウルカノを推しています。ウルカノ、ウルカノって見た目をしている上に、ウルカノという感じの性格をしているのが凄いです。これは因果が逆で、ウルカノっぽいキャラクターにウルカノと付けたセンスが凄いのかもしれません。
サブキャラだと思っていたので、仲間にできた時は嬉しかったですね。
続いて、戦闘の面白さについても話しておこうと思います。
歯車のUIで表されたCTBっぽいATBであり、行動順や戦闘フィールド上の位置を勘案して戦略を練っていくタイプです。
まず敵の状況まで観測できる行動順制御がある時点で戦略的ですが、ここにフィールド上の移動があることで、別次元の戦略性も生まれています。
フィールド上に散らばっていると相手の強力な範囲攻撃の影響を最小限にとどめられますが、バフの範囲に入れなかったり、一斉に回復できなかったりというデメリットもあります。また、場所によって性能も変化するので、そのキャラクターのやりたいことに合わせた立ち回りや位置調整も大事になります。
このあたりのメリットとデメリットを考慮しつつ、行動順を上手く使うことでメリットだけを享受していくこともできます。
ここを考えて行動を組んでいくのが楽しく、上手く戦略がはまり最大火力を出したり、ギリギリで立て直せたりすると非常に気持ち良いです。
戦闘バランスは、こちらの能力も強けりゃ相手も強いタイプのバランスであり、どちらが強みを押し付けられるかで勝敗が変わります。
このためバフデバフはもちろん大事であり、頑張って鋼糸を24つけて光輪で最大強化してぶっ放せばとんでもないダメージが出ます。どれくらい付ければワンキルできるか分からないからちょっと余分に付けすぎるのもご愛敬。
一方で、バフデバフしてたら波状攻撃に沈むことも多々あるので、それより殴ったほうが良いケースもあります。状況や相手によって適宜戦略を切り替えていくのも肝要でした。
とにかく、どんな行動が強いか、どんな組み合わせが強いかを考え、その上で、敵の強みを退けるための戦略を立てないと勝てないバランスです。そして、そこが考え所であり楽しいポイントとなっています。
どういったスキルを付けて対策とするのか、メインウェポンは何で攻めるのか、相手の強行動に対してどういった戦略をとって安定化させるか、事前の準備とその場のアドリブ双方で楽しめる戦闘となっています。
この戦略性はもちろんボスに顕著であり、魔女を始めとして割とギミックボスが多い印象を受けます。
例を挙げれば、アンチマレフィキウムのボスは回復行動を反転させてくる腐敗で場を混乱させてきます。これに対策を立て、その上でそれ以外の行動にも回答を用意する必要があります。
筆者は???の二回目に永久にメイクシフトされるなど、色々なボスに初見で敗れていますが、その経験をもとに戦略を立てて撃破しています。魔法を見直して火力を伸ばす、耐性を考慮して枠を整理する、技に対抗して使うキャラクターを変えたり位置を変えるなど、色々と戦略を立てて挑むのは楽しいです。
個人的に戦っていて一番楽しかったのはノーマルエンドのラスボスでした。
とにかく足が速く、火力も十分の強敵でした。少なくとも密集していると即座にやられるので、できるだけ離しておいてもなお強かったです。
味方サイドでは特定ケースで大活躍していた魔法の分捕りや無限魔法がこちらに牙をむき、改めて異常に強い能力であることを分からされます。ヒュギエイアを分捕られた時は軽い絶望を覚えました。
真のラスボスの攻略にあたっては魔女のスープが刺さっていて、強化解除手段として異様なまでに優秀だなと認識を改めていました。アイテムも有効活用すれば強力な武器になります。
このラスボスは強制睡眠+睡眠という初見殺しをやってはきますが、それ以外は結構まともなので、正直ノーマルラスボスのほうが強く感じています。ランダム魔法のどれを引かれるかも結構寄与しそうではありますが。
また、戦闘から少し離れますが、武器にスキルが割り当てられ、これを何度か使うと習得して外してもスキルが使えるようになるというシステムも秀逸です。感覚的にはFF6の魔石みたいな感じ。もっと近いシステムもあった気がする。
どんなスキルでもまず一定回数使ってみる動機になりますし、その中で何となくスキルの使いどころを学習できます。新しいスキルを触る導線、それを何度か使って把握するタイミングの提供の双方を兼ねており、色々なスキルを上手く使って攻略するゲーム性とも噛み合っていました。
このように、このゲームの良さの10割はフィールドの設計で、あとの10割はシナリオで、残りの10割は戦闘の面白さで構成されています。つまり300%良いゲームです。何ならキャラクター性の良さなどもこのゲームの楽しさの一つなので、300%では済まないかもしれません。シナリオに包含されそうですが。
それ以外にもいくつか細かい好きな点があるのですが、それを挙げるとキリがないので、いくつか紹介するのにとどめます。
まず、フィールド上のアクションでアイテムを回収できるシステムが良いです。オブジェクトに干渉できるという体験が、間をつなぐ要素としても機能しています。
これ以外にもワイヤーアクションができるなど、ただ歩き回るだけでないフィールドギミックが散りばめられ、マップに変化を生み出していました。
後は、村の到達不能領域で家を見切れさせていることで、村としての奥行きを演出しているのが好きです。プレイヤーが移動できる範囲が全てではなく、それ以外にもちゃんと営みがあり、そうして世界が成り立っているという感じがします。
さらにごくごく細かい点として、リベイアを竜の巣で呼ぶとちゃんと本体が動くなどの芸が細かいところも良いです。局所的な例外処理にも手抜かりはありません。
そして最後に、選曲が素晴らしいです。
あらゆる場面の曲がシーンに合っており、かつそのシナリオと共に印象に強く残るものとなっています。
殊にボス戦闘曲は非常に良く、仕事中に頭で勝手にリフレインするくらいには好きなものになっています。URL知りたい。
ここまでおおよそ良い所しか書いていないので、バランスをとるために気になったところについても触れておきます。
まず、戦闘のUIは割とごちゃごちゃした印象を受けます。慣れてくれば情報がまとまっているのですが、初見ではどこを見るか判然としにくいデザインになっているように感じました。
例えば、初見でチャージで増えたものを見逃していたり、リング式の選択UIを横で切り替えた時に変化に気づかなかったりしていました。
特にリング式UIの横切り替わりについては、切り替わった先のリングと形が一致していること、アイコンの色など分かりやすい点で差異が無いので形で見分ける必要があることなどから、そこそこ難しいものになっています。
なので、個人的にはアップデートで更新された押し込められている設計のほうが好きではあるんですが、それはそれで要素が多くて分かりにくいというのも分かります。分離式のほうが総合的なキー押下数は減りそうですしね。
後は、即死とのイベントバトルを越えないとセーブできない幽霊船や、なんとなく勝てそうになる負けイベントなど、若干厳しいイベントバトルがありました。
負けイベント自体は展開上アリだとは思っているんですが、時間の都合上、数ターン経ったら強制的に敗北くらいのバランスが嬉しいです。何となくいけそうだけど絶望的な技もあってジリ貧で負けるという体験それ自体は何だかんだ良いなと思うところはあれど、徒労に感じる面もあります。
このあたりの不満点はあれど、後からこの感想を書くために無理やり引っ張り出した程度には感情に残っていないものとなっていました。恐らく、他のプレイ体験が良すぎて消えたのだと思います。強烈なプラス要素は、多少のマイナス要素を押し流しますからね。
最終日手前でトゥルーを目指している時、更新に気づいて入れてみたらリングUIに改修が入ったところで、そういえば使いにくいと思ってたなとようやく感じたレベルです。個人的には良いアップデートだなと感じていました。
本当にやりたかったJRPGがやれたので、個人的にはウディコンはこのゲームをやれただけでも十分満足しています。そして、そういうゲームがいっぱいあるからウディコンは楽しいですね。
29. 女神の迷宮

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ハクスラRPG | Karukus |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 6時間 | 1.0.14 | 冒険者クリア |
良かった点
- 難易度を上げたメリットがあるというのが面白かったです
- 通常難易度とみられる冒険者では歯応えがありつつも突破できる良いバランスでした
- エンチャント装備を使いつつ、適度に装備を更新していくハクスラが楽しめました
- 装備のバリエーションや個性が豊かで面白いです
- 道連れのキャラクターも個性豊かでした
気になった点
- ダンジョンが殺風景でやや広い印象を受けました
- 一部ダンジョンはその限りではありません
- 特に広い部屋で周囲を確認しても何もないといったことが良くあったので、ミニマップなどがあると緩和されるかもしれません
- 料理を一気に食べさせたくなることがありました
レビュー
装備を回してダンジョンに挑もう
女神の迷宮は、装備をベースにしたハクスラ風味のRPGです。
迷宮に潜り、装備を拾い集めてパーティーを強化してその攻略に挑む流れとなっています。
迷宮はランダム性のあるダンジョンとなっており、彷徨っているとランダムエンカウントで戦闘が始まります。
この戦闘を切り抜けながら迷宮を進んでいき、最奥まで到達できればクリアとなります。最奥には強敵であるボスが待ち構えていることもあり、そのクリアは一筋縄ではいきません。
また、そこそこ火力が高いバランスのもと戦闘が進行するため、油断していると雑魚にも手痛いダメージを負うことになります。消耗を最小限に抑えるには、適度にリソースを切りつつ油断せずに戦うのが肝要となるでしょう。
こうした困難に満ちた迷宮を攻略する最大のカギとなるのは、迷宮に点在する宝箱から入手できる装備です。
グレードアップした装備が拾えることはもちろんパーティーの強化につながりますし、場合によってはエンチャント効果と呼ばれるものが付いたレアリティの高い装備を拾うこともできます。
エンチャント効果は、シンプルなステータスの向上から状態耐性までランダムで付与されるため、強力なエンチャント効果が付いた装備を手に入れることができれば、攻略は一気に楽になります。
雑魚との戦闘による消耗に耐えながら、宝箱を求めて迷宮を探し回っていきましょう。
また、攻略にはパーティー編成も重要です。近接のファイター、防御のバスティオン、補助のメイド、魔法のウィザードなど、いくつかの職種から4人までを選んでパーティーのメンバーを構成できます。
バランスよく前衛と後衛を整えた態勢であれば、道中もボスも戦いやすくなるため、これがスタンダードな攻略スタイルであると言えるかもしれません。
しかし、後衛だけや脳筋だけといった偏ったパーティーで攻略することも可能です。好みのメンバーを選んで迷宮の攻略に挑みましょう。
迷宮でたくさん拾える装備の中から、エンチャント効果も加味しつつ自分なりに取り回していき、雑魚やボスとの戦闘をより有利に進めていくというループが回るハクスラが魅力的な作品です。
また、装備を積極的に取り換えて性能の強化を図っていく中で、運良く強力な装備に出会える楽しみもあります。
装備を積極的に拾っては回していき、迷宮最奥のボスを打倒していきましょう。
感想
無心でダンジョンに潜ってハクスラするのは楽しいので、そのループに上手くハメてくれるこの作品も楽しいです。
相手の火力が高い代わりにこっちの火力も高いバランスをしているので戦闘のテンポも良く、武器の吟味を適度にしながらダンジョンを突き進めます。特にメディックが中盤くらいで習得する自動回復が入ると、戦闘後のメニュー開閉すら不要になるので凄く快適に周ることができました。
筆者は中盤まではグラップラーによる最大火力をバスティオンで補佐し、メディックが回復しつつレイダーが良い感じに立ち回るムーブで進めていました。グラップラーの連続攻撃で火力は大体担保されるので、バスティオンがちゃんと周りをケアできていれば割と問題なく動けます。
ただ、相手の火力もそこそこあるのでバスティオンに集中放火されると怪しい時もあり、冒険者でこれなので超克者だとより厳しそうな印象です。もう少し考えた立ち回りがいるかもしれない。
レイダーは強奪で採用しているところが大きかったのですが、メッセージが流れるのが早くて何を獲ったのかはよくわかっていませんでした。多分換金か固有ドロップを盗んでいるはず。雑魚戦ではむしろ巻き上げるを連打するのが、全体攻撃なのもあって強いムーブに感じました。
また、中盤以降はレイダーを葬儀屋に差し替えた攻撃に比重を置いた編成にしています。中盤あたりから雑魚が苛烈なのもあり、基本的に高い火力で相手を先に殲滅させていくのが大事だと感じました。下手に相手が残ると高火力の一斉被弾でピンチになりかねない。
バスティオンがいればデコイさせて1ターンくらいはもつので、そこを正念場とばかりに殲滅していました。
正直一体しか存在しないラスボスより、道中で大量に出る雑魚敵のほうが怖く、撃ち漏らすとあわや全滅というところまで来ます。あな恐ろしい。
拾える武器のバランスも良く、ネームド装備を拾ってはとっかえて使いつつ、適度に性能差で回っていく良いハクスラが楽しめます。
4人ぶんの5ライン装備くらいが思考のちょうどいいラインな感じがしていて、これ以上増えると大変になるギリギリのラインを突いている印象です。
実は付加効果まで加味すると考える範囲が広がるところもあるんですが、それより性能差が目に入るので上手く回転するという面がありました。感覚的には付加効果も加味して状態異常耐性なども表示されるリッチなステータス画面がある方が良さそうにも思えるんですが、プリミティブなパラメータだけが見える簡素なものだからこそ、装備をアレコレ入れ替えられるという節もありそうです。状態異常耐性が減るのが目視出来たら、装備の入れ替えにちょっと躊躇しそう。
パーティーメンバーを自由に組み替えられる都合上、ダンジョンでは割と死に武器を拾うこともあります。筆者が葬儀屋とグラップラーを入れるというピーキーな選択をしているのが悪いところもありそうですが。
グラップラーの武器ドロップは特に渋くて、最後の最後にようやっとエンチャント付きのものを拾えるレベルでした。ほぼずっとパワーフィストで通していたし、何なら左手は最後までパワーフィストです。よく戦力になったなあ。
そういう意味では一つだけ強い武器が落ちれば十分な葬儀屋は優秀でした。全体攻撃がちょっとでもかすると瀕死になるスリルはありますが。
ダンジョンについては割とだだっ広いという印象があり、結構歩き回ることになります。その割には殺風景なので、このあたりの探索の楽しみはあまりないかもしれません。アイテム回収と戦闘のための場所という感じ。
その分、研究所みたいなデザインされたランダム性があると割と印象が違うので、そういうのが間に入ってきていた点は良いメリハリに感じました。
特に広い部屋だと階段が無いか確認するために無駄な移動が挟まれてしまうことが多く感じたので、ミニマップのようなものがあれば多少印象が変わったかもしれません。探索した感じも出そう。
後は、個人的に好きな点を挙げていくと、難易度を上げるとちゃんとメリットがあるのが良いです。エンチャント入手率が上がるという玄人好みっぽいところを突いているのも良いところ。
ゆかいな仲間との共闘も結構楽しく、ユニークな能力がその時限りで使えるのが楽しいです。RTA走者はキャラクター性も相まってインパクトが強いですね。ちゃんと変な技も持っている。RTA走者を仲間にしている間は本当にRTAしてる気分になったせいか、戻ることなくダンジョンの最後まで突き抜けていました。
30. STARCHILD

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 精密アクション | 朝倉くもり |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 2時間30分 | 1.002 | クリア |
良かった点
- グラフィックも相まって良い雰囲気を醸成していました
- ステージ構成やギミックのアイデアが面白かったです
気になった点
- ジャンプが最後まで感覚的でなかったので、ゲージなどがあると分かりやすくなるかもしれません
- 地形判定が移動する軌跡を加味していなさそうなので、クラゲの移動時にすり抜けることがありました
レビュー
精密アクションに挑戦
STARCHILDは、独特なジャンプ挙動を上手く操って攻略する精密プラットフォーマーです。
様々なギミックから成るいくつかのステージを突破していくことで、クリアを目指します。
挑むことになるステージは、落ち着いた不思議な雰囲気を醸すグラフィックで構成されています。しかし、その穏やかな見た目に反して難易度は高めです。正確かつ素早いアクションが要求されるでしょう。
そのアクションの中でもとりわけ重要となるのは、足場を正確に渡り歩くためにジャンプのコツをつかむことです。その挙動はジャンプというよりも、次の着地までに一定時間得られる浮力が押下中だけ作用する、といったような制動を示します。このアクションを使いこなすこと無しに、上手く足場を乗り継いでいくのは難しいでしょう。
殊に最終盤の精密アクションをミスなく突破していくためには、かなり繊細な操作スキルが求められます。何度も遊んで慣れていきましょう。
ステージごとに様変わりするアートと、各ステージのギミックの特異性もあり、次に何があるのかを楽しみにしながらステージを攻略できる作品となっています。
ジャンプの挙動を熟知し、上手く動かしてラストステージをクリアできた時の達成感はひとしおです。何度も挑みクリアを目指しましょう。
感想
見た目に反してなかなかシビアなアクションでした。最終ステージをやっている時の気分は、壺をやっている時と相似です。そこそこ序盤から精密操作が要求されるタイプなので、難易度を下げて挑んでも相当難しい部類だと思っています。
グラフィックの雰囲気は良くて、トランジションと言い独特の空気感が醸成されています。効果音やBGMの音量が小さいきらいがありますが、静かな世界の印象とも相まってむしろ良い没入感が得られるかもしれません。
世界観が特殊なので最後まで解釈に惑うことはありましたが、美しい空気を感じるだけでも割と楽しめます。
各ステージの構成やギミックのアイデアも多様で、面白いクリアの仕方をしていくステージが多い印象でした。ステージの情景に合わせていることもあって、各ステージのどこも印象が被っていません。
中でもとりわけ印象が強いのは、やはり最高難度で立ちはだかる最終ステージです。ジャンプタイミングを誤って落下していって着地したあたりで、何か良い音楽が聞こえそうな気すらしてきます。あれは心を折る長さをしていました。
一方で、精密重視のアクションとしては若干操作性に厳しいところがあります。細かいところで言えばトゲの当たり判定がやたら大きい割に扉の下入力判定が狭かったり、水面の亀に代表されるような足場から足場への正解がやや不明瞭なレベルデザインは気になるところです。ラストステージにおいて、一度画面内から消えた共鳴が先行する箇所に効いてくる初見殺しはかなりしんどかった思い出。
システムの面で言えばジャンプの挙動がかなり特殊で、このとっつきにくさも操作精度を要求するゲームとしては難しいところがありました。
プレイした印象では、見えないゲージみたいなものがあって、Zを押すと消費して浮力を得るみたいなデザインをしている気がします。本当のところは分かりませんが。このジャンプ仕様がかなり曖昧なので、精密にクリアすべきプラットフォーマーとの相性はあまり良くない印象です。せめてゲージなどで可視化されていれば納得感はありそうです。
例えば、筆者は最初はデフォルトっぽいキャラを使っていましたが、溶岩の二段ジャンプで抜けるっぽい地帯を全く抜けられないので、最初に戻してゆるいジャンプのキャラに変えています。今ならジャンプの仕様が何となく分かっているので抜けられるような気もしますが、初見しばらくでの適応は相当難しいのかなと思います。
物凄く細かいシステム面で気になる所で言うと、恐らく地形判定が移動を考慮していません。具体的に言えばクラゲの移動中に乗ろうとすると抜けます。
多分プレイヤーの落下速度が速く、ちょうどAABBが抜けたのだと思っていて、移動するAABB vs 移動する球に対応していないのかなと感じました。上下にしか動かないならAABBを拡張して、球は移動を加味したカプセルにすれば抜けなさそうです。斜めは難しいので諦めても良さそう。
そもラストステージでは若干処理落ち気味ではあるので、これ以上判定を正しくすると不味いかもしれません。精密アクションと処理落ちはだいぶ相性が悪く、画面内にガスっぽい攻撃が出てきてFPSが落ちることで操作性に割とクリティカルな影響を与えていました。
このあたりのアクションのさわり心地の話はあれど、全体として見ればステージの構成や見目も変わるギミックの多様さが楽しいタイプのアクションです。ここでは何に出会うことになるんだろうと思いながらステージを進められます。
アクションの精密性が求められるので人は選びそうですが、ラストステージをクリアした時には達成感が得られる作品となっています。
31. オチル

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 落下 | ニモチ |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 3分 | 1.00 | クリア |
良かった点
- ステージの難易度の上がり方が良かったです
気になった点
- タイトルアニメーションはスキップできる方がありがたいです
- せつめいが終わるとタイトルに戻るため、2度見ることになります
レビュー
シンプルに落ちよう
オチルは、落下をモチーフとしたお手軽なミニゲームです。
ゲーム性はシンプルなもので、落下中に操作して指定の場所に落ちることを目指すものとなっています。
全てのステージで目的を達成できればクリアです。特にゲームオーバーのペナルティもないので、気軽に遊びましょう。
数分もかからない、短い時間で遊べるミニゲームとなっています。息抜きにぴったりの作品です。
感想
あまりに短いので、何なら説明とフェードとタイトルアニメーションを2回見た時間の方が長いんじゃないかと錯覚しそうな作品でした。少なくともダウンロードして起動するまでの時間のほうが長い。
純然たるミニゲームとして、さっと遊べて良いですね。
ゲーム性はシンプルで、直感的に分かりやすい初回ステージから基本的にルールは体感して分かるようになっています。
イライラ棒についてだけ、空中にいるのに地上から干渉を受ける理由が分からず、唯一初回でミスを喫しましたが、それ以外は直感的に理解して即座にクリアまで持って行けるレベルです。短い時間でやるのに向いていますね。
各ステージの難易度の上がり方は段階的で良く、最後まで特別違和感なく進めることができます。
個人的にはせつめいが終わったら即ゲームでもいいかなとも思っていました。ただ、せつめい後にタイトルに戻され、もう一度アニメーションを見ることの方がクリティカルな問題っぽいので、そちらが解決されたらそこまで気にならないかもしれません。
32. アドリブ・ロール
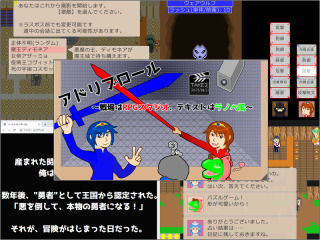
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ロールプレイングゲーム | Masaqq(マサック) |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 45分 | 108 | ノーマルクリア |
良かった点
- 行動のログが物語を作るという体験が面白かったです
- 対応するテキストもバリエーション豊かに用意されています
- 攻撃択のカードがそのままHPにもなる戦闘システムは斬新で楽しかったです
- カードを大量に消費すると強い代わりに脆くなるという、リスクとリターンの関係が成り立っていました
気になった点
- 戦闘にかかる経費の内訳が不透明なので、経費削減の具体的方針が立てにくい印象がありました
- ノーマルなら削減を大きく意識する必要はなかったので、些細な話ではあります
レビュー
ロールを演じよう
アドリブ・ロールは、ロールを演じてシナリオを進め、戦闘を経てクリアを目指すロールプレイングゲームです。
映画の撮影というゲーム設定に則り、プレイヤーが自ら役割を演じて進めていく斬新なゲーム体験が得られるものとなっています。
プレイヤーは映画撮影という形で各エリアで戦闘をこなしつつボスを選んで戦って攻略していき、ラスボスを打倒することを目指します。
この一連の流れは全てRPGの撮影なので、様々なイベントからボスとの熱いバトル、雑魚とのちょっとした戦闘まで、その道程は全て文章として残り、自分だけの物語となって記録されていきます。
プレイヤーの一挙手一投足がきっちりログに残る中で、思い思いのプレイをして自らの物語を紡いでいきましょう。
| 戦闘画面 |
|---|
また、このゲームは戦闘面においても斬新なシステムが搭載されています。
戦闘が始まると、攻撃や強化、回復と言ったスキルを示すカードが配られ、このカードの中から選択して行動を決めることになります。ターン消費無しのカードを除き、原則選べるカードは一枚です。
そうしてプレイヤーの行動が終わると、次にくる敵のターンでは味方に攻撃が飛んできます。この攻撃で発生するダメージは、配られたカードを減らすことで表現されます。4ダメージなら4枚のカードが奪われるわけです。全てのカードを失うと戦闘不能になります。
すなわち、カードは攻撃の選択肢であると同時に、防御の壁としても機能するという設計になっています。
この戦闘システムにおけるドローは選択肢を増やすという価値があることに加え、耐久を上げるという意味も持ちます。防御は一般にやりすごしの択に思われがちですが、このゲームでは回復のようでもあり、選択肢を増やす行動でもあるような特殊な立ち位置として、戦略の一部に組み込まれています。
また、カードの位置も重要であり、次に使いたいカードをダメージで消えない位置に上手く配置できると戦いを有利に運べます。
このように、配られたカードを中心とした戦略性の高いバトルが繰り広げられることになります。相手の行動や対象に取る条件は常に見えているので、その情報を鑑みて戦略的にカードを選んでいきましょう。
なお、配られるカードの質や、そもそものステータス性能はレベルと装備によって培われます。装備は戦闘や店などで取得可能です。レアリティの高い装備はカードの面でも性能の面でも優秀なので、見つけたら積極的に装備するのがお勧めです。
自ら役割を演じ物語を紡いでいく斬新な物語体験と、斬新な戦闘システムのゲーム体験が合わさった作品となっています。
見事撮影を無事に終え、ラスボスを倒した暁には自分だけの映画が出来上がっています。全てが終わってログを眺めるまでがアドリブ・ロールです。自分で紡いだシナリオを見てみましょう。
感想
文字通りロールプレイするゲームというのが斬新で、ゲーム体験としてずっと面白いゲームでした。行動がログとして残るのも良くて、役割を演じた後にその物語を後で追うこともできます。
雰囲気の指定やら細かいテキストの用意などで、諸々のシステム的な側面においても演じられた物語というものを表現しているので、心行くまで遊べました。イベントの選択や戦闘の状況に応じて、ちゃんと個々人の体験が特殊化されていくのも好きです。
戦闘システムもかなり斬新で、これ単独だけでもギミックとしてゲームを作れるんじゃないかという水準を余裕で越えたところにあります。
攻撃択を防御の値ともみなすシステムが面白く、ただ攻撃カードを選んでいくだけでも戦略性が生まれます。事実上はHP消費攻撃みたいな立ち位置に思えますが、カードの位置にも意味があったり、強化即攻撃のようなリスクリターンの見合った択が用意されていたりと、そのバリエーションはただ自身の耐久を削って出す技という印象に留まりません。
その上で戦闘のテンポも良く、かなり火力高めの調整がされているのかサクサクと敵を倒していくことができます。ボス戦も決して長引かず、それでいてカードによる小さなHPの削り合いであるが故の接戦している感覚も得られます。
こうしてテンポと戦略性を両立しつつ、カードの組み合わせによるコンボダメージみたいな気持ち良い要素も完備されているので隙がありません。
難易度もやや緩めで楽しみやすく、ノーマルでは適度に苦戦しつつも危なげなくクリアできる調整となっています。ノーマル専用の仲間がいて、これがべらぼうに強いので爽快感をもってクリアできました。
そこでシステムを学習して詰めたくなる人向けに高難度も用意されているので、そのあたりも至れり尽くせりとなっています。
戦闘面で唯一分からなかったのは戦闘に使っているお金で、何をした結果発生しているのかが最後までいまいち分からないままでした。もしかしたら説明を読み飛ばしたのかもしれません。
ノーマルで遊ぶ分には経費削減をそこまで気にする必要はないので、ハード以降で詰める時に考えればいいという話ではあります。
物語というかログに話を戻すと、テキストの行き届き方がかなり印象的でした。2ターンで魔王を倒せばわずか2ターンでの決着、のようにそれっぽい文章を付けてくれます。
このあたりの定型だけど自身の体験に確かに紐づいたテキストの組み合わせというのが、まさしくロールを演じるという設定に貫徹していて、遊んでいて納得感があります。
ログの中では、連携名がちゃんと残ってくれるところとか、逃げたら逃げたログが記述されるところとか「スタッフが尺稼ぎに困っていたようだ。」みたいな設定としてのメタも組み込まれたところが好きです。細かいネタっぽいのが好きなのかもしれません。
あと、このログは最終的にhtmlファイルとして吐かれる当たりも手が込んでいて良いところですね。
周回要素も結構あり、イベントの分岐やら仲間の種別もある、割かし周回前提の作りのような作品となっています。それ相応に一回のプレイ時間はテンポの良い戦闘により短めに収まっているので、とりあえず一回遊んでみるのが良いんじゃないかなと思っています。
自分の物語を行動から紡ぐという体験も、カードを基軸にしたシンプルで遊びやすい戦闘システムも楽しめる良い作品です。
33. ロロろくプラス

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 世代交代型部隊運営SLG | a-e |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 5時間 | 1.06 | ノーマル魔将撃破 |
良かった点
- 調子や寄る年波により、常に固定化されないメンバーでの戦略を考えることができて楽しいです
- 敵の行動が明示化されているため、チーム編成と隊列のレベルで戦略を組み立てる楽しみがあります
- 各ユニットに独特の個性があり、どのユニットも使ってみたくなります
気になった点
- 子供が出来た上で実践投入できるまでの期間が魔将出現に比して長めに感じました
- 子供が出来て強い部隊が作れるようになると楽しくなってくるのですが、その前に魔将とLv3魔物群に心を折られかけました
レビュー
世代を回して部隊を運営
ロロろくプラスは、世代交代しながら部隊を運営し、次々と湧く魔物を倒していくシミュレーションゲームです。
次世代を見据えた運用や新陳代謝の意識など、長期的な視座が求められる作品となっています。
大前提となるゲームのシステムは、拠点において人材を募集してユニットを雇うといった準備をし、準備が完了次第遠征に赴き、ワールドマップを歩き回って各地の魔物を討伐していき、頃合いを見て再び拠点に戻る、というループから成り立ちます。
拠点では最大14人までのユニットを雇うことができ、魔物との戦闘ではこの中から7人を選出して隊列を組んで討伐していくことになります。
| 戦闘画面 |
|---|
戦闘は半自動で行われ、味方の行動と魔物のルーチン行動が交互に繰り返されます。プレイヤーが干渉できるのは、相互の行動が終わった後に「ステイ」するか「ローテート」するかの選択だけとなっています。
ステイすれば隊列は維持され、再び双方の行動が実行されます。一方、ローテートすれば前衛は後衛、中衛は前衛と移動してから行動します。
前衛にいるユニットが近接攻撃をするように、各ユニットは隊列上の位置に応じて取る行動が変わります。各ユニットには得意な位置とその行動があるため、可能ならばそこでステイし続けたいところです。しかし、ローテートを回さないとダメージを軽減する回数が回復しなかったり、体力回復が特定列でしか行われなかったりと、ジリ貧になりやすくなっています。
敵の行動ルーチンに合わせた、適切なローテートが攻略において重要となってくるでしょう。
そうして各隊列をローテートして上手く魔物を撃破するには、隊列を機能させる7人の選出、引いてはその選出を下支えする14人のユニットの編成がカギとなります。
すなわち、拠点の人材募集で得られるユニットの厳選がそのまま戦闘力につながるというわけです。前衛に強い職種や後衛に向いた職種など、様々な職種とその性能差の中から編成のバランスも考えて採用していきましょう。
ここで重要なのが、どのユニットも戦闘を通じて成長し、年も取るということです。若い内はどんどん成長しますが、老いさらばえれば能力は劣化していきます。即戦力を割り当てていくも良し、期待の若手を採用するも良し、世代の入れ替わりを意識して部隊を運営しましょう。
そうして年月を経るほどに成長と厳選を重ねて部隊は強くなっていきますが、その一方で敵もまた強くなります。
充分時間が経つと、ある程度鍛えた程度の部隊では壊滅的被害を被るような魔物も現れるようになってきます。こういった魔物を倒すためには、長い目で見た部隊の成長プランが不可欠となるでしょう。
また、強い魔物を無視して弱い魔物だけを討伐することも可能ですが、魔物は放置すると瘴気度を上げてきます。これが一定値を超えるとゲームオーバーになるため、あまりたくさん放置もできません。場合によっては腹をくくって討伐に向かいましょう。
ゲームオーバーにならずプレイを進めるには、様々な人材から自分なりのユニットを選んで部隊を運営していく長期的な戦略と、事前に示された魔物の行動を元に選出する7名と隊列を考えて上手くローテートして倒す短期的な戦術の双方を必要とします。
加えて、前者は後者の取れる選択肢を広げ、後者は戦闘を通じた成長という形で前者と密接にかかわります。この交じり合った高度な戦略と戦術を並行して立てていき、ゲームを進行していく楽しみのある作品です。
ここで紹介したものに限らず、いざという時に使うアイテムや、リーダー格の子供を作って能力を一部継承していく仕組みなど、様々なシステムを駆使して部隊を精強にしていくことができます。
あらゆるシステムを駆使し、ユニットを鍛え上げて運用し、強力な魔物に挑める部隊へと成長させていきましょう。
感想
正直な話をすると、楽しくなるまでに時間のかかるゲームです。遅効性の面白さ。遊び方というか、動かし方が分かってこないと楽しめない部類のゲームだとは思うので、今からやるなら有識者の遊び方を参考に取り組むのが良さそうです。
類型ゲームとしてセブンとヴィーナス&ブレイブスというものがあるらしいですが、この辺履修していないがゆえに詰まったところはあるかもしれません。
何もわかっていない初見だと、Lv2の時点で相当の苦戦を強いられることになります。メンバーのバランスとか、ローテーションの組み方とか、そのあたりの方針が固まっていないと、どんどん難しくなります。
加えて中長期的な視点がかなりのウェイトを占めることもあって、場当たり的な解決をしていると真綿で首を締めるように苦しい時間が続くことになります。
ここにLv3と魔将が来て崩壊したのがファーストプレイです。
そこで立ち回りをある程度学習し、必要な要素を朧気に理解した状態から始めることでようやくクリアに漕ぎつけました。必要なものに対する逆算力が問われます。後はユニットガチャ運。
そうして強いユニットを引き、上手く運用し、子供に引き継いだ30年目あたりからようやっと楽しさが見えてきます。子供の強さを利用して他のユニットの引き上げを図り、それをまた他の子供へと還元していくことで、ようやく安定して強いユニットを供給することができるようになりました。
その状態ですらLv4は結構ギリギリで、神宝を使ったうえでなお薄氷の勝利でした。何なら一度は敗北しています。
隊長をデコイにしつつ、うまいこと負荷分散していくのが肝要でしたが、70%の集中を見越した構成であり戦略でもあったので、かなり運に左右される展開ではあったと思います。
ここまでの流れは、端的に言うとローグライクのようなものとはまた違った意味合いで喪失のデザインをしているので、モチベーションが続きにくい部類ではあると感じました。
次々に湧いてくる敵を、ちゃんと部隊運営した上で倒す必要がある一方、こちらの仲間はガチャ運に左右され、ある程度戦略性を保っていても時間経過とともにどんどんしんどくなっていきます。
加えて、特に引き継げる分かりやすく強い要素もないので、ずっと喪失を味わっている気分になってきます。
引き継げる要素として強い子供や神宝についても、前者は活用できるまでに時間がかかり、後者は使い切りなのでここぞという場面でしか使えません。自分が強くなっているか弱くなっているかもわからないまま、ひたすら世界をうろつき回るのは中々しんどいものがあります。
ここを乗り越え、部隊運営の面白さに目覚め、子供への引継ぎによる強化を実感するまでには恐らく30年以上のプレイが必要になってきます。山を越えるまでが長い。山の上で面白いですよと叫んでる人を見かけないと、なかなかチャレンジしにくそうな感じがしますね。
また、マップの巡回要素も少し難しいところがあります。魔物はポンポン湧いてくるので、ちゃんと上手いこと回って潰していくのは結構骨が折れます。動くのにも時間を使うので、効率よく回れないと一気に瘴気の進行が進むことになるからです。
ただ、魔物の対応にだけ追われていると結局ジリ貧なので、どこかでアドを取ったり損切りしたりといった判断が必要になります。漫然と回るだけでは安定は覚束ず、Lv3を諦めたり、遠くのルートを採択しなかったりといったことも重要になってきます。
続いて、戦闘の戦略性についても話します。パーティーをラインに分割し、回して戦わせるのが面白く、操作は簡単なのに高度な戦略性を伴っています。
まず第一の戦略として、戦闘前に位置関係によって発生するスキルの有効性を事前に見定めて隊列を組むというものがあります。
高い攻撃力と自己回復を兼ね備えるが支援能力がない暗殺者や、列回復という強みがあるが癖のある占星術師、などなど、各ユニットごとに特色があるのが面白いところになってきます。
色々とシナジーもありそうなんですが、シナジーを考えられる程潤沢にユニットを雇うのは割と難しいです。雇える人数の制限もあるので、何なら戦いを始める前のユニットを雇う段階で勝負は始まっているとも言えます。
このあたり、与えられた豊富なカードから組み合わせを見つけるタイプのゲームでなくて、厳選したカードを使って戦うタイプのゲームかもしれません。筆者は厳選が苦手なので、与えられた手札で戦いがちではありましたが。
7人という採用人数も絶妙で、ローテを組もうとすると大体一人浮きがちになってきます。そこを浮いても戦える強い人材で埋めるのか、浮かさせずに全体をやや薄めるかという判断が必要になってきます。
そして第二の戦略として、戦闘中のライン交換のタイミングを見極めるところがあります。
相手の火力は意外と高いので、ローテの仕方をミスると普通に負けます。隊長しか狙わない、などの狙い判定もちゃんと見て適宜運用していく必要が出てきます。
そして、ここで何よりも大事なのは相手の行動を見ることです。敵の動きのローテは決まっているので、その中の一部分でもいいから防ぎきるビジョンを持っておくのが大事になってきます。
可能であればローテを完封できる構成が用意できるのが理想ですが、そんなにうまくはいきません。ちゃんとビジョンを持った厳選をしていないとユニットが揃わないので。
完封できない場合は、対応方法を頭に入れつつ、咄嗟のアドリブで攻略する場面も多くなってきます。このあたり、3秒という思考時間が良い味を出していて、常にちゃんと思考を回して戦うことになり、こういった戦闘に緊張感が生まれます。
改めて、最初のプレイでLv3に囲まれて老兵しかいないパーティーが蹂躙されていく様を見た時は軽く絶望していましたが、その経験を糧にして楽しくなったゲームです。
こういうゲームに慣れた脳みそが無い場合は、事前に攻略法などに目を通しておくと楽しみやすいかもしれません。自分で色々試してみるのも楽しいので、それも良いとは思います。
34. BerriesWitch

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 果実育成SLG | たう |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 2時間 | 1.08 | クリア |
良かった点
- 素晴らしく、またゲームらしい遊び心のあるUIでした
- 引継ぎ要素の塩梅がちょうどよく、気軽にリトライして進められます
- 交配を繰り返して自分なりの最強果実を作っていくのが楽しいです
気になった点
- ゲームオーバー時、全ての果実は売る以外にないので、次の周回を始めるタイミングで自動売却してほしい気持ちになりました
- ロックを外して一括売却するコマンドがある、というのでも良いかもしれません
レビュー
交配を繰り返して自分だけの果実を作ろう
BerriesWitchは、種をまき果実を育てては交配して、美味しい果実を作り上げていくシミュレーションゲームです。
シナリオ進行の壁として立ちふさがる品評会を勝ち抜くためにも、よりおいしい果実を作るという目標を目指すことになります。
| ゲーム画面 |
|---|
まずは農地に種を植え、成長させることで果実を収穫することができます。そうして収穫した果実を組み合わせて植えることで、その親の性質をある程度引き継いだ果実が作れるようになります。この交配を繰り返していき、より良い性質の果実を作っていきましょう。
ただし、果実の性質を飛躍的に上昇させるには、交配だけでは足りません。品質の更なる向上には魔法が不可欠です。
植えた農地にんは二つまでの魔法をかけることができ、これが収穫できる果実の性質に強い影響を与えます。果実の伸ばしたい方向が決まっていたら、積極的に使うのがお勧めです。
魔法は魔法石を消費することでランダムに手に入り、魔法石は果実の売却によって得られます。交配に使わない余った果実は売却し、より良い果実を作る魔法のための基盤としましょう。
これらの行動を一定回数繰り返した後、育てた果実のうち四つを持ち込んで品評会に挑むことになります。
品評会は、審査員の欲しい性質の果実を推測し、それを料理して提出するQTEとして表現されています。その中で、使った果実の品質の良さや好み、そしてQTEの結果も加味して加算されていくスコアを競うことになります。周りの誰よりも高いスコアを取ることが目標なので、良い果実をセレクトし、QTEを成功させて突破を目指していきましょう。
なお、負けても三度まではリトライできるので、下振れてしまっても安心です。それでも勝てないなら果実の力不足を意味するので、大人しく一から出直しましょう。一から出直す場合は魔法と魔法石を引き継げるので、二週目はより良い果実を作りやすくなっています。
適切に交配し、魔法を適度に使っていけば、高いレベルの果実が作れるようになってきます。原則、子は親より良い性質を持つため、これを繰り返せばよりハイレベルな果実を作るのも夢ではありません。
品評会という制限時間もある中で上手く交配を繰り返していき、品評会で勝てるような自慢の果実を育てましょう。
感想
個人的今ウディコンUI大賞受賞作品です。それくらいにUIが良い。
UIの良さは主に使いやすさにあるとは思っているんですが、そこを当然のように担保しつつ、ゲームとして遊び心のある演出が仕込んであるというのが良いポイントです。右上に出現するUIがちゃんと戻る時にアニメーションするような、細かいところまで配慮の行き届いた動きをします。
ゲーム性もUIと強く紐づいた操作から成るものとなっているため、この動かしていて気持ちの良いUIはかなり強い効果を発揮していました。良いタイプのソシャゲみたいな感じ。
ゲームとしても交配を繰り返して果実を作っていくのは楽しく、適度に品評会という目標が設定されるのもあって目的意識を持ちつつ進めるこがもできます。
品評会までの日数は割と短く、そういう意味でもリプレイ性は高いので、ミスっても1時間かからずに最終品評会までは辿り着けそうなのも良いところです。
リプレイ性については、魔法石の持ち越ししかないというのが良い塩梅の引継ぎ要素となっています。
魔法は極めて重要なので、これを引き継げると確かに強力な助けとなります。その一方で、ゲームの本質はあくまで果実なので、そこは最初から育てていく必要があります。
本質を補佐する要素を引き継ぐことで、確かに便利になった実感を得つつも、遊びとしては初めから楽しむことができるようになっています。成長の頭打ちもケアした、良いリセットでした。
個人的な攻略の印象としては、二種程度に絞ったうえでガンガン新しいのに差し替えていくのが効率良さそうに感じました。クリア時のプレイでは味を多種類揃えて挑みましたが、持ち込みが四種に限定されることもあってあまり効果的ではありません。結局は、自分の考えた最強の果実を叩きつけるのが一番強いです。
Lv4くらいの果実ができたら品評会で勝てるラインに乗っていそうなので、あとは頑張ってQTEをこなせば勝てます。エクセレントは絶妙に難しい。
三回リトライさせてくれるのも嬉しいところで、下振れをキャンセルしつつ上振れを狙える良いチャレンジ回数となっていました。三回挑んで負けた場合、果実の力不足であるという諦めをちゃんとつけることができるのが良いですね。
ストーリーについても、シンプルなゲーム性を妨げることなく、テンポを損なわない範囲で役割を振られたキャラが明快に動く、気持ちの良い成長物語となっていました。
その上で周回前提で配慮されているところもあり、徹底してゲームに付加価値のみを提供するものとしての役目を果たしています。短編としてちょうどいい。
最後の最後に果実撮影会のための時間が用意されていて、ここで各プレイヤーごとの果実を拡散できるようになっているのも良いんですが、その時間で手動で売却していくのは少し面倒でした。
自動で売り切ってくれるのでもいいですし、一括売却コマンドでもいいんですが、何らかの方法は欲しいなと感じていました。翌週ボタンで自動売却が一番プレイヤーの手間は無さそうですが、分かりにくくはあります。一括売却も普段は邪魔というのもあって難しいかもしれません。
とにかくゲームに集中できるUIと、それを阻害することなく補佐していく要素の整い方が良く、必要な要素が整頓されたゲームという印象を受けました。ゲームとして綺麗にまとまっています。
尖った要素を享受して楽しむゲームもあれば、安定した楽しさに浴するゲームもあり、こういった様々なゲームがあるのがフリゲの良いところだなとつくづく感じ入っています。
35. 睡蓮
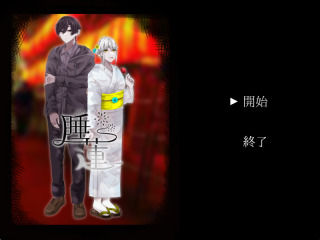
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ノベル | リュース |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 12分 | 1.23 | 読了 |
良かった点
- 良いボーイミーツガールでした
気になった点
- タイトルが睡蓮である理由が気になりました
レビュー
掌編ボーイミーツガール
睡蓮は、掌編のノベルゲームです。
ある少年とある少女の出会いと交流が、率直な筆致で描かれている作品となっています。
作中の舞台とも言える夏という季節に相応しく、夏、浴衣、花火という黄金比でもって構成されており、その空気を感じることができるでしょう。
また、ごくごく短く後味の良い物語でもあるため、掌編として気軽に読むこともできます。
ぜひ手に取ってみて下さい。
感想
ごくごく短いボーイミーツガールでした。夏、浴衣、花火、ボーイミーツガールは、黄金比ですね。
短編として、そしてその短い物語として良く心に残る作品でした。
個人的には、主人公の生気の落とし方が割とリアリティあるのが良いなと思っています。明らかに気落ちしているし気力はないけれど、外食のためにちょっと出かけるのに躊躇はないし、おいしいと評判のうどん屋は知っている、それくらいの感覚です。
気分が底に落ち続けているというよりは、常に逃げ続けてる方に近いというメンタルに対してかなり正鵠を射た描写なんじゃないかなと思っています。それなりに生活はしているけど、生活そのものの充実性はなく、友達がいるかは不明だけど、評判のうどん屋の話を聞くないし耳に入れて覚えておく程度の余地はあります。
こういう極端な人間の話ではないという表現が良かったです。真白はあまりにも救いとして極端な光ではあったかもしれませんが。
主人公の行動様式については、最悪を想像しているというのもあるかもしれませんが、それ以上に己の罪悪感があまりに救われたくすらなさそうな状況であり、そのあたりを曲げて仮託して逃げるというのは心の防御行動なのかもしれません。
向こうから連絡してこなかったあたり、向こうは向こうで主人公のこの辺の心理はよく理解していそうではあります。主人公側から連絡させないと、この心の影はずっと落とすという判断なんですかね。正しそうですが、このミーツガールが無ければ成立しなさそう。もっとも、最悪ケースでも来年会うことで帳尻を合わせようとしていた可能性はあります。
こういった、どこまでも悪人がいないストーリーなのは個人的には好きなのでプレイできて良かったです。
そして、これは本当にどうでもいい感想ですが、かき氷のシロップはおおよそ味が一緒なことでお馴染みですが、夏味はちゃんと味変わってるんでしょうか。
36. ヒーローの冒険

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| RPG | OZ |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 3時間 | 1-0-2 | クリア |
良かった点
- 装備を作って階段状に強くなっていく楽しさがあります
気になった点
- 装備合成はかなりの稼ぎが前提となっていますが、ランダムエンカウントと確率ドロップで収集がやや辛めです
- せめて序盤のひたすらコウモリを倒す稼ぎは緩くして良い気もします
レビュー
素材を集めて強い装備を作ろう
ヒーローの冒険は、アイテムを合成して装備を作り戦闘を優位に進めていくRPGです。
シナリオはほとんどなく、戦闘メインで進行していくことになります。
戦闘バランスはかなり尖っており、序盤の内は、開始エリアから少し進んだ場所に入ってエンカウントするだけでも負けかねない難易度です。
奥へと進んでエリアを越えるとますます強くなっていく、そういった敵に対しても勝利を得るためには、装備が重要となります。アイテムを集めて合成することで装備を用意できれば、一気に強くなることができるでしょう。アイテムはおおよそ敵がドロップするものから構成されるので、雑魚をたくさん倒して集めていく必要があります。ひたすら雑魚を屠り、強敵への糧としましょう。
なお、ついでにクエストで討伐の任務を受けておくと、合成に必要なお金も集まって一石二鳥です。
そうして戦闘を続け、エリアを進んでいくにつれ、装備だけでなくパーティーのメンバーも増えていきます。
メンバーが増えると戦いが楽になる一方で、各メンバーの装備を揃えていく必要も出てきます。よりアイテム集めに血道を上げる必要があるかもしれません。装備の過渡期においては、上手く使い回していくのも大事です。
全体的に戦闘をメインとし、戦闘回数の多いRPGとなっています。
戦い抜いて、装備を作り上げ、より強い敵に挑んでいきましょう。
感想
稼ぎ前提のバランスのゲームでした。とにかくひたすらアイテムを揃えて、装備を作ってしまいさえすれば一気に強くなれます。
この辺の強くなった感覚の分かりやすさは良かったです。強い装備を作る、仲間を増やす、といった一つの達成項目ごとに階段状に強くなっていく構成で、グラデーション的でない強化要素となっています。この感触が、連戦する唯一のモチベーションとして機能していました。
一方で、この稼ぎ前提バランスは序盤から徹底されているので、序盤からだいぶ厳しくなっています。優に100は超える戦闘が序の口です。
難易度的にはずっとコウモリを倒す必要のある序盤が一番辛い可能性すらあって、最初にちょっと強くなったかなと思って進んでみたら、キャタピラーに一瞬で蹂躙されるようなレベルです。ある意味では乙なもの。
序盤から合成難度が高いことも相まって、このレベルデザインはプレイヤーがいきなり壁にぶつかることを意味しています。さすがにもう少し手加減しても良いのではと感じました。
ある程度遊び方が分かってきて、装備が整ってくれば、永久強化要素もある上に装備が強いのでほぼ負けることはなくなってきます。アイテムを揃えていくと図鑑コンプ報酬で良いものがもらえるので、意外と合成しなくてもアイテムは手に入ってくれました。
とはいえ、クエストの達成のための敵がランダムエンカウントなので会えない時は本当に会えず、ある程度稼ぎのための周回は必須です。
そうして辿り着いた筆者の最終構成は、ヒーローがタゲをとって戦士が会心二連続攻撃でひたすら殴るところに落ち着きました。 会心装備を作って殴るのが一番強く、引き付けるで着ぐるみがタゲをとればさらに安定します。
ここで魔術師が常にヒーローにヒールを投げ、盗賊はピコハンの防御減少やパワーアップ、アイテムによる回復などをやればより安全です。
この方針は敵がグレートドラゴンでも安定しますが、回避も完全対策も不能の睡眠があるので、これはお祈りするしかありません。とはいえ、即死性能がある技を持っていたという点を加味すれば、リリスのほうがグレートドラゴンより強いまであったかもしれません。
37. エド王子の冒険 大地の精霊と邪悪な神

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| RPG | せーのすけ。 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 5時間 | 8/4 | クリア |
良かった点
- 展開に応じたNPCの言動の変化が細かく用意されていました
- 雑魚も十分に強い戦闘バランスでした
気になった点
- 階段の接触判定が狭いため壁を擦るように動くと降りられず、毎回位置調整が発生するのがややストレスでした
- ダンジョンを脱出するとき、リバックしてワープするのが二度手間なのでワープに統一しても良い気がします
レビュー
王道RPG
エド王子の冒険 大地の精霊と邪悪な神は、王道を征くRPGです。
ゲームシステム、世界観、シナリオの運びなど、あらゆる面で王道を攻めた作品となっています。
まずもって、魔王を倒すために勇者が旅をするというシナリオそのものからして王道の雰囲気が漂っています。そして、その雰囲気を裏切ることなく、あらゆる面で丁寧にオーソドックスな作りをしています。
ワールドマップで町を渡り歩き進めていくゲーム進行、そうして辿り着いた町で発生するイベント、その全てが堅実かつ王道的に作られており、RPGに慣れていればよりサクサクと進めることができるでしょう。
戦闘システムもまた、分かりやすいシンプルなターン制で構築されています。ただし、難易度はやや高めのものとなっており、雑魚を相手取っていたとしても、スキルをケチると場合によっては全滅まで見えるバランスとなっています。敗北を避けるには、惜しまず戦うのが重要です。
いわんや、シナリオの壁となるボスもまた強敵です。特にこちらの様々な耐性を低下させる行動が脅威であり、事前に対応した耐性を上げておかないと圧倒的に不利な状況となってしまいます。一度戦って敗北したら、その情報をもとに装備の組み合わせを考えてから再戦していきましょう。
最後まで一貫したオーソドックスなデザインで構成されたRPGです。このため、奇をてらうことのないRPG体験を得られます。
戦闘で強力なボスを打倒し、シナリオを進行し、ゆくゆくは魔王を倒す王道的な体験をしていきましょう。
感想
かなりオーソドックスめなRPGです。展開とか戦闘の設計とか、諸々が基本に則り作られたRPGという感じ。尖った特別な要素はありませんが、尖った要素がないことそれ自体がアイデンティティとなっています。
中でもシナリオはかなり王道というか往年のRPGっぽく、長ったらしい話もなくサクサクと進みます。この辺は巨人の肩に乗っかったシナリオとでも言いますか、かなりお約束に準じることでテンポを上げているように感じました。
RPGに慣れていれば何となくここに行けばいいのは分かるし、誰に話しかければいいのかも分かる、そういった暗黙の了解のような決まりごとにかなり則っているので、RPGに慣れているとサクサク進められます。
その分、次にやるべきことの話でも結構あっさりとした感じで話してしまうので、読み流しているとたまにやること分からなくなりがちではあります。
説明がないことで厳しい場面もちょこちょこあり、パセポの村をずっと探していたら崩壊した村のことを指していたというのが順繰りに巡回し続けてようやく発覚するということもありました。どこに説明あったんだろう。
とはいえ、おおよそのイベントはなんとなく発生しそうな場所に空気を読んで行けば発生するので、己の直感に従えば大体うまくいきます。
また、そんな王道かつともすれば淡泊でもある物語運びではありますが、シナリオ自体はちゃんと王道に良いものとなっています。
展開に応じたNPCの会話変化も細かく、ちゃんと闇に覆われたら不安になりますし、 襲撃中でも店は開きますし、助かれば感謝も言い、光が晴れたエンディング後にも専用の会話がありました。このあたりの微に入り細を穿つ作り込みは好きです。
戦闘面については、割と尖ったバランスな印象を受けますが、何とか乗りこなせるレベルに制御されてもいます。
とにかく強力な攻撃を作って提出するのが強く、クリティカル必中3連などを押し付けていくのが理想になるタイプです。
くじ引きで引いた武器は割と最後の方まで頼りにはなりますが、終盤になるとさすがに一筋縄ではいかなくなることもありました。とはいえ、運用次第ではお世話になりますし、雑魚戦では普通に強いです。
また、終盤の雑魚はかなり強いので、スキルを使いまくるつもりで戦わないと普通に負けることもあります。物理反射は面倒なので戦わないという選択肢もありかもしれません。
なお、終盤にまで辿り着いていると戦闘開始前フェーズでのパッシブスキルがそこそこの数あるため、その影響で少しゲームスピードに影響が出るのは気がかりでした。逃げるつもりでも結構待つことになります。
ボスも十分に強く、こちらが戦略を練って耐性をつけていても容赦なく耐性を落としてきます。耐性装備は戦闘を優位に進めるために運用するもののことが多いですが、このゲームではそれがスタートラインです。マイナスをゼロにする作業。
なお、ボス戦も含めて割かしS調整が重要なゲームバランスをしている印象ですが、肝心の素早さによる順序が見えにくいゲーム性となっています。たまに、素早さをどれだけ上げても上を取られることがあるのはいまだに良く分かっていません。乱数入ってるのかな。
細かいところの遊びにくさがないわけではありませんが、諸々王道に仕上げることで良いテンポ感と割と難しめの戦闘バランスを楽しめる作品でした。
38. ~罠~狙われた仔共たち・・

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| RPG | 零八識 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 2時間 | 1.00相当 | 全ENDクリア |
良かった点
- 特にボスのグラフィックが美しいです
気になった点
- 水のようなもので誘導がありますが、フレーバーとしても配置されているため誤誘導が発生している印象があります
- 別ENDになるまでの道が一番きついですが、目に悪そうな画面全体の明滅がありました
レビュー
ダイナミックなグラフィック
~罠~狙われた仔共たち・・は、荘厳で迫力のある敵グラフィックと、それに引けを取らない巨大な数字が特徴のRPGです。
圧倒的な迫力を持つボスを前にして、圧倒的な数字のダメージで殴り合うことになります。
その圧倒的な数字に打ち勝つには、こちらも圧倒的な数字を用意することが重要です。マップを探索し、超強力な補正を持つ装備を手に入れることで、初めて五分の勝負に持ち込めます。
なお、戦闘は巨大な数字の応酬とはいえ、そのベースはオーソドックスなシステムです。適度に回復し、隙を見つけたら攻撃していくことで相手を削っていくことになります。敵のHPは膨大ですが、こちらの攻撃力もまた甚大です。強力な火力でもって殴り続ければ倒すことができるでしょう。
タガの外れたような数値の殴り合いができるゲームとなっています。
次々に立ちふさがる絢爛なボスを撃破し、シナリオを進めていきましょう。
感想
ひらすらダイナミックなグラフィックを浴びつつ、とにかく巨大な数字を見ることになるゲームです。もはやそこにある数字に意味はないんじゃないか、というレベルで大きな数字で削り合いをすることになります。
戦闘バランスはかなり大味で、特にボスは全強化を先にやってあとは防御の石と大回復で耐久していくゲームとなります。
強い技を連打するだけでは勝てないので、決定ボタンを連打するゲームではなく、固定ルーチンをひたすら回すことになりました。脳みそは動いていないけれど手は動いています。
また、どれだけ防御力を上げても恐らく防御貫通攻撃で通されてる気がするので、HPと鬼のように高い攻撃力以外のパラメータに意味はないかもしれません。回避と命中に関しては完全に死にパラメータかも。
難易度の面で言うと、最初のボスが一番の鬼門で、2番目のボスの初撃だけ厳しいという印象です。
最初のボスは色々揃ってないのもあって普通にしんどく、回復アイテムを拾ってからは攻撃と回復を繰り返し、適宜魔法吸収するだけなので割と簡単です。
ラスボスはそれほど難しくはありませんが、HPは恐ろしいほど高いので耐久力を試されます。
シナリオ面では演出が長めで、OPの演出のテンポ感が最後まで通貫しています。退出するためにゆっくり下がり、そこから間を空けて、別のキャラクターが来るあたり、決定キーを押さないと進まないイベントかと思いました。せっかちには辛い。
エレベーター演出についても、最初に見た時はどうして入力が効かないのかも分かっていませんでした。
また、ダンジョンには迷いの森や滑る床、ワープゾーンと言ったギミックがあって戦闘以外でも遊べるようになっています。
ただ、迷いの森のヒントは言及がなく、滑り床のロジックは今でも謎に包まれています。いつの間にかクリアできたので、宝箱を一つ回収し損ねました。ワープも最初に遭遇したのが入り口に戻すものだったのでそういうものかと思っていましたが、どこかと繋がっているワームホールでした。
とにかく手当たり次第に色々試すのが攻略の糸口っぽいです。
そしてこの作品、ある意味オチが祟女と相似かもしれません。一番怖いのは人間なんですかね。最後にスクロールして絵が映し出されるのはインパクトがあって良かったです。
それにしてもあのドラゴン、手加減していた割に強すぎませんか。
39. デジチューバー

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ミニ育成シミュレーション | KAZUTO |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 5分 | 1.00相当 | 全END |
良かった点
- END到達時に一定の変化があるなど細かい演出があります
気になった点
- 特にありません
レビュー
とにかく短い育成シミュ
デジチューバーは、配信者を育成するごく短いシミュレーションです。
短編として構成されており、育成シミュレーションとしては行動回数は少なめとなっています。
しかし、その少ない行動回数とは裏腹に、このゲームは様々なバリエーションの分岐を抱えています。プレイヤーの数少ない選択は、メインキャラクターであるデジ子のその後に強い影響を与えるでしょう。
行動回数が少なく短く遊べることから、全てのエンド分岐をさらうのは難しくありません。
異なるエンディングで見られるデジ子の変化を楽しみましょう。
感想
めちゃめちゃ短編です。ごく短く、読み味も明るいニディガみたいな印象。
育成シミュレーションではあると思いますが、この短さだとミニゲームと表現するか迷うラインです。でも、方向性を定めているのでやっぱり育成かもしれません。
行動回数も少なく、それによって派生し得る分岐も多くはありませんが、むしろこの行動回数にしては分岐は多いまであります。
直前のENDによってタイトルが変わる細かい演出もあり、サクサク全部見ていく動機にもなっています。一周もごく短いので気軽に回せました。ちなみに、筆者はED4の見た目が一番好きでした。
40. 可愛い子と夏祭りに行きてえよなあ!
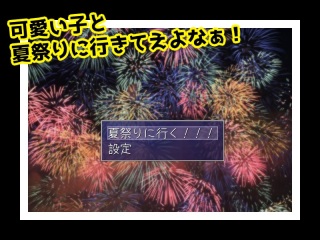
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ノベル | クリムS |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 8分 | 1.05 | 全END |
良かった点
- 上手いシナリオ構成でした
気になった点
- 周回要素がありますが、スキップ等がないので分岐の確認はやや手間です
- なお、かなり短い作品なので大した手間ではありません
レビュー
可愛い子と夏祭りに行きてえよなあ!
可愛い子と夏祭りに行きてえよなあ!は、タイトル通りのノベルゲームです。
タイトルがあまりにも説明を完璧にこなしているため、付け加えるべき情報はそれほど多くはありません。
ゲーム内に存在するルートは3パターンであり、道中の選択によって分岐していきます。選択の種類もストーリー全体の長さもコンパクトなものなので、各ルートの周回は容易となっています。
あるルートを辿ることで色々と理解の裾野が広がるので、ぜひとも全てのルートをご覧ください。
感想
言われてみれば、一言も言ってませんでしたね。叙述トリックというやつです。
そしてちゃんと見直すと、描写がそれを意識したものともとれるようになっていました。浴衣の話とか、着慣れてないのはまあある種当然だけど、それを知った状態で読むと違った味わいがありますね。
文章の上手い方が綺麗にネタに走ったという感じです。
ハッピーエンドについては、どっちに倒れているのか多少気になっています。あくまでも女子として描写されたエヴェレット解釈的な何かのものなのか、本当に友人を恋人にしたんでしょうか。
まあ後者なんだろうと思っています。どっちつかずで疎遠になるあたりも友人っぽいですしね。
しかし、夏祭り、可愛い子で綺麗に被ってしまったかと思っていたら、変化球で被らなくなったのは体験的に良かったです。ウディコンの開催時期を踏まえれば、夏祭りが被るのはさもありなん。
あとは、タイトルがあまりに完成されすぎています。何か紹介文を一言で書こうとしてタイトルしか思いつきませんでした。完璧。
41. ショートファンタジー マージョのマジかるパニカル

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 全方位シューター | ヘビトンボ |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 3分 | 1.10 | 7750 |
良かった点
- タイトルの遷移の仕方がミニゲーム感があって良いです
- 空撃ちがデメリットになり自分の首を絞める良いデザインでした
気になった点
- コンボによるスコア倍率が大きいため、アイテムはほぼおまけに感じていました
- アイテムを取るためにウェーブを遅らせる選択肢が実質無いので、近場にあれば取るというレベルです
レビュー
コンボをつないでスコアを稼ごう
ショートファンタジー マージョのマジかるパニカルは、シューティング然としたスコアアタックのミニゲームです。
ルールはいたってシンプルで、敵に弾を当ててスコアを稼ぎ、被弾してゲームオーバーになるまでのスコアを競うものとなっています。
特徴的なのは、自分が撃った弾がステージの壁で反射することで性質が変わり、その反射した弾に当たると被弾扱いになるということです。すなわち、敵を倒すために撃ったその弾がそのままリスクとして場に残り続けます。
被弾の可能性を極限まで下げるには、同一線上に複数の敵を揃えて撃つ、空撃ちをしないといった弾の節約がカギとなるでしょう。
しかし、ただ生存することを目指しているだけではジリ貧で、いつかは被弾する上にそれほどスコアは伸びません。敵を連続で倒してコンボを繋げない限り、スコアの伸びは緩やかなためです。
コンボを意識して素早く、しかし空撃ちを避けて慎重に弾を撃ち、上手く反射する球から逃れていくアドリブ力が求められるでしょう。
ステージにはアイテムがランダムに配置されるため、これを使って場を有利にするのも肝要です。
短い時間でサクッと遊べる、スコアアタックのミニゲームとして完成された作品です。
ランキング機能もあるので、我こそはと言う方は挑戦してみましょう。
感想
ミニゲーム感のあるミニゲームとして良かったです。ササっと楽しく遊べるタイトル。右からにゅっと出てくるマージョが見られる、タイトルの遷移の仕方なんかも良い雰囲気でした。
もちろん、一ゲームが短いのですぐに遊べるのも良いです。何ならその一ゲームより遊び方を読んでる時間のほうが長かったんじゃないかというレベルでした。スコア倍率についてだけでも読んでおくと良さそうです。
最初のプレイでは生存重視で立ち回っていましたが、それだとスコアが伸びなかったので、次のプレイでコンボ重視に切り替えて遊びました。その時点でランキングに入れた程度には得点が取れたので、恐らく有効な戦略だと思います。現時点ではどうせ抜かれてるとは思いますが。
スコア倍率を効率よく上げるのは大事ですが、アイテムは可能なら取ってみるラッキーなものと捉えたほうが良さそうでした。遠くのアイテムを取るためにウェーブを遅らせるのは、コンボの観点から悪手な印象です。
後は、このミニゲーム然として完成されているゲームシステムの中でも、空撃ちをきっちりデメリットに昇華させているのが好きです。ちゃんとエイムに意味があるゲーム性になっています。加えて、制限時間システムではないものの、実質的な退場も担保しています。
場に出る数を減らすために、射線に敵を揃えるみたいな細かい技の使いどころもあって楽しい仕組みでした。
42. じゃんけんバトラー俺
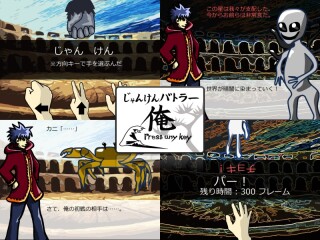
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| じゃんけん | 遊句 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 5分 | 1.00 | 裏END |
良かった点
- ネタの濃度が濃かったです
- 曲が良いです
気になった点
- 特にありません
レビュー
じゃんけんしよう
じゃんけんバトラー俺は、じゃんけんをして進めていくミニゲームです。
プレイヤーがやるべきことはじゃんけんのみであり、アローキーを押して相手に勝つべく手を出すことしかできません。
ただし、じゃんけんと一口に言っても相手によってその様相は変わってきます。立ちふさがる様々な敵を相手取り、じゃんけんで勝利をつかみ取りましょう。
じゃんけんに限定したシンプルなゲーム性と、それに合った勢いで構成された物語の中、疾走感と共に駆け抜けられる作品です。
多様なじゃんけんを潜り抜けて、じゃんけんの勝者になりましょう。
感想
ショート枠の中でも、勢いで最後まで駆け抜けるタイプのミニゲームでした。負かした相手に腕をちぎって渡すカニのような狂気が満ち満ちています。ゴリラもいます。
ミニゲームとして見ると、ほぼただのジャンケンなんですが、全ての戦いで微妙に考えるべきことが変わるようにもなっています。各ポイントに良い曲を配する作りにもなっていて、短いながらも細かいところがちゃんと整備されているミニゲームでした。見た目は完全にネタゲーっぽいのに。
End画面でも、キー入力に応じて掛け声が変わるという小ネタが差しはさまれています。最後まで細かい。
なお、かなり短いのでタイムアタックでもやるかと思って始めたら裏ENDに入ったので、何か間違えたのかもしれません。
二度目のチャレンジでは、宇宙人は要するに最後の瞬間の勝負になるので、ずっとチョキだして最後の瞬間にパーに変えるのが楽ということに気づきはしましたが、手を変えまくって相手も変えまくるのを見る方が楽しいのでそうしていました。
43. オカルトノート 土雲ガクレ編

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ホラー探索ADV | カッパ永久寺 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 3時間 | 1.04 | トゥルーエンド |
良かった点
- 神話を丁寧に取材した上で題材としているためシナリオに深みがあります
- 探索と推理パートが上手く噛み合ったデザインでした
気になった点
- 誘導がだいぶ薄めなので、探索を手厚めにする必要がありました
- マップ自体は広いので大きな問題にはなりません
レビュー
論理的に怪現象に挑む
オカルトノート 土雲ガクレ編は、ホラー要素がある探索アドベンチャーゲームです。
現代の家を舞台とし、古代からの闇で塗り固められた土雲の怪異の調査を行っていくことになります。
ゲームの進行はオーソドックスな探索ものとなっており、クローズドな家の中を探し回ってアイテムなどを見つけては物語を進めていくというものです。
その中で、探索ものとしては定番である謎解きや追いかけっこといったものから、シナリオ進行にかかわる推理パートまで、プレイヤーは様々な要素に挑むことになります。殊に、推理パートではこれまでの情報を整理して、論理的に怪異の正体を導いていくことが求められます。思考を巡らせ、怪異の謎を突き止めていきましょう。
また、このゲームにおける圧巻は何といっても古代史や神話の類に裏打ちされた確固としたシナリオです。バックボーンが綿密であり、それに下支えされた確かな土台の上で組み上げられていく良質な世界観と物語が展開されていきます。
表の筋をコメディ要素と王道的展開でもってエンターテインメントとして完成させつつ、古代から伝わる怪異を現代ナイズして解釈したアレンジをその背景に加えることで、楽しみつつ濃厚な世界を体験するものとなっています。
基礎をオーソドックスな探索アドベンチャーで固めつつ、展開と背景共に優れたシナリオでもって構成された作品です。
エンディングは7種類あり、行動に応じて変化していきます。論理的な推理をもとに、良いエンディングを目指していきましょう。
感想
知識に裏打ちされた物語が個人的に好物なので、古代史や神話の類に対して解釈を交えつつゲーム向けにアレンジして語る、この物語構成は好きです。
日本神話は特に神の名前をあんまり覚えられていない都合上、割とあやふやだったりごっちゃになっているところがあるので、その辺のおぼろげなところを突いてくるのもあって良かったです。あの辺り、無為の神という中空構造があって絶妙に覚えにくいんですよね。
ゲーム性はホラー探索をオーソドックスに作り込んだ印象で、そこにエッセンスとして推理要素や古代神話要素が入っていると感じました。
ホラーは本質的には未知に対する恐怖を主眼に置くことが多いので、そこに対して論理的に立ち向かうというのは面白かったです。ホラーそのものの要素はありつつも、ちゃんと論理的に事件を導こうとしています。
推理パートは論理的なものではあっても論理パートではなくて思い出すパートであり、どちらかというと証拠集めのほうが大事になっています。
この辺りのヒントは薄めなので探索を厚くする必要のあるゲーム性になっており、ちゃんと隅々まで調べないとアイテムが見つからないようになっているなあという印象がありました。ただ、家というか対象マップは狭いので調べつくすのにそんなに時間はかかりません。
推理面では、マップチップの関係ではあるんですが、あの穴が通れるように見えなかったり、首を落とせるように見えなかったりはするものの、その辺は口頭で推測がなされることで推理必須要素から外すことで上手くカバーしています。
しかし、最終的な推理が全部正しいとすると、ヨウカ達がうろちょろしている時間はまだ母親は2階にいたんでしょうか。順序的にはおばあちゃん演技、母親になすりつけようとする、なのでその段階では睡眠薬を盛る理由が無いので。
もっとも、双方後ろ暗いところがあるので、そうなっていても違和感はありませんが。
シナリオの面でも個人的に好きな推理要素を抜きにしても面白く、どんでん返しも熱い展開も用意された至れり尽くせりのものとなっています。
腕の件を見てしまうと、扉が開かないのもまた思い込みの力であり事件を誤解していたという事実も相まって、ここまでの事象がマロンの思い込みの力かもしれないというミスリードも働いていました。ただそうするとおばあちゃん問題が解決しないので、これは筆者のミスリードかもしれません。
悪意という毒は何物をも侵すものだというのはSound of Dropなどでも言及されているところですが、物語展開に対する意識外からの作用として強力だなと感じています。思い込みを打破するのは作劇として優秀なところです。
それにしても、政治的主張はないとの但し書きについては、まあ確かに取り扱っている題材だけに必要そうですね。ほとんどリアリティを付与するための道具みたいな扱いではありますが。
後は怪異の扱い方も割と好きで、怪異もまた現代ナイズされているからLINEのような通信媒体で呪いを伝播させてきます。この辺は、玉藻の前が現代ナイズされてネットワーク越しに悪意をばら撒こうとしている作例があるように、現代においての怪異に向き合っていて個人的に好きなポイントでした。
良く分からない因習村もそれはそれで怖いですが、現実に地続きの所に潜んだ恐怖もまたホラーとしては秀逸ですからね。
入念な取材なり知識なりが裏に垣間見える設定をバックボーンに持ちつつ、シナリオそのものは決して難しくなり過ぎないように設定を上手く使いこなしているのが素晴らしい作品です。
重厚に手をかけて作ったであろう設定を押し付けるのではなく、あくまで背景として運用して目立たせず、シナリオに深みを持たせる付加装置として機能させているというのが個人的な推しポイントになります。押し付けないけど感じ取れる厚さって良いですよね。
44. WOLFALL
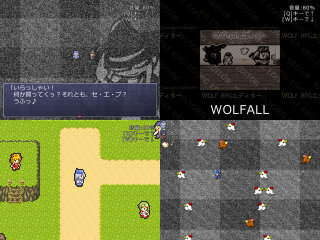
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 弾幕回避 | 秋月ねこ柳 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 30分+1時間 | 1.20 | クリア (☆15) |
良かった点
- 曲に合わせた弾幕が良かったです
- 基本的に考慮すべきことが自機の周りに表示されているので視線が散らずに集中できます
- ある程度の強化要素でクリアをサポートしつつ、やり込み向けの制限もある難度の幅広さがあります
気になった点
- 特にありません
レビュー
もしもウルファールのサンプルゲームが出オチだったら、どうかな
WOLFALLは、弾幕を避けることをメインとしたシューティング要素を備えたゲームです。
BGMに合わせて四方八方から展開される弾幕を相手に、その完奏と共に訪れるステージの終わりまで上手く避けきっていきましょう。
弾幕を上手く回避するためには、上下移動のコントロールがカギになります。
プレイヤーは左右の制動に関して自由である一方、上下には弾の発射の反動でしか動けません。弾には時間経過でしか回復しない残数があるため、闇雲に上下に動いていては弾が枯渇して避けられなくなります。最低限の動きで避けて温存しつつ、いざという時には大きく消耗したとしても大胆に動くことが重要です。
また、弾幕や敵にかすることで弾数の回復速度を速めることもできます。リスクを取ってギリギリで回避していくことも狙っていきましょう。
また、弾幕を発射する一部の敵はその上下に発射する弾で倒すこともできます。厄介な弾を撃つ敵を早めに処理できると有利なので積極的に狙いたいところですが、弾を発射すると上下に移動してしまうため回避の制動に影響が出ることにもなります。上手く当てられそうなところでは狙いつつ、こだわりすぎないのが良いかもしれません。
ただし、一部の敵については倒すことがクリアの制約となっているため、その場合は全力で弾を敵に当てることが目標となります。撃ちすぎて画面外に出てゲームオーバーにならないように注意しましょう。
弾幕は苛烈であり、難易度はそこそこ高いものとなっていますが、上下移動のリソース管理を上手く行い、ステージごとの弾幕の傾向を覚えて避けるパターンを熟知していけばクリアは自ずと見えてきます。
ステージを遊ぶごとに手に入るお金を使った強化要素もあるため、強化していけば少しずつ楽にもなります。加えて、基本は無制限にコンティニューできるため、クリアだけを目指す場合はある程度被弾しても問題ありません。
ただし、ステージクリア時の評価を上げるにはノーミスや強化要素の制限が必要になります。コンティニューを繰り返すことで腕が上がり、被弾が減ってきたら挑戦してみましょう。
曲に合わせて幾何学的に展開される弾幕を、適切な移動で上手く回避していく楽しさを味わえるゲームです。
間隙を縫って被弾を抑えて進行できるようになると、大きな達成感を得られることでしょう。ステージに何度も挑戦し、パターンを体に覚えさせてクリアを目指しましょう。
感想
前作の弾幕は覚えゲーっぽかったんですが、今作は割と反射神経ゲーな印象があります。フェーズごとの対策は覚える必要があるかもしれませんが、割かしアドリブで避けられるのと、パターン化しにくくてその場の判断力のほうが求められることが多かったイメージでした。
もっとも、もう少し高難度を極めようとすると、また違ってくるのかもしれません。
ゲーム性としては、上下移動に強い制約が入り、これを乗りこなすのが難しくて楽しいです。その判断に必要な情報については自機周辺に完備されているので、自機の操作に集中しながら遊べるのも良いところでした。
上下移動で弾を使う必要がある分、それを回収するために敵に近接してグレイズして稼ぐ必要があるデザインも良くて、ギリギリで回避する旨味が出ています。むしろギリギリで回避しないと、弾が枯渇して怪しくなる。
画面を覆いつくすような弾幕の時だけ残弾数を無視して全力で回避に徹し、このために残していた弾の数をフル活用して乗り切っていくのが楽しかったです。
また、曲に合わせた弾幕も美しく、適当にばらまいている敵機がそんなにいません。加えて自機狙いの弾も巧妙に混ぜられているので、そこそこ難しく感じます。この回避だけでも割と難易度は高めに感じますが、それに加えてひたすら避ける以外の攻略法があることで、より複雑で高い難易度を有しています。そして、そこが面白いポイントです。
特にボス戦においてはそのデザインが顕著で、敵機の攻撃タイプの違いもあって常に新鮮に挑めました。集大成のようなオマケは一見の価値ありです。
難易度の面で見ると無限にコンティニューできますし、☆3を目指さないならこちらを強化して挑むという択も残されているあたり、かなり優しいなという印象です。同作者さんのウディコン作品の中では一番クリアしやすいんじゃなかろうか。
あと個人的に好きなのは、最高評価を目指す場合についても全てを縛るのでなく、難度の中でのやりくりが必要な程度にとどめているところです。せっかくの強化システムをちゃんと活かしつつ、プレイスタイルに沿って攻略に挑めます。
筆者は弾幕シューティングが壊滅的なまでに苦手ではありますが、それでもクリアできたことから見るに、かなり楽しみやすいゲームになっているなあという印象です。弾シュー、Hellsinker.ぶりのクリアかもしれない。
無限のコンティニューがあるのはもちろん、強化の組み方で上手く攻略できるのが嬉しいところです。隠しステージでさえも、被弾判定減少を捨てて火力特化のビルドにして早期決戦を挑めば意外と何とかなります。
筆者は基本的には体力上昇と被弾減少に振り、とにかく回避を徹底することで全ステージノーコンでクリアしています。ボス面によっては弾丸の火力が欲しいこともありますが、基本的には回避が強いです。弾数は200程度あれば大体なんとかなります。弾幕が激しい分、グレイズである程度稼げるので。
しかし、エディ、上に飛ばすで無駄な既視感を覚えましたが、解決策はだいぶ異なっていたので勘違いのデジャブでした。
物語の中では、FALLをもじったのだろうと最初に思わせてからのALLもじりが上手く、個人的に感動を覚えたポイントです。ちゃんと最後のALLであるところのタイガも登場させているあたりも良かったです。
45. 異界門事変

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| RPG | パンツ14代目 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 3時間 | 1.02 | クリア |
良かった点
- 癖の強いメンバーが良かったです
- アイテム図鑑にフレーバーがあるなど細かい作り込みがあります
気になった点
- 武器の合成が装飾を除けばグレードアップにほぼ限定されるので、横の広がりがあまりありませんでした
- グレードアップ目指して自動探索を回す作業的なムーブが多かった印象です
レビュー
武器を強くしてダンジョンに挑め
異界門事変は、レベルアップや武器の獲得でステータスを上げて敵を倒していくハクスラ要素のあるRPGです。
ダンジョンのような探索要素が一切排されているため、純粋に戦闘だけを楽しむことができます。
戦闘は各階層に挑む形式で行われ、階層内ではウェーブ形式で進行していきます。各ウェーブの戦闘を全て乗り切れば、その階層はクリアとなります。
その戦闘に勝利するためには、スキルと装備が重要となってきます。スキルはスキルポイント、装備は素材がそれぞれ必要であり、これらは戦闘で手に入るものです。
このシステムにより、強い敵に挑むために戦闘を繰り返してパーティーを強化し、そしてさらに強い敵に挑むためにまた戦闘に挑むというループが構成されています。戦闘の円環に身を投げていきましょう。
なお、一度クリアした階層は自動で探索することもできるため、何度も同じ相手と戦わなくても成長は可能です。自動探索を行うことで経験値、スキルポイント、素材を集めていき、そこで得た強化をもって上位の敵に挑むこともできます。レベリングの時間を節約したい方は使ってみましょう。
もちろん自動探索を使わなくても構いません。その場合は仲間との信頼度が上がっていき、信頼度が高ければイベントを見ることができます。イベント目当てに手動で戦っていくのも一興です。
ハクスラ的な戦闘がメインでありながら、自動探索の導入により稼ぎとしての戦闘要素をばっさりカットすることでもできる独特なゲームデザインの作品となっています。
効率よく自動探索で階層を進んでいくも良し、自力で稼いで信頼度を上げつつ進んでいくも良し、やりたい進め方で戦っていきましょう。
感想
キャラクターの癖が強くて良いゲームです。ハクスラ要素はありますが、戦闘バランスは割と大味なところがあるので、強い武器を回していれば戦える感じになっています。
一度クリアした階層は自動探索という仕組みにより稼ぎが実質不要であり、ひたすら自動探索して回していくことで稼いでいけるため、難易度もそれほど高くはありません。勝てなければ、レベルを上げて装備を整えるのが丸いです。
戦闘バランスについてもう少し触れると、10階層くらいまではスキル連打で帳尻が合い、それ以降の雑魚もある程度装備を回していればそこまで苦労しないバランスです。雑魚で強いのはほぼドラゴンくらいで、それ以外はボスに注視していれば十分となっています。
また、基本的に稼ぎが自動化されているためステータス不安はそんなになく、敵側の崩し択がほぼ被虐に固定されます。もしくは連打で削ってくる方向性。
個人的には50Fより49Fの被虐じゃんけんのほうがしんどかったんですが、ここは無理して初期メンバーで突破した弊害かもしれません。控えメンバーに対応策があったかも。
この被虐を始め、状態異常は相手が使う分にはそこそこ強力ですが、こちらで使う分にはあまり信用が置けませんでした。ドラゴンを睡眠にさせたのに普通に行動してきたり、 封印しても普通に技っぽい攻撃を撃ってきます。道具も妙な動作をするなど、微妙に信用が置けないところがありました。
ハクスラの要素については装備がメインで、基本的に素材を集めて合成するという筋になっています。
ただ、装飾品を除けばそれぞれの性能差が大きく、同程度の性能差にそこまでバリエーションが無いので、基本グレードアップが丸い選択になっています。装備の幅として見ると割と狭く、上位装備に挿げ替え続けることになりやすいです。この辺は微妙にハクスラっぽくない印象です。
そも合成メインかつ素材アイテムのバリエーションがそれほどなく、結果的に武器自体のバリエーションが少ないというのもあるので、いっそのこと装備枠を削って武器と防具と装飾品だけとして、同程度の性能間で選択肢が増えていた方が個人的にはハクスラっぽい気がします。
こちらはこちらで、無駄なことに悩まずに回転率を上げられるメリットはあるんですが。
もう一つのハクスラ要素としてはスキルがあって、色々習得できますし、ポイントを振ってレベルを上げて性能を引き上げることもできます。
特に序盤はスキルの力が目に見えて強いので、うまく扱えると戦闘力を引き上げられて楽しいです。
ちなみに、筆者の遊んだバージョンだとスキルレベルを上げるのに100回決定キーを押すことになっていたので、一気に上げる手段が欲しくなったのですが、こちらはアップデートで追加されたみたいです。神機能。
これらのハクスラで必要な素材なりは、自動探索によりクリア済み階層から楽に拾ってくることができます。
この機能はものすごく助かる一方で、100回も回るようになると、通常時の戦闘で手に入る経験値やスキルポイントが大したことないように見えてしまうというのは気になりました。苦労したほうが見返りが少ないような印象を受けます。
特に序盤はかなりバランスブレイカーめいているので、せめてキャップはあっても良いかもしれません。
また、筆者は初期パーティーで攻略していましたが、これは控えメンバーに経験値が入らず、自動探索と(当時は)スキルポイント連打によるそれぞれの連打の繰り返しをあんまりやりたくなかったからになります。
その結果、イベントもほとんど見ることができていないので、ここはやや気がかりになっています。イベントのハードルが割と高いので、イベントを見たいというモチベーションがあんまり上がらなかったというのがあります。
初期メンバーを上げるだけでもイベントが見れて、それを基点にモチベーションが保てれば見ていたかもしれません。
46. 救済少年の終末

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 探索ADV | すたーあいす* |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 1時間 | 1.04 | 全END |
良かった点
- 予定表とワープによってかなり平易に行動ができました
- 時間経過で各々の行動が変容していくのが面白かったです
- ストーリーや世界観にマッチしたグラフィックでした
気になった点
- アシストが強いので初手でトゥルーに到達しやすくなっています
- 全END見たいプレイヤーが最後に回収するのがBADになりやすいので若干後味が悪くなるかもしれません
- この辺りは遊びやすさとのトレードオフな気もしていています
レビュー
滅亡までの数時間
救済少年の終末は、キャラクターに関わることで運命が分岐していく探索アドベンチャーです。
地球最後の10時間の中で、様々な行動を取っていくことになります。
この10時間の中では、プレイヤーはもちろんのこと、各キャラクターもまた時間に沿って様々な場所に移動して最後の時を過ごしています。
その中で各々の行動に干渉していくには、メニューから見ることのできる予定表が便利です。各キャラクターの時間ごとの場所が全て網羅されているため、予定表と突き合わせながら行動を決めていくことができます。
時間と場所と、そこにいるキャラクターを確認し、積極的に関わりに行きましょう。
各々のキャラクターとの関係性を進展させるためには、特定の持ち物を渡さなくてはいけない場合もあります。持ち物の獲得のためには、マップを探索したり、別のキャラクターと話したりといった行動が必須となります。
いろんな場所を訪れ、いろんな人と会話して、それぞれのキャラクターとの関係性を深めていきましょう。
それぞれが個別で過ごすシステムにより、複数のキャラクターが並列に別軸で行動するため、ともすれば複雑に感じられるかもしれません。しかし、予定表によるスケジュールの網羅やワープによる移動の短縮など、あらゆる面でユーザーフレンドリーな設計になっているため、プレイ感としては複雑さを感じにくいデザインとなっています。
快適なゲームデザインの中で色々と試してみて、それぞれの終末を見てみましょう。
感想
凄く遊びやすいADVです。各キャラクターがそれぞれの時間軸で別の行動をするという、結構複雑なシステムの中でエンディングの分岐に挑むわけですが、そうとは思えないほどすんなりと進めることができるように設計されています。
この遊びやすさを担保しているのがタイムスケジュールで、いつでもそれぞれの行動と場所を見られる上、それ以降の行動も知ることができるようになっています。このため、何度も周回してそれぞれの行動を把握するというような工程なしに、エンディングのための最適なルートをあらかじめ考えることができました。
とはいえすべてのことが分かっているわけではなく、お金の管理だとかアイテムの管理などはある程度伏せられていて、スケジュール通りやれば必ず上手くいくということもありません。この辺のバランス感覚が良いですね。
加えてワープ機能もあり、移動という手間も徹底的に省いています。遊びやすさにかなり振っているという印象がありました。
一方で、このワープと予定表のシステムもあり、良かれあしかれ、かなりADVゲームであるという印象が強いものとなっています。システマティックに振っている感じ。
ただ、仮にタイムスケジュール無しで各人の動きを見ようとするとMoonっぽくなりそうで、それはそれで風情はあると思いますが敷居は上がりそうです。
また、初手で全てが分かっているため、最初からトゥルーエンドを目指すのもかなり楽で、実際に筆者は初見で辿り着いています。
このため、残りのBADを見に行こうと思うと、UndertaleでGルート行くのと同じような気持ちを抱えることになりました。じゃあBADを見るなという話ではあるんですが、ここはもう性根がそうなっているのでご容赦願いたいです。
ADVを作ろうとしてプレイヤー体験の導線を引こうとすると、上述のことからあえて不便を与える方向に行きたくなると思うんですが、そこを抑えて徹頭徹尾プレイヤー利益の目線でゲームを構成したのだろうなと感じています。
これは明確に良いところであり、利便性に振っているので結果的に周回も楽ですし、Fキーによる時間経過まで完備されているのは徹底しています。プレイヤーが通る道をこじ開けるのではなくて、通りやすい道を徹底的に整備してあるようなイメージ。
全体的には、ゲーム性よりも遊びやすさを優先して、より物語に没入できるように構築されているような印象を受けました。
シナリオ面で個人的に好きな所を挙げると、主人公が関わる行動は基本的に良い方向にしか向かないというのがあります。
このゲームのBADは救わなかった結果として訪れるもので、救おうとする行動を起こせばおおよそGOODに向くようになっています。これはテーマというか、主人公の善意に対してゲーム側が応えているところなのかなと感じていました。
彼は皆を少しでも救いたいと思っているはずなので、それが反転して呪いになるようなことはプレイヤーの気持ち的にも避けてほしいところがあります。
その分、とりあえず行動しとけば良いENDに行きやすいという性質があることにはありますが、ここもトレードオフでしょう。
後は細かい点だと、大体のアイテムを対象外に渡しても何らかのリアクションが返ってくるのは作り込みが細かいなと感じました。少なくとも観測範囲では、なんだそれ、みたいな定型文じゃないのが良いです。
なお、最後まで通しての疑問として、アルセだけはなんで残ってるのか良く分かっていませんでした。
彼もまた生きづらさを抱えてはいたのかもしれませんが、少なくとも表層的にはあまり動機があるように見えません。思考のパターンが筆者の頭になくて、うまく解釈できていないのかもしれません。
47. 未来よ心のままに

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 戦闘メインRPG | ケイ素 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 2時間 | 1.09 | 全Ex撃破 |
良かった点
- プレイヤー側が場をコントロールできる良い戦闘システムでした
- シナリオは良い人間賛歌でした
気になった点
- アイテムの性能が高く、かなりプレイヤー有利なバランスに感じました
- 1ターンの使用アイテム数には上限があっても良かったかもしれません
レビュー
場をコントロールして敵を倒せ
未来よ心のままに は、陣取りのような戦闘システムが特徴的な、戦闘をメインとしたRPGです。
敵を倒すごとにシナリオが進行し、ボスの撃破をもって一つの章が完結していく形式となっています。
| 戦闘画面 |
|---|
立ちはだかる敵を上手く撃破するには、独特な戦闘システムを利用しつくす必要があります。
プレイヤーが行うことになる基本的な操作は、中央にある3カ所のスロットの中から、SPを消費して1マスチャージするというものです。このチャージを繰り返し、スロットの5マスが埋まるとスキルが発生します。重要なのは、敵もまた同じスロットから選んでチャージしてくるということです。
互いにスロットを選んでチャージし、双方のチャージを合算して5マス埋まるとそれぞれのスキルが起動するという流れになります。
そうして発動するスキルの種別は、埋めたマスの数に依存します。概ね多くのマスを埋めるほど強いスキルが発動するため、より多くのマスを埋められるようにチャージしたり、反対に相手の大技を防ぐために邪魔する意味でチャージしたり、ということも可能です。
相手のチャージ段階ごとのスキルは常時確認できるため、受けても良い技とダメな技を確認しつつ、適切にチャージを割り振っていきましょう。例えば、こちらの物理防御が高く、特殊防御が低いのであれば、物理攻撃を積極的に受けるように立ち回ると被弾を抑えられます。
そうして敵を撃破していき、シナリオを進めていくことで素材値が手に入ります。この素材値を使うことで、いつでもステータスの編集やパッシブスキルの獲得、アイテムの入手などができます。加えて、プレイヤーが使えるスキルもまた、いつでも変更可能となっています。
特にボスなどの強敵に挑む際は、相手に合わせたステータスやスキルを選び、戦略的に相手を封殺することを目指していきましょう。
操作は陣取りだけでありながら高度な戦略性を持つ戦闘と、合間に挟まれるコンパクトながら要点を得たシナリオが両輪となって楽しめる作品です。
敵の性質やチャージ段階ごとのスキルを鑑みて戦略を立てて戦うことができれば、相手の攻撃を誘導し、こちらの通したい攻撃だけを通すことも可能です。戦闘をコントロールして、強敵を撃破していきましょう。
感想
戦闘システムが面白い作品です。プレイヤー主体で駆け引きを楽しみつつ、適度な戦略性をもってバトルを進行できます。
バランスとしてはかなりプレイヤー優位なので、上手く戦闘を進めることができれば強敵相手でも一方的な試合展開を演出できるのが楽しいところです。
相手も自分も同じ盤面でマナを取り合うというゲームシステムが秀逸で、こちらの行動指針を考えるのに加え、相手の妨害まで一手で行える面白いシステムとして完成されています。
これは、相手の各コストの技を見て、どのコストの技に警戒し、どのコストの技なら打たせても良いかを考え、上手く盤面を制御して勝利できた時の達成感が強いシステムとなっていました。相手のしたいことを潰し、こちらのやりたいことを通すのは非常に楽しいですね。
一方で、エンジェルグレイスで回復しなかったり、精度不良でもなく命中100回避0でも稀に外したり、スキル面で微妙に不安定なところはありますが、把握できれば対処はできます。
筆者の戦略は相手に意味のないバフデバフを撃たせて、超攻撃力の物理で押し切るスタイルでした。
少なくとも3章の強敵までは十分通じますし、4章で物理押しがちょっと封じられはしますが、アレンジを加えていけば最後まで押し切れるポテンシャルを持っています。体力を削り切ったところでバーサク+エーテルが強いですね。TP取れてるなら突撃もアリ。
裏ボスもこのスタイルで突破できていて、1 ,2を起動させることなく上手く盤面をコントロールすることで勝利をもぎ取りました。物理主体なのもあり、本当は5でハメたかったんですが、割と賢いのでちゃんと4で止めてきます。そうは問屋が卸さない。
こちらが場を制御しやすいこともあり、上述の通り戦闘バランスは明らかにプレイヤー優位な傾向を持っている上、特にアイテムを使うとより優位な行動を取れます。ずっと俺のターンができるので。
これまでの作品が相手の攻撃に対応するプレイングが必要なバランスだったのに対し、この作品では相手の攻撃を管理するようなプレイングができるようなシステムになっていました。ここを理解し、相手の行動をコントロールできれば大分有利に働きます。
難易度がどうしても上がらない仕組みではあると思いますが、個人的にはこちらの方が戦闘を上手く制御できている感覚があって楽しかったです。
また、シナリオも良く、機械目線による人間賛歌の群像劇に近い構成となっており個人的に好きでした。
構成としては掌編を連ねつつストーリーを進めるもので、それぞれの掌編の起承転結がきっちりついているので読んでいて安心感があります。
そして強く思うこととしては、やっぱり独特の美学を貫く悪役っていいなということです。共闘する元悪役も出てくるのでよりどりみどりという感じです。良い悪役のバーゲンセール。
返す返す、やることはシンプルな配置だけで、考慮事項はこちらの通す択と相手に通させる択という重なりを持っているこの戦闘設計は非常に秀逸なものです。テンポ良く戦闘を進められるにもかかわらず、非常に戦略的に戦ったような感覚を覚えることができます。
攻略して上手く型にはめる楽しさが味わえる作品でした。
48. アリアとウィヴィと魔女の塔

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| WWA | バル |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 8時間 | 1.07 | クリア |
良かった点
- WWAをたっぷり遊べるボリュームでした
- バフを盛ればある程度クリアが簡単になりつつも、歯応えのある難度でした
気になった点
- ステージの数に比してギミックや敵のバリエーションが少なく感じました
- 会話スキップについて、会話を一度も見ていなければスキップ出来ないほうが良いのではないかと感じました
レビュー
ボリュームたっぷりのWWA
アリアとウィヴィと魔女の塔は、いくつかのステージで構成されたWWA風のゲームです。
事前に分かる情報をもとに数字の足し引きを管理していく、パズル的な戦闘を楽しむことができます。
攻略することになるステージに配されるのは、基本的に敵とアイテムの二つであり、敵に接触した場合は自動で戦闘が行われ、アイテムの場合は取得することになります。
自動で行われる戦闘は、相手のHPを削り切れるダメージを与えるまで敵の攻撃を受け続けるというものです。すなわち、1発で倒せるならノーダメージですが、10発必要なら9回も攻撃を受けてしまうことになります。
ダメージは攻撃力から防御力を引いた簡単な値で算出されるため、被害を抑えるには攻撃力を上げて必要回数を減らしたり、防御力を上げて被ダメージを軽減させる必要があるでしょう。
そういった戦闘を有利に進めるステータスを手に入れるには、アイテムを拾って強化する必要があります。ただし、アイテムの配置は一筋縄で取得できるものではありません。敵が立ちはだかっていたり、鍵のアイテムを必要とする扉の先にあったりと、障害があるのが常となっています。
どのルートを攻めてアイテムを取り、被害を抑えつつ成長していくかなどを考えていくことが肝心です。将来のために大きめの被害を被ってでも無理やりアイテムを取りに行くか、あるいは小さい被害をコンスタントに受けることを選ぶか、都度都度決断していきましょう。
現在のステータスを鑑みつつ、敵やアイテムの配置とステージの形状からルートを定めていく長期的な視野を必要とするゲームとなっています。
その一方で、ステージ制を採用しているため、特に序盤においては一つ一つのボリュームは抑えめです。まずは少しずつルート決めの思考に慣れていき、中長期的な視座や局所解を詰める能力を養っていきましょう。
お助け要素もあるので初心者にもクリアへの道は開かれており、他方で上級者向けにはダイヤスコアという目標点もあります。自分の腕前に合った挑戦をしていきましょう。
感想
想像の3倍くらいボリュームのあるWWAでした。いっぱい遊べる。
全20ステージある上、それぞれダイヤスコアも設定されているので、全てをクリアしきろうと思ったらさらなる時間が必要になると思います。筆者はダイヤスコアどころか、お助け機能の利用まで手を伸ばしてギリギリのクリアとなりました。
目標としてはダイヤスコアがあるものの、明確にクリアすることで先に進んでいくデザインなのもあってか、クリアするだけでも歯応えのある難易度となっています。なんとなく良さそうな交換を雑にしているだけだとクリアはおぼつきません。
筆者は最初の方はショップを使ってお助けなしで進めていましたが、中盤くらいからお助け機能も使い倒す方向に切り替えました。そして、それでもそこそこ難しいなと感じていました。この局所最適解を積み上げていく思考が苦手なだけかもしれません。
また、WWAが各ステージに分離されたことにより、一つ一つのプレイ時間は短めになっています。
これによりWWAに必要な長期的な視野の重要性をある程度弱めることができていて、やり直しがしやすくなっていました。これが無ければ、最初の方のステージでお助けを使わずにクリアできていなかったかもしれません。
とはいえ近視眼的思考だとすぐに詰まるラインは確保されており、ステージとしてのボリュームはパズルの意味を持つレベルに収まっています。このあたりの塩梅が良い。
ステージに対して特殊なギミックもいくつか用意されており、各ステージで毎回同じことをやるというのはあまりありません。
ただ、そのバリエーション自体はそれほど広くなく、敵もパターンのガワ変えがメインで専用ギミックのようなものはありませんでした。錆びや毒という駆け引きは存在しますが、プレイヤーサイドに対し明確にマイナスな要素の拡張なので、障害の一要素としての感覚に留まっています。
オーソドックスな設計が続くという面において、WWAを好んでいる人にはかなり良い作品なのかなと思っています。
WWAとしての遊び心地は良く、各種レスポンスも軽快でルートを考えて楽しむことに集中できる作りになっています。特殊要素の解放も段階的なので、いきなり多くを覚える必要が無いのも嬉しいところです。
オープンオーブの消費コストだけスキル選択時に欲しい気持ちもありましたが、使えばわかるのでそれほど重要でもありません。
また、個人的にはクリア後にタイトル画面を見返すとその意味というか解釈が変わるのが割と好きです。確かに二人とも大分落ち着いていますね。
49. マスコット

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ホラー | The倶楽部ズ |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 10分 | 1.0相当 | クリア |
良かった点
- 怪奇的な良さのあるマスコットでした
気になった点
- 出口を示すマップチップがあまり自明ではありませんでした
- アイテムがあるエリアの解像度差が気になりました
レビュー
追いかけっこ
マスコットは、追いかけっこをメインとしたホラーです。
ノベルパートと追いかけっこをするパートに分かれており、いずれも短い時間でさっと遊ぶことができます。
上手く逃げ切って、エンディングへと辿り着きましょう。
感想
ホラーというかオーソドックスな逃げるゲームです。
ホラーものと逃げるものというのは、フリーゲーム界隈だと割とニアリーイコールなところはあります。
逃げるシーンにおいては出口だけ分かりにくく、初見では見つからないうちに普通に追いつかれました。恐らく壁の上部を示しているマップチップだと思うので、何かしら別のチップを使ったほうが良い気はします。
また、ウディタの追尾は微妙に弱いところがあるので、入り組んだところだと割と簡単に引っかけることができます。それほど致命ではありませんが、こだわるならA*なりを使うのも良いのかもしれません。そこまでやるかという話はあります。
なお、選択肢は一応全部選んでみましたが、それほど結末の過程に変化はありませんでした。どれかは撒けるかなと思っていましたが、そんなに甘い相手じゃなかったみたいです。
しかしこのマスコット、いったい何だったんでしょうか。マスコットと言うからには、何かしら幸運をもたらすものだと思うのですが。
50. 「財宝竜と四騎士」The sunset and breaking dawn King

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| RPG | ZRA157 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 1時間 | 1.06a | クリア |
良かった点
- シナリオのスケールが大きいです
- 任意のスキルをカスタマイズできる仕組みは面白かったです
- いざという時はアイテムとして使用できるという点についても、ボス戦などの良い場面で役立ちました
気になった点
- 背景が不透明な段階から4人で話し始めるので、誰が喋っているか分かりにくく感じました
- 特に個々人の属する組織や関係性を飲み込むのに時間がかかりました
レビュー
壮大な叙事詩の一節
「財宝竜と四騎士」The sunset and breaking dawn King は、シナリオのスケールが大きいRPGです。
ゲームボリュームそのものは短編ですが、背景に長大な物語を感じさせる作品となっています。
ゲームのシステムはオーソドックスなRPGであり、シンボルエンカウントで出現する敵を倒しながらステージを進み、ボスに挑む構成となっています。攻撃性能の高さに寄った戦闘バランスとなっているため、テンポ良く戦闘をこなしていけるでしょう。
殊にボスは攻撃が苛烈なため、回復を主体にして粘るプレイングではジリ貧で負けになりかねません。攻撃できるときは積極的に攻撃を加えていき、押し切っていくことが大事です。
その苛烈な戦闘を戦い抜くために重要となるスキルは、装備によってカスタマイズできます。いくつかのスキルから選んで装備し、強敵にも対応できるビルドを模索していきましょう。
さらに、いざという時には装備品としてのスキルをアイテムとして使用することもできます。アイテムとして使うとそのスキルを消費してしまいますが、ノーコストで発動できるため場面によっては非常に強力な武器となり得ます。SPが枯渇した時の回復手段であったり、最後のダメ押しの一撃であったり、とっておきの切り札として運用可能な手段です。苦戦するボスには積極的に活用していきましょう。
そうしてスキルを駆使してボス戦を乗り越えていくと、徐々にキャラクターや世界の背景が明かされていき、壮大な世界の一端に触れることができます。
強力なボスを打倒していき、叙事詩のその一節の完遂を目指していきましょう。
感想
大叙事詩の一節みたいなスケール感のゲームです。全体の流れがダイジェストで一気に紹介されたときは面食らいました。
ハイファンタジーというか、かなりシナリオ面でも背景でも壮大な話なので、固有名詞がだいぶ多く出てきます。
世界観の壮大さだったり、単純に中二心的な面でも好きな所ではあるんですが、そのぶん話を追うのがかなり辛めではありました。特に序盤が顕著で、知らない単語を叩きつけられる上に、知らない人たちのそこそこ長い会話を聞かされることになります。
紹介パートが個別で行われるのはテンポ的に良い感じがするので、序盤ももっとスムーズな方が取っかかりやすいかもしれません。
特に個々の関係性が不透明な点が理解の妨げになっているところはあるので、せめて誰が喋ってるのかわかった方が理解の助けになりそうでした。
戦闘面は火力が高めの調整で、非常にテンポが良いです。雑魚戦でもボス戦でも、さっくりやられるか、さっくり倒せるかのいずれかになります。
とはいえ戦闘が平易というわけではなく、さっさと倒さないとヒールレインを繰り返して回復したところでジリ貧になって負けるというバランスのため緊張感があって楽しいです。とにかく火力を用意して叩きつけるのが大事。
筆者の体験としては毒がかなり厄介で、相手につける分には火力のインフレもあってそうでもないんですが、相手から付けられると大分しんどいです。多分、デスペルオールよりエスナオールの方が優先は高いと思います。
また、スキルについて、アイテムとして消費するとSP消費なしで攻撃できるシステムも面白いです。設計上ボスくらいにしか切れませんが、使いどころを見極めれば戦況をリセットできるくらいの力はあります。
そのシステムの都合上、SP消費の大きい行動に使いたいところですが、そういう大技はあんまり拾えないジレンマはありました。
筆者は最終戦ギリギリの戦闘において、ヒールレインを攻撃魔法使いに使わせることで窮地を脱するなどしていたので、体験としてかなり良いものに感じています。とっておきという気持ち。
シナリオが一部分の話に留まる点や、短編の都合上説明がない部分もあるので、プレイ後の疑問は尽きません。
うろついているドラゴンと世界を揺るがすレベルのドラゴンは何が違うのか。地母龍の復活は普通に気になるんですがどうしたのか。個人的には、これまでの各龍の力を使って竜と人が手を取り合って原初に打ち勝つんじゃなかろうかと思っています。
51. Know Your Enemy, Know Yourself

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ローグライク | morimori |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 2時間 | 1.1.2 | クリア |
良かった点
- 未知を解読して上手く扱っていくローグライクの楽しさが抽象して表現されています
- 難易度の向上がちょうどよく、前半に稼ぎ、終盤は原則逃げる戦略の変遷が楽しめます
- 任意の地点にメモを残せる機能が便利でした
気になった点
- 仲間を雇うタイミングが良く分かりませんでした
- 知識に金を使わなくなる終盤に雇用しましたが、仲間がいても辛いのでほぼ壁として運用していました
- 知識比で仲間の雇用コストが高いような印象を受けています
レビュー
知識は力
Know Your Enemy, Know Yourself は、未知を識別することをもって攻略とするローグライクです。
魔法、アイテム、敵の全てがほとんど不明な状態から開始し、その全ての知識を得ることでクリアとなります。
基本的には、マップを探索して村を見つけ、そこで本を購入することで知識が得られます。売られている本にはアイテム、魔法、敵のいずれかの知識が書かれており、欲しい情報を選択して購入することができます。特にアイテムの知識は重要であり、この情報がなければアイテムの運用もままならないため、積極的に購入することをお勧めします。
また、本を購入するための資金源は敵のドロップ頼りであり、お金を稼ぐために敵と戦う必要もあります。マップ上で接触することでダメージのやり取りが発生するほか、魔法やアイテムで遠距離から攻撃することも可能です。上手く立ち回って安全に敵を処理していきましょう。
ただし、漫然と敵を倒しながら彷徨って知識を得ているだけではクリアはおぼつきません。時間の経過とともに敵の強さが指数的に増大していくためです。最初の内は複数の敵に囲まれていても余裕で処理できますが、長い時間プレイしていると一対一でも負けかねない状態になってきます。
そして、この困難な状況を打開するのに必要なものもまた知識です。アイテムや魔法の知識を十分集めることができれば、それを活用して強くなった敵とも渡り合えます。できるだけ素早く知識を集めて強敵に備えつつ、敵が強力になってくる終盤をいかに乗り越えるかが肝心となるでしょう。
知識を効率よく収集していくには、効率の良いマップの巡回がカギとなります。マップには一日に一回知識や魔法が得られるクリスタルが点在しているため、この場所と村を基点にルートを決めていくのが良いでしょう。
序盤の内に歩き回ってマップを把握し、プレイの度に自動生成されるランダムな地形から上手く知識を集められるルートを構築していきましょう。
知識がクリア条件であり、同時に知識がクリアの助けともなるゲームです。目的が手段であり、また手段が目的でもあります。同時に、そうして知識の識別という準備をこなし、最後の逃げ切りに備えるというローグライク的体験が得られる作品でもあります。
知識を蓄えてクリアを目指し、その知識を持って難局を打破していきましょう。
感想
知識が力であり、知識がクリア条件という首尾一貫としたローグライクでした。
かなり独特なシステムをしていますが、目的と手段が一致しているので理解を深めながら楽しく遊びやすい作品になっています。
特に、ルートを抑え、知識を集め、魔法を収集して可能な限り達成度を上げていく序盤から中盤と、手持ちのリソースを使いつくして残りの達成度を損害少なく埋めていく終盤のグラデーション的な体験はまごうことなくローグライク的で楽しめます。
このあたりの難易度調整はかなりちょうど良く、1日目の余裕がある状況、2日目あたりからの雲行き、3日目以降の敵の強さはかなり綺麗にデザインされています。初回プレイでは3日目に落とされました。
難易度が高いか低いかで問われれば高い方と答える部類ではありますが、ローグライクとして見ればむしろ絶妙と答えるような歯ごたえに仕上がっています。
筆者がクリアした時は、魔法として遠距離魔法とワープを確保できたのでだいぶ安定しました。遠距離魔法はアイテムとの組み合わせで回復までやれるので、かなり当たりだと思います。ワープも最終盤の逃げながら集めていくフェーズなどで活躍しました。
こうした有用なものを集めるために、とにかく序盤は情報と魔法の収集に血道を上げるのが肝要で、それが後半の備えになる上にクリア条件にも重なっているというのが、このシステムの秀逸なところです。クリアを目指していれば、勝手に後半の準備がある程度整うことになります。
そうして準備をして3日目になり、Gが強いなあと思いながら逃げ惑ったり、通路で一体ずつ処理したり、ワープで誤魔化していったりするのはだいぶ楽しかったです。
全ての機能が恐らくランダムに設定されているのも面白いところで、攻略の方向性はプレイする度に変化します。筆者の例で言うと、最初のプレイでは回復が多かったので耐久でしのいでいましたが、二回目のプレイでは遠距離を引いたので先に始末する方向性で戦っていました。
一方で、完全にランダムなこともあり、使ったものの識別は困難を極めます。条件も複雑なので、使用によって識別するのはあまり得策ではありません。漢識別もしにくい。確定アイテム以外は破棄しながら進めていくのが行動としては丸そうでした。この辺は不思議のダンジョン系とは異なるところです。
また、仲間というシステムがあり、コストを高めに払うことで増やせるのですが、これの使いどころは割と難しかったです。
店買いの知識の値段、周囲の敵のバランスからして、多分90%台くらいから仲間を連れていくバランスなのかなと推測しています。そもそも、店で知識を変えるならそっちに振ったほうが、クリアの面でも収集の面でも有利です。店買いで余るくらいから検討段階に入ります。
しかし終盤は逃げ切り態勢に入っているので、そこで仲間が増えてもやることはあまり多くありません。ほとんど囮くらいにしか使えない印象でした。上手い使い方が分からない。
なお、各色のパラメータとその関係とか、説明書にはあったけど一読で理解できてなかった要素はいったん無視して遊んでみるのが良さそうでした。全部処理するのは難しい情報量なので、困ったりゲームオーバーになったりしたときにその原因として覚えたほうが身に沁みます。
そも相手の追尾力が高く、逃げる選択肢を取りにくいゲームなので、パラメータがわかってるからといっても有効な行動がとれるとは限りません。ピンポイントで必要な情報なので、その時に覚えるくらいがちょうどいいと思います。
後はメモ機能が地味に便利で、主に終盤に役立ちます。どうしても地形が似通っていて覚えておくのはほぼ無理になってしまうため、そういう時にメモが置いてあると良いです。ソースコードにコメントを付けておくと、一週間後の自分が助かるアレです。
終盤、逃げながら情報を集めている最中にあった、こちらは行き止まりのメモは非常に助かりました。ちゃんとメモを残しておきましょう。
52. 一画面で成し遂げる地獄再興

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| クリッカー | semicolon |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 30分 | 1.0.2 | カンスト |
良かった点
- クリッカーらしくどんどんと桁が上がる楽しさがあります
- 地獄石の活用で一つギアを上げられるのが楽しいです
気になった点
- メニュー操作がややわかりにくかったです
- 画面だけでは操作方法が分からず、説明書を読んでも左右のメニュー切り替えをしばらく理解できていませんでした
- クリッカー系の印象でマウス操作をしたくなったのもあります
レビュー
連打で恐怖を量産しよう
一画面で成し遂げる地獄再興は、キーの連打と施設とリソースをもってギャーを集めていくクリッカー風のゲームです。
始めは連打でリソースを稼ぎ、そのリソースをもってさらなるリソースを稼いでいく拡大再生産が楽しめる作品となっています。
始めに連打をしていくことで鬼と地獄石が生産されていき、その鬼はギャーを生産し、ギャーは鬼などの生産強化へと回せます。このループを繰り返し、ギャーをどんどん効率よく稼いで貯めていくという一連の流れが、このゲームシステムの中核です。
ギャーの循環が回り続けることでギャーの桁は見る見るうちに上がっていき、それに伴って地獄が再興されていくでしょう。
また、連打によって手に入る地獄石を使うことで、自動で連打してくれたり、現在のギャーに応じてギャーを即時入手できたりといった効果を得ることもできます。生産リソースの拡張に加え、この効果を組み合わせることで加速度的にギャーを稼ぐことが可能です。
地獄石は連打によってしか手に入らないリソースであるため、生産能力がどれだけ向上しても連打には価値があります。連打し続けましょう。
リソースをぶん回すことで、リソースの桁が上がり続けていく楽しさを味わえるゲームです。
無心に連打してギャーを稼ぎ、ギャーをもってさらなるギャーを集め、地獄を再興していきましょう。ちなみに、連打だけではなく長押しでも生産は可能なため、指をつる心配はないのでご安心ください。
感想
クリッカーです。厳密にはキーを押すのでプレサーかもしれませんが、語呂が悪いのでクリッカーで良いと思います。
あまりにもUIがクリッカー過ぎて、最初はマウスで操作しようとしてしまいました。説明書を読みましょう。
クリッカーよりは放置に旨味がなく、常時クリックの価値が高めのバランスになっています。放置の性能を上げる設備投資以上に、クリックにより得られる地獄石をベースにした倍々ゲームの方が遥かに効率が良いためです。クッキークリッカーでもある条件下ではクリックが最高効率に変わるタイミングはあるので、クリッカーっぽいとも言えるかもしれません。
この辺はカジュアルに遊ぶ分には良くて、クリアを目指すだけならそれほど時間のかからないバランスも相まって、ミニゲームとしてちょうどいいボリュームを提供しているように感じました。
筆者は途中までは適度に施設を増やしつつ、あるラインから連打して地獄石を稼いで倍々ゲームをしていました。とにかく倍々ゲームの恐ろしさがわかる作品だと感じていて、最終的にはずっと倍にしつつ、影響ない範囲で設備拡張するようにしていました。何なら設備拡張すら要らなかった可能性はあります。
あるタイミングからは長押しで良くなるので、指にも優しいのは良かったです。あのまま最後までやってたら指をつってたかもしれない。
また、無量大数より先にも到達しましたが、カンストしすぎてバグみたいな状態にはなりますが、ちゃんと動きはします。要求値とか諸々おかしいので、二倍に増やそうとすると表記上は減るみたいなことは起こりますが。
連打しながらでもメニューが触れる構造なのが良く、連打して地獄石を稼ぎつつ、施設強化などを並行して行うことができて効率が良いです。
一方で、メニューそのものというか、主に地獄石の使い方が説明書を読んだ上でもしばらくはつかめず混乱していました。
地獄石のメニューを開くまでは行けるのですが、そこでメニューを左右移動する発想がありませんでした。左右という操作については記述があるんですが、それによるページ切り替えの発想が浮かばないという状態です。恐らく、メニューのUIを見て切り替えできるように感じないのが遠因なのかなと考えていました。
後は、フレーバーが軽めにあるのも良くて、画面の変化に一役買っています。鬼だけだと画面映えしませんからね。
クリアするとちゃんと笑顔になるのも細かくて好きでした。
53. 亡者の行軍 Invasion from OtherSide
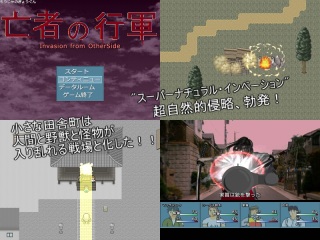
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| RPG | 雪見大介 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 2時間 | 1.25 | 10日でクリア |
良かった点
- 様々な要素が渾然一体となったカオスな世界観が魅力的です
- オープンな世界を回っていく楽しさがあります
気になった点
- ラストパートが長めなので、リザルトをもう一度見るハードルがやや高めです
- クリア後に何らかの手段でリザルトだけ確認したくなりました
- 宝箱やヌシを回収したい、クリア後にやり込みを始めるプレイヤーでない限り問題はありません
レビュー
自由に探索
亡者の行軍 Invasion from OtherSide は、オープンなシナリオとカオスな世界観が融合したRPGです。
タイトルにある亡者に加え、クマや妖怪も飛び出る混沌としたオープンなマップを探索していくことになります。
この開けたマップ上において、どこに行って何をするかはプレイヤーにほとんど委ねられています。いきなり奥地まで進んでアイテムを集めるも良し、とりあえず近場を探索していき足元を固めるも良し、好きなプレイスタイルでもって攻略に挑めるでしょう。
加えて、エリアごとの攻略法そのものにも自由度があり、一つの課題に対して複数の回答が用意されていることもあります。正面突破やスキルを使った搦め手など、これまた好きな手法でもって攻略していくことができます。
そうした攻略の壁として立ちはだかるのは、各地で発生する戦闘です。回復リソースが限定的な分、雑魚を相手取っても緊張感のある戦いになってきます。
特に、各エリアの攻略において最大の障害となるであろうボスは強力であり、相応の準備をもって挑むことになるでしょう。
そういった強敵との戦闘にあたっては、リソースを消費する代わりに大打撃を与えられる銃の使いどころが肝心です。苦戦する相手に対しては、温存することなく迷わず使っていきたいところです。
とにかく自由にマップを探索し、自由にシナリオを進めていくことのできるゲームです。個別具体の攻略法もまたプレイヤーに委ねられています。
心の赴くままに探索し、準備を重ね、ラスボスに挑んでいきましょう。
感想
フリーシナリオRPGとして、どこに行っても良く、何をしても良い感覚が得られるゲームでした。
とはいえ目的もなく放り出されるわけではなく、明瞭な目的に対してどういうアプローチで攻略するかという面においての自由度があります。割と適当に回っても色々見つかるようにはなっているので、いろんなところに手を出して気ままに探索していくのが楽しいです。
とにかく攻略法がいろいろありそうなのが良く、プレイヤーの進め方や考え方やビルドの方向性などで解き方が変わってきます。例えば筆者は鍵開けで屋上の警察官を倒しましたが、多分ロープなりで登るという選択肢もあるでしょう。
加えてフィールドもそこそこの広さがあり、ここも回り方は人それぞれになってきます。ちょうどいいレベルでプレイヤーに選択権が渡るので、適度な自由度を得て探索していくことができるようになっていました。
また、フィールド上においては、行くべき場所というか接続点は分かりにくい状態にはありますが、そこはUIで補助しています。このため、近づきさえすれば接続面はだいぶ分かりやすいのが良いところです。
なお、時間の概念があり、日数経過に応じた時限イベントがないわけではないようですが、デメリットは無いのでそこは安心できます。
筆者はそこそこちゃんと歩いたつもりでしたが、割と取り逃がしていました。
特に、トレジャーを9逃しているのでまだまだ探索は足りません。ウナギを渡しそびれたのと、開けてないエリアがいくつかあるのは覚えていますが、記憶もだいぶ曖昧でした。このあたり、どこに何があるかメモっておくべきだった気はします。
一方で、戦闘面では各地の妖怪は結構倒しておきましたし、月無し以外は討伐しています。月無しは一回遭遇して壊滅的被害を被ったので撤退していました。アレは強い。
シナリオ面はやや薄めですが、その分背景情報は色々あるので考えを巡らせることもできます。
また、状況がしっちゃかめっちゃかなのも良く、 警察は機能してないしよくわからん亡者はいるし妖怪は出るしの大渋滞です。相対する敵もそれ相応にバリエーションに富んでいる上、ラスボス周りできっちり回収もされました。
カオスに近い状況にもかかわらず、上手いことまとめて最後の展開につなげている剛腕は素晴らしいの一言に尽きます。
また、オープニングのカーチェイスなど、細かい部分の演出力も高い仕上がりになっていました。
戦闘面では探索も含めてSPが希少で、釣りもそうなんですが効率は悪めです。戦闘で使う場面はかなり限られており、庇うか応急措置がメインになりそうです。そのため基本的に殴り合いになりやすいバランスとなっています。
一応、デメリットなく日数経過で全回復できるので、SPなどのリソース管理にそこまで気を遣う必要は本来ないんですが、なんとなくリソースをケチって戦いたくなっていました。
その一方で明確にリソースを管理して強敵に切るべきアイテムとして銃が存在し、これが極めて強力なのが良かったです。ラスボスエリアでは、そこそこセーブ禁止区間が長いので、これをどこで切っていくかが攻略において大事になってきていて、使った時の破壊力が印象に残るようになっていました。
そして、セーブ禁止のラストエリアとわかっているがゆえに、ラストエリクサー症候群に陥らずに、魚だの熊の胆だのを遠慮なく使えるのも良かったです。ここまで貯めてきたリソースをフル活用してボスに挑めます。
しかし同じウディコンで土雲被りすることがあるとは思いませんでした。日本神話のブームが来てるのかな。
54. SICS(シックス)~特殊事件対策係~

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ガンシューティング | お魚UFO |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 1時間30分 | 1.16 | クリア |
良かった点
- ガンシューティングとして完成度が高かったです
- 怪生物を始めとしたグラフィックで良い雰囲気を作っていました
気になった点
- 当たり判定が直感的ではない、ないしは当たった時の手ごたえ感が薄い印象を受けました
- ヒット演出が弱く、敵のノックバックなどもないので、じっくり見ないと攻撃が有効打なのかをいまいち確認できません
- 上方にいるボスが多いのですが、上方向を向いた時の主人公のモーションが一番動きが無いので攻撃しているかが分かりにくくなっていました
- 他方向だとエフェクトなりモーションなりでリアクションがあるのですが、上方向だとSEだけとなっています
レビュー
怪生物を撃ち倒せ
SICS(シックス)~特殊事件対策係~は、迫りくるゾンビや怪物を撃ち倒していくガンシューティングです。
マップを徘徊する敵からダメージを受けないように立ち回り、困難を排除していくゲームとなっています。
ゲームの基本的なシステムは見下ろし型のガンシューティングであり、手持ちの武器と敵の位置やその距離感を加味して上手く相手取っていくものです。ただし、倒すことは必ずしも必要ではありません。シナリオ進行のためには移動と探索で十分なこともあるので、銃の弾薬を節約するためにも時には逃げることも大事です。臨機応変に立ち回りましょう。
それでも進行の上で障害となる敵を倒す場合は、多様な武器を使いこなすことが大事です。ゲームの進行とともに使える武器は増えていくので、適宜使い分けていきましょう。なお、ガンシューティングではあるものの武器の中にはナイフなどの近接装備も用意されています。被弾の可能性が劇的に高まるリスクはありますが、弾薬消費を抑えたい時は積極的に活用していきたいところです。
そうして必要な場面で敵を倒しながら探索を進めていく過程で、要所要所ではボスと遭遇することになります。ボスはそれぞれ特殊なギミックを持っていることが多く、歯応えのあるアクションが楽しめます。敵の性質を捉まえて攻撃を避けつつ、弾薬を惜しまず使って上手く攻略していきましょう。
そうしてボスを倒していくことで探索はさらにもう一段階進み、シナリオもまた進行していきます。廃村から始まる怪生物との戦いは、やがて様々な場所を舞台としたものへと変化していくことになるでしょう。
全体を通し、往年のガンシューティングを彷彿とさせる作品です。それ故にアクションスキルを要求されるシーンは多いですが、弾薬や回復アイテムが比較的多く手に入るため、ある程度は融通が効くデザインとなっています。
怪生物に銃を始めとした武器で挑み、生き残りをかけて戦っていきましょう。
感想
ガンシューティングとして既視感を覚えるレベルでしっかり作り込まれた作品でした。ものすごく有体に言えば、の〇ハザを強く想起させる作品です。思い起こさせる程に完成度が高いということも意味しています。プレイしていて懐かしくなってきました。
作中のシステムやら雰囲気から少なくとも意識はしていそうなんですが、どうなんでしょうか。
筆者は途中まで斧をぶん回して進めて、ラスボスだけ諦めてロケットランチャーをぶっ放してクリアしました。
斧が割と強いのは結構良くて、近接でナイフでチマチマやるストレスなく戦うことができます。弾丸数を気にしてしまう吝嗇気味の人間としては、思う存分振ることができるそこそこ強い武器が用意されているのは助かりました。
ラスボスはさすがに斧でやるにはしんど過ぎたので、何回か挑戦したのちに諦めてロケランに手を伸ばしました。やっぱり遠距離武器は最強。
そういう意味であんまりガンシューティングとして楽しんでいないきらいはあるのですが、ラスボスに挑むための準備をする再プレイで銃を使いながら進めてみてもいます。銃を使えば苦戦していた敵も割と倒せるのでお勧めです。なんで斧でセルフ縛りしてたんだろう。
ナイフや斧、銃以外にも火炎放射など武器が豊富にあるのも結構面白く、それを使った特殊ギミックっぽいボスも登場します。
そうでなくても逃げるだけのエリアなど、ただアクションをやる以外の仕組みも入っていたり、途中から大きく場面転換したりと、飽きにくい作りになってるのも良いところです。村から研究所へ向かうさまはバイオハザードを彷彿とさせます。
個人的に火炎放射をフル活用する植物ボスは結構好みです。場面にも合っていて、ギミックも分かりやすく、それなりに強くて歯ごたえがありました。
なお、全ボスそれなりに攻撃パターンさえ理解すれば倒せる程度の難易度となっていますが、ラスボスだけはべらぼうに強いです。
斧クリアを諦めてありったけのロケランを積んでなお薄氷の勝利でした。
ラスボス戦は下に移動しながら上に攻撃する都合上、振り返って攻撃したいのですが、方向転換だけすることができないので必ず一マス移動し、これが被弾の遠因になることが多かったです。方向転換のみのキーか、向き固定のキーがあると難易度が下がりそうです。
また、ラスボス戦に限り、基本的に上方向にしか攻撃ができないのですが、これが上方向攻撃モーションの動きの無さとかみ合いが悪く、攻撃してるのかどうなのかの手ごたえがなかったのもしんどかったです。ずっとこれは有効打なのか疑問に思いながら戦っていました。
また、回復アイテムを使おうとメニューを開いた瞬間にゲームオーバーになることもしばしばあったので、回復アイテムがボタン使用だと助かるなとも感じています。何故か会話ログが出て進行不能にもなりました。ラスボスで運悪く変な挙動引きすぎですね。
また、全体的に当たり判定が不明瞭なところが多く、ダメージの手ごたえ自体は薄めです。ちゃんと死亡モーションには遷移してくれるので雑魚は倒したという感じが出るのですが、強い敵だと攻撃したという感覚を得られにくく思いました。
SEである程度表現はされているんですが目立たないので、エフェクトなりなんなりで視覚的に見たいところです。とはいえ、そこまですると画面がうるさくなるという懸念もあります。難しい。
また、受けたダメージ量が分からず、その結果回復するべきか判断に迷うケースもありました。HP残量がメニューを開かないとわからないので、常時出ている状態だと嬉しいかもしれません。ダメージ量も視覚的に分かります。
タイトルからして絵が動いていますが、グラフィックの質は高いです。
ドット絵による各種敵の個性も良ければ、一枚絵や顔グラフィックの質も担保されており、どちらの方面でもゲームを強く演出しています。画に動きがあるの良いですよね。殊にボスは全部特徴的で、とりわけラスボスはラストに足る迫力がありました。
55. 文無し行商人の遺跡探索

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ローグライクデッキ構築 | なす太郎 |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 2時間30分(NORMAL)+30分+α | 1.01 | VERY HARDクリア |
良かった点
- 悪運に呑まれない安定したビルドを作っていく楽しさがあります
- 緩いグラフィックと緩い世界観がマッチしていました
- ある程度ルート分岐があるため、選択の幅が広がっています
- 細かい設定が拡張設定に押し込められているため、初見では必要最低限を見つつ、慣れてくると色々カスタムできるようになっています
気になった点
- 非戦闘時にスキル等を選択すると、その効果が進行ルートUIの代わりに表示されますが、これを戻す操作がやや直感的ではありませんでした
- 何らかの効果説明がないボタンを押す、というものだと認識しています
- 特にスキルが埋まっていると、この効果説明がないボタンが少なくなるのでちょっとだけ混乱します
- 慣れるとキャラクターを明示的に押せば確定で切り替えられるので気になりません
- 何もない所をクリックしたらカーソルUIだけキャラクターの所に移動する、あたりの機能があると解決するかもしれません
- 何らかの効果説明がないボタンを押す、というものだと認識しています
レビュー
ローグライクの沼へようこそ
文無し行商人の遺跡探索は、ダイス運に左右されながらも都度のアドリブ力とビルド構築の力で乗り切るローグライクです。
イベントや戦闘が満載のマスから成るフィールドを、30マス無事に進むことでゲームクリアとなります。
| 戦闘画面 |
|---|
クリアの障害となるのは主に戦闘です。HPを全て削り切られるとゲームオーバーになるので、上手く戦って勝利していく必要があります。
その戦闘中の行動はダイスによって制御されており、出た目に応じて取れる行動が変わります。例えば上記の画面で言うと、2列目が1、3列目が3となるためパンチの1打点だけが主に取れる行動です。
ただし、こうしてダイスだけで全てが定まるのであれば運ゲーとなってしまいます。そのため、このゲームにはダイス結果に影響を与えるスキルが存在しています。例えば上記でプラスワンというスキルを発動すると、いずれかの列を一つずらすことができます。ダイスが外れた3列目を下に一つずらせばキックで2打点与えられるようになる、という寸法です。
すなわち、ダイス運によらず安定して戦闘に勝利していくには、安定して運用できるスキルが鍵となります。
スキルはダイスに干渉できる以外にも、攻撃に使えるタイプ、防御に使えるタイプ、パッシブスキルとして機能するタイプなどが豊富に存在しており、これらを戦闘中に上手く活用していくことになるでしょう。
なお、スキルを発動させるにはチャージが必要であり、原則ターン開始時に溜まっていき、一定の数値に達することで使えるようになります。ただし、ダイス1列目のパラメータによって性能が変わるスキルもあるので、即座に発動するべきかは状況に依存します。切り所を考えるのもまた、大事な要素になってくるでしょう。
また、安定した勝利には各列のパンチ、キックのパラメータの強さも考慮から外してはいけません。ダイスがそこを指せば無条件で発動するため、コンスタントなダメージ源として機能します。
そして、パラメータは分散させて期待値を上げるよりも、偏らせる方をお勧めします。多くの場合で、一撃のダメージが大きくなる方が優位性が高いためです。ダイス操作スキルなどで偏らせた位置に上手く補佐して、強力なパンチやキックをお見舞いしましょう。
これらのスキルやパラメータといった戦闘における重要な要素は、進行とともに習得し、強化していくことになります。この強化で重要になってくるのが、戦闘後の報酬です。戦闘に勝利したら、スキル習得に必要な経験値とパラメータの強化が提示された選択肢が三つ表示され、その中から一つ選ぶことになります。現在の置かれた状況、所有しているスキル構成、各列のパラメータの状態などを加味して、目指したい方向性の選択肢を選んでいきましょう。
このように、戦闘をこなすほど強くなっていく仕組みのため、戦闘を適度にこなしていくことが後半のアドバンテージへと繋がります。特に序盤では、被弾を抑えつつも積極的に戦っていきたいところです。
なお、経験値を消費して得られるスキルもまた、ランダムに選ばれた三択から好きなものを一つ選んで習得していく形式となっています。このため、挑む度に異なるスキルセットでクリアを目指していくことになります。強化の方向性を都度考えつつ、シナジーを探りながら何度も挑戦し、良いビルドを見出していきましょう。
この時点でも運を克服するに足る様々なシステムが用意されていますが、加えてこのゲームにはプレイアブルなキャラクターがもう一人います。すなわち、パラメータもスキルももう一人分構成できるというわけです。
もう一人のキャラクターであるアイラはメインのBBより先に動き、全体攻撃や防御貫通攻撃といった別種の行動を取ることができます。こちらの方向性も併せて検討し、うまくメインのBBとのシナジーを出せるように探っていきましょう。
空転しがちなダイス運に抗うには、自分なりに強いスキルでビルドし、各列のパラメータを拡充し、不幸を出来るだけケアできる体制を整える他ありません。ここで紹介した以外にも、いつでもダイスを振り直せるエクストラダイスや、パッシブとして強力な効果を持つアイテムと言ったものもあります。これら全てを十全に活用し、知識と経験に基づいたその場のアドリブ力と構想力で運をねじ伏せていく楽しさのある作品となっています。
挑むたびに変わるスキル構成から自分なりのビルドを目指し、運を支配してクリアを目指していきましょう。ゲームオーバーになっても、その知識をもとに再挑戦させる中毒性があるため、遊び過ぎには注意が必要かもしれません。
感想
本当に無限にやりそうなので、これが番号後半にあって良かったなと思っている作品です。
筆者は残り時間的にもNORMALをクリアしたらさすがに次に行こうかなと思っていましたが、クリアした瞬間におもむろにHARDで次の周回を始めていました。もう少し筆者の意思が弱ければ、そのままVERY HARD の沼に入っていたこと疑い得ません。
何回か挑んでクリアできずに、後ろ髪引かれつつもやめてしまったことは若干後悔もしています。
何はともあれ、ローグライクとして完成されたシステムの話をします。
前作からダイスの割り当てが撤廃され、やや戦略性が失われましたが、それを補って余りあるほどにテンポが向上していて非常にスムーズに進行します。特に今作は二人のスキルを操作することになるので、このテンポ向上の恩恵は高く、高いリプレイ性の一つの要因となっています。
スキルについてもテクニックとスピードを意識するものとパワーで押すものが混在し、ビルドの指針を定めつつ選択していく楽しみがあります。そうしたスタンダードなスキルのほかにも、魔法を絡めたトリッキーなものやパッシブスキルといった変わり種も習得でき、毎回異なるビルドをあれこれ試しながら進めることができます。
このスキルの種別の数はちょうど良く、何度かプレイすればおおよそ把握できるものの、毎回ポケットの6個は微妙に異なるビルドで最後まで挑むことになります。運が悪いとシナジーの出ない組み合わせになることもありますが、ビルドの指針通りに組みあがったシナジーを持つスキル構成は無類の強さを発揮してくれます。思い通りにいけば爽快で楽しく、ままならなければそれはそれで苦労の味として楽しめます。
個人的にはエクストラターンも取れるスピードベースで組むと有利かなと考えて組むことが多いですが、スピードベースの技は火力が抑えられているものが多く、バフのスキルもあまりないという綺麗なバランスになっています。一方でテクニックベースは火力が出ますが、スピードを担保できないので敵のエクストラターンでやられがちです。
パッシブも強力なスキルが揃っていますが、パッシブばかり集めるとスキルが回らず負けやすくなっています。この当たりのバランス感覚が優れていることにより、色々な構成を試すことができる土壌が醸成されていました。
また、ステージのマス数もちょうど良い長さとなっており、これが高い中毒性を生み出しています。あと少しでクリアできそうなラインを演出しつつ、一筋縄ではいかない長さをしています。
中間としての遺跡があるのも良く、ひとまずの区切りとして捉えやすいです。遺跡まで行ければ、大体ビルドと思考は間違っていません。後はダイス運とより強靭な戦略が必要です。
各マスで発生するイベントも特徴的で、良くないイベントもダイスとステータスによってはメリットに化けるのも面白いところです。ステータスを上げる意味がより強く出ます。単純なイベントでもステータスダイスは振ることになるので、序盤にステータス強化をしていると地味に効いてくるところとして機能していました。
また、先々のマスをある程度見ることができるため、小さな戦略を立てやすくなっているのも良いポイントです。体力が危ない時にベッドを見ると、あの電柱までは頑張ろう作戦を発動できます。
ちょっとだけ分岐選択要素があるのも悩むところとなっており、体力を勘案して戦闘を避けてイベントマスでギャンブルするかといった小さな駆け引きが生まれます。
そして何より、ダイスに支配された戦闘の射幸性は極めて高いものになっています。事実上ダイスは振っていませんが。
あえて偏らせて組み上げたピースにきっちりはまって火力が出た時はドーパミンが出たような感覚がしますし、あと一回刺せば勝てるときに連続でプラスワン領域から外れてエクストラダイスが空転した時の絶望感はすさまじいものがあります。後者をベリハで一度味わいましたが、筆舌に尽くしがたいものがあります。なんで端に張り付くんですか。
この運に支配されたように感じる戦闘において、初期スキルにプラスワンがあるのが戦略性を成り立たせています。習得スキルでなく初期スキルにしてあるのは非常に良く、ダイス操作というスキルの強さを感じるきっかけともなっています。運命操作できるのはやっぱり強い。
エクストラダイスと出目操作の切り所が勝負の分かれ目と言っても良く、どうやって運を乗りこなすかが問われています。ローグライク、割と理不尽に挑むところに楽しさが存在する節がありますね。
筆者がNORMALをクリアした時の最終ビルドは、二段蹴りのコツとハイキックのコツをブレンドして蹴り主体で戦ったものでした。
地味にエレキヒットからの片足タックル+掌底やステータスの加速でエクストラターンが取れていたのも強く、この中で作っておいた蹴り火力8をぶっ放していました。プラスワンを考えると半分の確率でかなりの火力の蹴りが飛んでくる構成となっており、ガードも何のそのです。
NORMALでコツをつかみ、HARDは2回目で突破できたのですが、VERY HARDはだいぶ難儀しました。最初に一番惜しいところまで行った時は、エクストラターンで倒す手前まで行ったところでエクストラダイスが空転して最大火力の蹴りが出ずに敗北しています。
最終的なVERY HARDクリア構成は、スピードを活かしたエクストラターン確定戦術でした。
スピード3のマスを何個か作った上でリロールで固め、フロントステップと合わせることで初回でエクストラターンを狙う構成です。
その後も片足タックルやエレキヒットなどを絶え間なく打ち、エクストラターンを切らすことなく続け、ターンを稼いでシュートダウンやアイシクルランスといった強力な攻撃を当てられるようにしています。
最終戦はエクストラターンを死守し、ためておいたエクストラダイスの切り所を考えながら有利に進めてクリアへと至りました。エクストラダイスの使いどころか悩みながら戦うのは楽しかったです。
地味に被ダメージ6なので、実績にあと一歩届いていませんね。無念。ほぼ毒ダメージです。
| HARDクリア時の構成 | VERY HARDクリア時の構成 |
|---|---|
VERY HARDの難易度バランスはかなり良く、あと一歩届かないレベルと感じる絶妙な塩梅です。プレイミスをした時のしっぺ返し分でちょうど負けるくらいの調整に仕上がっているので、何かミスったらそこを遠因としてどこかで足りなくなります。
これは運が悪ければどうしようもないバランスとも言えますが、そういう時は切り替えて次に活かすことにしていました。一プレイが短いのがここで効いてきます。
何度も繰り返し、技構成の強い指針を学び、リスクを取って成長を選ぶ初期の選択を過たなければ、いつかはクリアの扉が開きます。運は慣れである程度支配できるので。
また、何度も遊んでしまうもう一つの要因として、スムーズに使うことのできるUIも挙げられます。
いつでも右クリックすれば説明が出てくる便利な機能を始めとして、プレイヤーが何となく操作すればそれっぽく動くように工夫が施されています。アイラのスキル枠を選べばアイラが選択されたのと同様の状態になりますし、ダイス確定はボタン以外でも適当に連打していれば勝手に行ってくれます。
慣れてくるとかなり軽快に動かすことができるので、サクサクとプレイしてはサクサクとやり直していくことができました。
個人的に好きなのは細かい設定を拡張設定に押し込めているところで、最初のプレイ中は意識する必要がなく、周回したい人には便利なものとなっています。いきなり大量の設定項目を見せられても訳分かりませんからね。
一方で快適さに振っている代償として誤操作しやすいつくりにもなっており、特に次へと休むのボタンが被っているため連打していると誤って休みがちです。恐らくマウス移動の少ないデザインなんだとは思いますが、距離は多少離れていた方がありがたいかもしれません。
この辺りはレスポンスが良い弊害ともいえるところで、個人的にはレスポンスを良くする方に振っているのが好きではあります。
最後にシナリオとグラフィックについても触れておくのですが、双方とも緩い雰囲気で箸休めとして良いです。
各種イベントがあると小会話を見ることができるので、息抜きでやり取りを楽しむことができます。会話が出てきてログ化するデザインは良く、台詞のやり取りが自然に行われます。中央で被ってしまっているのがやや気になる所ではありますが、3人並べる都合上仕方のない所かもしれません。
敵のグラフィックも緩い見た目でありながら、その役割が見て取れる良いデザインです。
毒を扱うものは毒々しく、変な技を使うやつは変な格好をしています。大体変な格好と言われればそうかもしれません。
個人的に竹馬のウサギが一番好きなのですが、バフに1ターンかけてボーナスタイムを用意してくれるからそう感じているだけかもしれません。性能の呪縛からは逃れられない。
とにかく全体を通したリプレイ性の高さから中毒性を生み出し、延々とやってしまう魔力を秘めたゲームです。無限にやってしまうので、こんなゲームをコンテストに出されると困りますね。ほかのゲームをやる時間が見る見るうちに溶けそうです。
この感想を書いていたらやりたくなったので、またVERY HARDに挑もうかと思います。
56. 棺ふる海

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ソロジャーナル | うどんのたまご |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 30分 | 1.02 | 完成 |
良かった点
- 色々な思考が誘引される良いテーマでした
- ダイスで緩めに制限が入る指向性のおかげで、ある程度まとめやすくなりました
気になった点
- ジャーナルをもう一回書きたくもなりそうなので、空のジャーナルを再度出力してほしくなりました
レビュー
棺ふる海に、あなたは何を見ますか
棺ふる海は、ソロジャーナルと呼ばれるジャンルのゲームです。
与えられたシチュエーションをもとに、自らの手で物語を紡いでいくことになります。
自ら設定と物語を組み上げていく土台は、海の底に住む海妖という設定と、海上から降る石棺を皮切りとしたいくつかの断片です。
海妖がどういった存在であるか、その場所はどういったものなのか、そして石棺は何故降り続けるのかという結末まで、プレイヤーは物語の語り手となって記述していかねばなりません。
いくつかの設定についてはダイスによってランダム性が与えられるため、プレイヤーによって、あるいはプレイした周回によって異なる物語が紡がれていくことでしょう。
設定という指向性のもと、自分だけの物語を構築できる作品です。与えられた設定における指向性の塩梅がちょうど良いため、ジャーナルを書いていくのはさほど難しくありません。設定から想像される情景を描いていきましょう。
あなただけの物語を紡いでみてください。
感想
これはゲームなのかと思いつつ、まあプレイヤーが楽しめる電子媒体はひっくるめてゲームだろうと思って楽しんでいました。ちなみに、物書きをごく軽くかじった身としてはすごく楽しいです。三題噺みたいなものなので。
ほぼ間違いなく創作者にしか刺さらないので、ウディコンという場だからこそ遊ばれるゲームな気もしています。
システムとしては、ある程度ダイスで物語に傾向が与えられるのが良くて、その時々に自己の方針とアドリブ力で誤魔化していく楽しさがあります。たまに以前書いた内容と矛盾が発生して大変になることもありますが、それもまた味です。
テーマ設定も良くて、よくわからないけど石棺が降ってくるというテーマ、色々書けそうないい塩梅の光景である気がします。なんとなく色々解釈が生まれそうなテーマを作るのって難しそうですが、かなりマッチしたお題という印象でした。
以下にざっと書いた筆者のジャーナルも載せます。
ただし、主観文章を書くのが苦手なのと、その時の気分と、ちょっとした誤読により客観文章で書いてしまっています。痛恨のミス。
1 | 『棺ふる海』ver1.02 プレイ日時:2023/08/11 |
57. Anthy
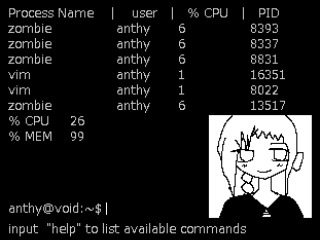
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| ゾンビサバイバル | リボン |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 10分(1時間)/1時間 | v?+2 | クリア+色々遊ぶ/V3プレイ |
良かった点
- 発想が良く、設計も良いゲームでした
- 様々な考察要素があって考えさせられます
気になった点
- コマンドラインなので上キーで前回入力コマンドの履歴を辿りたくなりました
- これをやると難易度が下がりすぎるので無いのが正解だとは思います
レビュー
Anthy is cursed. Never get involved.
Anthyは、ゾンビをCUI上でkillするゾンビサバイバルです。
Linux風のOS上で、ゾンビとなったプロセスをひたすらkillしていき、画面にいる少女を救うことが目的となっています。
ゾンビプロセスは放っておくとCPUを食いつぶし、やがてリソースが足りずにOSが落ちてしまいます。CPUをより多く喰っているゾンビを優先してkillしていくのが肝要になります。
ただし、それだけでは少女を救うことができないかもしれません。少女を救う権限を得るには、色々と調査をして回る必要があります。
ネタバレを避けた上では、筆者にはこれ以上書くことができません。与えられた情報を最大限に活用し、どうかAnthyを救ってください。
感想
here の方の新作ですね。面白くない訳がない。
以下はものすごくネタバレを含むので、できればクリアしてから見たほうが良いと思います。
プロセスがゾンビになるというのは用語としてありますし、killコマンドも普通に使いますし、何ならプロセスを殺すも普通に使うんですが、それでゾンビを殺すというところに落とし込むというのは思いつかなかったです。言われてみれば物騒な言葉使ってますね、エンジニア界隈。
その上で、それはゲームの表層でしかなく、このゲームをクリアするにはさらにメタなところを理解する必要があります。
説明で言われている範囲でコマンドやファイルとしては網羅できるんですが、そこからさらに誕生日を探し当てるのにHTMLページまで使うあたりが良く出来ています。
ついでにその時の情報を使うと色々見れるのも良かったですね。.vomit とか。
筆者はv2でここを一通り遊んで、/root/があるところまでは見つけたんですが、全然入れなかったのそこでやめていました。
クリア画面でのAnthyと思しき少女のリアクションも良くて、クリックしたり閉じるボタンにカーソルを動かそうとしたりするとちゃんと反応してくれます。最後までメタ的な認知の使い方が上手い。最小化と閉じるで微妙にリアクションが違うのも芸が細かいですね。
そしてここからは、ウディコン後にv3やった話に移りますね。ここからはゲームの話というよりAnthyの話になります。
以下はv3のネタバレを全て行うので、まだv3をやっていないのであればぜひプレイしてください。
さて、/root/は見つけていたので何か変わってないか見に行ったら/cyan/になっていました。2.1.21 の方のログインネームもcyanなので、同じ要領でパスワードを抜くのはそんなに難しくはありません。
そして、侵入して少女から話を受けるのもクリックするだけですし、クリックして話を聞いていれば最後のクリアと思しき画面に到達することも簡単です。ただ、その解釈をしようとすると、多分人によって変わってきます。
大前提として/cyan/Desktopにはpass以外に文章がいくつか存在していて、ここを読むと彼女、Anthyは予備の臓器として、私の一部として生きているという旨の言葉があります。
また、2.1.21ログイン後のAnthyと思しき少女の発言からは、暗く永遠に続くような光の見えないトンネルをひたすら歩んでいるような状態ということが分かります。
1.6.43 におけるAnthyと思しき少女が髪を結って快活である一方で、2.1.21のAnthyと思しき少女は髪を結っておらずぐったりとしています。これが時間経過によるものと仮定すると、恐らく1.6.43はCyan存命中に開発が進められていたStable版、2.1.21はその後Cyanが昏睡するまでの間に開発は進んでいたが完成はしていないバージョンであると推測されます。
1.6.43 における/cyan/のパスワードで2.1.21に入れたことから両者は同一と考えると、1.6.43における/cyan/以下にあるファイルの言葉はすべてCyanのメッセージではないかと推測されます。
/cyan/以下にあるメッセージは、getOut!などの強い言葉と、先述したAnthyを予備臓器として、という下りの文章があります。
ここで、HTMLページの開発チームの言葉を見ると、Cyanに娘――これがAnthyであることはパスワードと誕生日の関係からほぼ確定と見ています――がいるとは説明されていますが、この娘がどういう状態にあるかは何の記述もありません。
ここからはだいぶ妄想になりますが、Cyanは娘がまだ生きている(She is still alive)と言っています。つまり、同僚にも娘はまだ生きていると発言していたのではないでしょうか。ただし、その意味は(My dear Anthy, my spare organ.)であり、生きていると言える状況にあったかは疑わしいところです。
臓器がCyanの中にある状態で、Anthyの意識のようなものがOSに移ったと解釈した場合、これは現実ではなくても心の痛みがあるということは、OSに複製されたそれ自体は現実でなくても、Anthyというオリジナルがいたことにはなるのでその幻肢痛のようなものと解釈できるかもしれません。
さて、プレイヤーは最後に心臓をひたすらクリックしてAnthyの会話を聞き、最後にはエラーを起こしてある空間へと辿り着きます。左には暗黒の空間、右にはエラー起因で発生したノイズのような何かが現れ、ここにAnthyが現れて動かすことができます。右に動かすとBGMが鳴りだすことからも、こちらが順方向と解釈できるでしょう。
ここの解釈は人によりそうですが、筆者は心臓をクリックし続けることで何らかのエラーが発生し、そのエラーにより発生したノイズによって完全に暗黒であった空間にこのノイズのようなエリアが発生したのではないかと考えています。
そしてこれが、Anthyがずっと戦い続けていたnever-ending dark tunnelを抜けたものであり、glimmer of lightを超える光であったのではないかなと解釈しています。エラーノイズが光を作ったならば、Anthyは救われていてほしいとも。
話を戻してCyanの話をします。臓器、だけではどの臓器か分かりませんが、このゲームにおける象徴的な臓器ならばまさしくAnthy.exeのアイコンであり、プレイヤーがクリックしてエラーにより壊した心臓があります。
これはcyanの中にあるAnthy.exeです。なればこそ、Cyanの中にあるAnthyの臓器である、と解釈できないでしょうか。Cyanは突然容体が急変して亡くなりました。それはプレイヤーがAnthyに光を与えるために心臓にエラーを起こしたからかもしれません。
ここに関しては時系列的におかしいので何とも言えませんが。我々は誰かが行ったそれをゲームとして模倣しているだけかなとも。そのへんをより正しく解釈しようとするなら、Anthy is cursed と唯一言及しているフォーラムのAllytiを深掘りしたいところですが、この辺が限界な気もしています。
あともう一つ、never-ending dark tunnelあるいはabyssについて。
1.6.43時点ではAnthyと思しき少女の背景が白だったのに対して、2.1.21の背景は黒くなっています。これがdarknessなのだとすると、1.6.43時点では彼女はまだ暗闇に囚われていなかったことになります。
リリースが停止し、打ち捨てられたOSであるがゆえにdarknessであるとするならば、CyanがAnthyの開発を続けられていればこうはならなかったことになるので、前述の話は部分否定されます。
そもそもAnthyが抗い続ける理由として、自分を愛してくれる人がいるという発言をしていることからも、誰かとの関わりを持っていたことが伺えます。それがCyanだとするならば、OSにAnthyの意識をインストールして生かしていたのはCyanの手によるものであり、She has become a part of me とは自分のプロダクトを自分の一部と捉えている発言とも取れるかもしれません。さすがに直後のorganやThank you for saving my lifeを考えると牽強付会なきらいはありますが。
ともかく、解釈を深めていくには、CyanとAnthyの関係性、AnthyとAnthyOSの関係性が鍵になってくるのでしょう。どう解釈すればいいんだろう。
Anthyの解釈バトルというか、他人の解釈聞きたいですね。誰かお願いします。
他人の解釈を聞いて広がりが出たらこのページに追加していきたい。
なお、全編通して英語の上にスラングもあり、かつ最後のAnthyの語りはまあまあ長いので、英語弱者には結構厳しいゲームになっていました。大体言いたいことは分かるけど、たまに本当に知らない単語が突っ込まれることがありました。
58. カエルはカエる

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| プラットフォーマー | ネオジム |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 30分 | 1.41 | コインコンプリート |
良かった点
- GB風のグラフィックで統一された雰囲気を醸しています
- アクションの操作性が良好でした
気になった点
- ステージクリアしたら残機を復活させても良いように感じました
- 最初に残機を減らしてゲームオーバーを経て回復してからステージに臨むのが効率の良いプレイになっています
- レトロ感を演出するという意味では正しい設計のようにも思います
レビュー
GB風アクション
カエルはカエるは、GB風のグラフィックが懐かしいプラットフォーマー型のアクションです。
5つのステージに分かれており、それぞれのクリアを目指していくことになります。
アクションとしてはオーソドックスな形式であり、ジャンプやダッシュを駆使して足場を渡り歩いていくステージデザインとなっています。ただし、ダッシュの慣性は独特なものであるため、焦って使うと失敗しがちです。急いでいる時ほど、慎重にダッシュを使っていきましょう。
また、システムの中で特徴的な点として、カエルの舌を使ったワイヤーアクション的な要素が挙げられます。各所にある特殊なギミックに舌を引っ掛けることで、空中ジャンプの操作ができるようになっています。これを上手く使うことが攻略のカギとなるでしょう。
アクションの操作性が全体的に良好なアクションゲームとなっています。難易度は程よく難しいため、ステージクリアの達成感もまた程よく味わえます。
カエルの操作に慣れていき、ステージのクリアを目指していきましょう。なお、各ステージにはコインが隠されているので、慣れてきたらコインを集めるチャレンジをするのも一興です。
感想
GB風味の統一感あるグラフィックが良かったです。アクションとしてはそこそこの難易度となっていて、特に最終面の強制スクロールは割かしハードなため、プラットフォーマーアクションを楽しめました。
この最終面のレベルデザインは、強制スクロールに初見殺しを組み合わせたものなのでかなりミスしやすい作りとなっています。難度が高そうな方に移動したら強制ダメージ、折れ曲がりルートで出っ張りへの誘導など、一発で通させない意思を感じます。
話をアクションに戻すと、操作性が概ね良好に楽しめる変則ワイヤーアクションとしての完成度が高いです。ワイヤー操作そのものは、どの程度飛ぶかの直感性が弱いところはありますが、大体飛びたい方向に飛ぶことができれば問題ないようなコースのステージデザインでカバーされています。
ダッシュ時の慣性が独特なのも良い味を出していて、焦るとこの仕様でミスしやすくなっています。危ない時ほど落ち着いていきたいところです。強制スクロールではダッシュしたくなる気持ちを抑えられないので、その意味でも最終面はハードです。
また、ダッシュ操作自体は二度押しで行えるようになっていて、ボタンの同時操作が少ないメリットを取ったのかなと感じています。個人的には慣れていると別ボタンとの同時押しの方が便利なところもあるかなと思っていました。二度押しだと、誤操作で意識しない大ジャンプが発生して通り抜けることがしばしば起きたので。
この辺りはシンプルに寄せるか、誤操作を抑える方向に振るかのトレードオフっぽいので難しい所ではあります。
なお、GB風のレトロなグラフィックとコースデザインから、アーケードのようなゲームオーバーで一からやり直しを覚悟していましたが、実際はステージごとにやり直せる親切な設計です。コインを集めるのにも便利。
このおかげで大きく手戻りなくコースを学習でき、多少難しいステージでも何度も挑むことで突破できるようになっています。
ただ、ステージをクリアしても残機が回復しないので、最初にステージに挑む時はとりあえず減らしてゲームオーバーになって復活するのが推奨になります。残機フルで挑んだ方が勝率は良いので。ここはクリアしたら残機回復でもよいのかなと感じていました。
やや作るのが大変なステージエディット機能というかステージ読み込み機能もあるので、やろうと思えばオレオレ難しいステージも、難しいと感じたところを易化させることもできます。
このテキストエディット機能は面白く、さらに凄いことに曲までテキストで作っています。ここまで自作した強者は作者さん以外にいるのでしょうか。そうしてリアルタイムに演奏していることもあるのか、ゲーム容量は極端に小さく、ダウンロードが一瞬で終わった時は何事かと思いました。
レトロな見た目とは裏腹に操作性などは現代ナイズされたユーザビリティで構成されているので、非常に遊びやすいアクションとなっています。
ウディタを触ったことのある方なら、クリア後はフォルダの中身を覗いてもうひと驚き出来るはずなので、是非見てみましょう。
59. 死をきたい
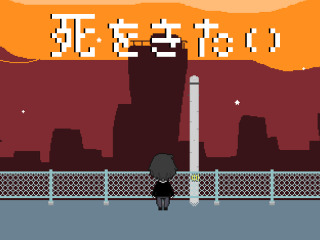
| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| 探索ADV | みやの |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 20分 | 1.05 | 全エンド |
良かった点
- ぷにどりが個性豊かで楽しい動きをします
- 周回がしやすい設計に思いました
気になった点
- ボーリングについて、相手の点数と押したところが一致していないような感覚を受けました
- 毎回4点くらいの所で押している気がします
レビュー
ぷにどり
死をきたい は、奇妙な世界を探索するアドベンチャーゲームです。
不思議な世界を探索しつつ、死を体験することで手に入る服を利用して、探索範囲を広げていくことになります。
死を体験するには、ちょっとした謎解き要素と探索要素をこなす必要があります。適度にマップを探索しつつ調べていきましょう。怪しいところがあれば、服を着替えてみるのが良さそうです。
なお、マップを探索するかたわら、各地で困っているぷにどりを助けることもできます。見かけたら声をかけてみるのも良いかもしれません。
アドベンチャーとしての主題はホラーに近いものであり、その中でも鬱屈とした暗いものがテーマに据えられています。しかし、マスコットキャラクターのようなぷにどりを始めとした可愛らしいデザインが、それをややマイルドにも、あるいは印象的にもしている作品です。
ぷにどりを助けつつ死を体験していき、物語を最後まで見届けましょう。
感想
変に言葉を選ばずに感想を言うと、フリーの微ホラーっぽい探索ゲームに求める中の一つそのものと言っていい作品です。希釈されていない原液に近く、ある種における原体験にも近いものがあります。
とりあえずぷにどりに言及するんですが、マスコットとして非常に良いキャラです。個性豊かなうえに楽しい動きをするので、世界観との良い意味でのアンマッチもあって印象に強く残りやすいキャラクター性をしています。鶏が焼き鳥を渡すな。瞬間移動の笛の時の動きは個人的な好みです。
他のキャラクターが専用の役割性を持ったような登場の仕方をすることもあって、よりマスコットとしての輪郭が強く記憶に残るのも面白いです。
ミニゲームとして遊べるボーリングにも言及しておくのですが、一週目はともかく、最終的にはトリプルしないと勝てない気がします。CPUが明らかに4点くらいの位置から9点をたたき出してきているような印象を受けました。不正していないか、君。
ゲームのメインである探索面については、程よく考えさせるギミックもありっつ、基本的には探索すればいける範囲で構成されています。序盤で行きたくなったところには、後々ちゃんと行けるようになっているあたりの探索における楽しさも担保されていました。
ギミックとして服を変えるというのがちょうどいい謎解き要素となっており、かつそこまで複雑でないレベルでマップに落とし込まれています。
加えて二週目のプレイ時については、ベースを同じにしながらいくつも異なる点を用意しつつ、色々とカットすることで探索しやすくなっています。この配慮のおかげで、二週目は手間と感じることなくエンドに到達することができました。
二週目固有の謎キャラクターもまた、主人公の中にある精神的な何かなのでしょうか。
個人的に好きなのはエンド分岐にかかわるものが最後に置いてあることで、セーブによる分岐確認がしやすくなっています。ありがたい。エンド分岐は全回収、未回収、二週目未回収っぽいです。他にもあるかもしれない。
シナリオは色々と散りばめて考察させつつ、大きな筋は用意されているタイプのものです。考えられそうな範囲では想像を巡らせられますが、タイトルなど大事な所はちゃんと回収してきます。バランスが良いですね。
60. 異世界ノ迷宮

| ジャンル | 作者 |
|---|---|
| RPG | koh |
| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |
|---|---|---|
| 2時間30分 | 1.22 | クリア |
良かった点
- ダンジョン前の拠点でも色々探索出来て楽しいです
- 拾った装備で能力値をカスタマイズしていくのが良かったです
気になった点
- クエストの絶対数が少なく場所も限定されているので、メニュー画面に常駐するような項目には感じませんでした
- また討伐など不要な項目がいくつかあったように思います
- あまり重要でない台詞でもウェイトがついていて、イベントのテンポを損なっている印象を受けました
レビュー
ソウルでカスタマイズして攻略せよ
異世界ノ迷宮は、敵を倒しつつダンジョンを踏破していくオーソドックスなRPGです。
レベルを上げて装備を付け替え、ステータスを上げてより強い敵に挑んでいくベーシックな体験が得られます。
RPGとして戦闘がメインに据えられており、攻撃で早めに倒していくのが重要なバランスに調整されています。そのバランスの中で素早く敵を倒していくには、ステータスの強さが大事です。そして、ステータスを上げるために重要なのは装備となっています。
ダンジョンで拾うことのできる装備がある他に、ダンジョンの手前にある町においても探索していると装備が見つかることがあります。装備を強化していくためにも、きちんと探索していきましょう。
また、主に敵が落とすソウルもまた装備となっており、こちらは基礎ステータスのいずれかを上げる性能を持っています。
最大3つまでソウルを装備できるので、キャラクターの役割に応じたソウルを割り振ることで指向性を持った強化を図れます。ダンジョンで遭遇する敵は積極的に倒していき、ソウルを集めていきましょう。
ダンジョンをしっかり探索して装備とレベルを整え、ボスに挑んでいく奇をてらわない進行で進むRPGとなっています。
堅実に成長を重ね、ダンジョンを踏破していきましょう。
感想
拾った装備でカスタマイズしてダンジョンに挑む、ちょっとだけハクスラっぽいRPGです。ダンジョン手前で色々探索できるマップが用意されているのも楽しい作品でした。
挑むべきダンジョンがある街およびその周辺は割と広く作り込まれており、かつ探索するとアイテムなどの成果も挙げられます。プレイの最初の方はずっとマップをうろちょろして色々と探していました。早くダンジョンに入れと言われそうです。
ダンジョン内はランダムっぽい地形に対し、モチーフやギミックで変化をつけているものなので、何なら手前のマップのほうが作り込まれているまであります。探索し甲斐がある。
ゲーム性としてはハクスラっぽいシステムを取っており、落とす装備を適度に回してパーティーを強化して進められます。
落とす装備が固定化されていて、ランクによって制限もかかっているので、バリエーションはそれほど広くはないものの、ざっくりと装備を回してカスタマイズして戦闘に挑んでいく体験自体は良いものとなっています。
魔法攻撃特化ビルドで魔法をぶっ放しまくるなど、ソウル装備の自由度で戦闘を楽しむことができました。
全体的な戦闘バランスは攻撃が強めのデザインになっていて、これがダンジョン探索に対してテンポの良い戦闘を提供しているので相性が良いものとなっています。
その一方でボスなどの攻略パターンについては庇って魔法で殴るのが強く、ソウルでカスタマイズしても戦略性の広がりはそれほどありません。やはり火力が正義。
個人的に気になったポイントとしてはメニューのクエストがあり、階層を進めるごとのイベントとして機能しているのですが、タイミングや達成条件を考えるとほとんどメニューにある意味をなしていません。受注してイベント完了して終わりなので。
納品など不要な項目もあることから、恐らく出来合いのコモンイベントを使っている気がしますが、消せそうなら消しておくと混乱が少ないかなと思っていました。
また、これは筆者がウェイトを多用するな教の信者だからなのですが、あまり重要でないイベントでも台詞にウェイトが入り込み、そこそこテンポを削いでいました。オープニングから散見されてるのがより厳しく、ゲームを遊ぼうとしているところに水を差されたような印象を覚えます。
演出上の意味があるケースはあり、効果的に使えるシーンは確かに存在するのですが、そういうところで効果的に使うためにも、普段使いするのは避けたほうが無難な気がします。
後は、最初の最初からゲームの開発日誌が読めるのが個人的には面白く、ゲームを始めた直後にすべて読破していました。こういうの、クリア後のおまけとしてはよく見る要素なのですが、最初からアクセスできるとは思いませんでした。
個人的に活字が好きなのと、体験記が好きなので、こういうオマケをあまねくゲームにじゃんじゃん入れてほしいです。
個人的得点表
| No | タイトル | 熱中度 | 斬新さ | 物語性 | 画像/音声 | 遊びやすさ | 加点 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 零落と紺碧の海神 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 35 |
| 02 | 少女大猩猩 -その猩猩、凶暴につき- | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 30 | |
| 03 | 祟女 -TATARIME- | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | |
| 04 | Forcelagoon2 因果律の少女 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 39 |
| 05 | 怖がらないでよ僧侶さん | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 37 |
| 06 | メリカと野菜の剣士たち | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 34 | |
| 07 | 群像物語~タコ型宇宙人と残された七日間~ | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 33 | |
| 08 | ギフテッドワールド | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 37 | |
| 09 | みかど出現 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 26 | |
| 10 | オミくじ | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 21 | |
| 11 | 竜と黄金の梨と焼け残り | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 31 | |
| 12 | 不屈のスペラ | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 2 | 41 |
| 13 | 煽り時計の誕生の旅 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 29 | |
| 14 | プリティアックス外伝 ~斧姫~ | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 30 | |
| 15 | ウラミコドク | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 45 |
| 16 | めっちゃ危険なダンジョンだろうとみんなで潜れば怖くない | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 32 | |
| 17 | 前進中の迷い人他四種のミニゲーム | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 25 | |
| 18 | ビャッコーギャモン | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 52 |
| 19 | その日暮らしの冒険補償 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 37 | |
| 20 | ECO2クエスト | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 28 | |
| 21 | 九色カーズレボリューション | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 21 | |
| 22 | SIBLINGS | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 49 |
| 23 | Alkersas | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 31 | |
| 24 | ウディダッシュ | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 22 | |
| 25 | コトノリ | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 35 | |
| 26 | マインのパズルでバトル | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 32 | |
| 27 | 一人非零和有限確定無情報非ゲーム | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 30 | |
| 28 | DayDreamDreamer | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 46 |
| 29 | 女神の迷宮 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 33 | |
| 30 | STARCHILD | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 27 | |
| 31 | オチル | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 22 | |
| 32 | アドリブ・ロール | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 38 | |
| 33 | ロロろくプラス | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 33 |
| 34 | BerriesWitch | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 39 | |
| 35 | 睡蓮 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 31 | |
| 36 | ヒーローの冒険 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 26 | |
| 37 | エド王子の冒険 大地の精霊と邪悪な神 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | |
| 38 | ~罠~狙われた仔共たち・・ | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 26 | |
| 39 | デジチューバー | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | |
| 40 | 可愛い子と夏祭りに行きてえよなあ! | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 30 | |
| 41 | ショートファンタジー マージョのマジかるパニカル | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | |
| 42 | じゃんけんバトラー俺 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | |
| 43 | オカルトノート 土雲ガクレ編 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 33 | |
| 44 | WOLFALL | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |
| 45 | 異界門事変 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 30 | |
| 46 | 救済少年の終末 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 35 | |
| 47 | 未来よ心のままに | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 40 |
| 48 | アリアとウィヴィと魔女の塔 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 32 | |
| 49 | マスコット | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 | |
| 50 | 「財宝竜と四騎士」The sunset and breaking dawn King | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 31 | |
| 51 | Know Your Enemy, Know Yourself | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 31 | |
| 52 | 一画面で成し遂げる地獄再興 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 30 | |
| 53 | 亡者の行軍 Invasion from OtherSide | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | |
| 54 | SICS(シックス)~特殊事件対策係~ | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 33 | |
| 55 | 文無し行商人の遺跡探索 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 41 |
| 56 | 棺ふる海 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 30 | |
| 57 | Anthy | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 35 |
| 58 | カエルはカエる | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 31 | |
| 59 | 死をきたい | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 31 | |
| 60 | 異世界ノ迷宮 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 |
結果発表を受けて
以下は推敲なしで、特に何らかの意図をもって書くことなく、思い思いに書いた感想になります。
多少不適切な表現や、矛盾した感想があるかもしれませんが、ご勘弁願います。
1位 SIBLINGS
このゲームを越える熱中度はあり得ないというレベルで楽しい作品です。トッポも驚きの最初から最後まで熱中度たっぷり。
画像音声についても、BGMやSEの巧みさ、演出のすばらしさを含めた総合力での判断と考えれば納得の一言に尽きます。演出力という面で言えば、頭一つ抜けてましたからね。
ずっと楽しいゲームというのは中々無いと思うんですが、このゲームはそれを達成しています。短編とは言っても素晴らしい。
相手の攻撃モーション、イベント、どれをとってもスピーディーで一切気持ちを切らすことなく最後まで走り切れる作品です。雑魚戦ですら楽しい。このゲームに対する一切の途切れのない没入感という意味では、無二の作品だったと思います。そりゃあ熱中度も高くなりますね。
2位 文無し行商人の遺跡探索
もうこの時点で1位か2位のどちらかには入ってるだろうと思っていました。個人的な順位はスぺラと同じで同率5位なんですが、どちらにも甲乙つけがたい魅力があるのでどっちが上とかはありません。
この作品が熱中1位じゃないというのは、今回のウディコン1位であろうあの作品の熱中度の高さを表していますね。レベル高すぎませんか。
しかし、デッキ構築ローグライク、ウディコンにブームが来ましたね。前年度の脳筋があまりにも良かったかからかもしれない。
ゲームとしての完成度はもちろんのこと、まあまあ理不尽に近い運要素があるのも魅力の一つです。神様は乗り越えられる試練しか与えないと言いますが、作者さんは割と乗り越えられるか怪しい運を要求してきます。それでも手持ちのデッキと知識とアドリブ力で乗り切ったところに強い達成感があります。乗り越えられる理不尽は気持ち良いですからね。
3位 不屈のスペラ
デッキ構築ローグライク、空前のブームなのかな。個人的に一番遊びやすいデッキ構築型ローグライクでした。チュートリアルが手厚いのもそうなんですが、何より自分で選択すべきことが極力省かれています。あえて削られた選択肢によってそれぞれの選択に注力できるの、めちゃめちゃ遊びやすい。遊びやすさトップもありうべきことです。
さらに個人的な話をすると、ピンチをチャンスには大分発明的で、この手のゲームで必ず取る必要のあるHPギリギリで敵と戦うリスクある行為に対してのリターンを増幅させているんですね。言い換えると、デッキ構築ローグライクにおける強い行動である「リスクを取って序盤からカードを充実させていく」という行為に対する強い動機付けを作っています。上手い制度設計だ。
そのあたりの表には見えにくいゲームデザインでも遊びやすさというかプレイしやすさが担保されている作品でした。
4位 ビャッコーギャモン
個人的優勝候補なんですが、難易度の高さでこの順位なんでしょうか。物語性トップなら最後までやった人多そうなんですが。プレイヤーの絶対数が少ないんでしょうか。
というか物語1位、その他1位、熱中斬新でBEST5入っても優勝できないんですね。魔境。
物語としての熱量は比類ないレベルで、最後の方はずっとあまりにも良いなあと思いながらプレイし続けていたわけなので、物語性が最高峰に位置しているのは当為といってもいいかもしれません。
アクション面でもガン攻め上等のスタイルが個人的にマッチしていてずっと熱中できたんですが、まあまあな高難度がちょっとした壁になってたのかもしれませんね。個人的にはちゃんと動かせるゲームの高難度は好きなんですが。
遊びやすさはその辺で響いたのかもしれませんね。後は、ゲームパッド用意できないと確かにきついゲームなのかもなとは思っています。
5位 メリカと野菜の剣士たち
デッキ構築ローグライトの中でも、デッキ制限と入れ替えでかなり緩く遊べるようになっているのが良い作品です。あの手のゲームの初心者にこそ勧めたい。遊びやすさの順位が高いのはその辺の所以ですかね。
デッキ構築型ローグライトの醍醐味の一つでもある、デッキに入れる要素の取捨選択というシステムに対するペナルティを極限まで落としたのが素晴らしい判断だったんだろうなと感じています。
要素のロストを無くし、取捨選択を常に行えるようにしておくことで初心者でもデッキ構築を緩く楽しめるようになっていますし、そもそもシナジーを考える上でも構成を気軽に変更できるので色々試しやすくなります。完成度の高い設計。
6位 零落と紺碧の海神
エントリー1番という手に取りやすさに対し、季節に合った爽やかな読後感というのもあって全体的に評価が高くなりそうな作品です。夏は良いよ。
20分しかプレイしていない割に3000字くらいレビューと感想を書いているところから分かるんですが、良く心に刺さる作品です。物語性の高さも必然という感じがありますね。
個人的に最大の効用があったと思うのはゲームオーバーの撤廃で、これが物語的にもシステム的にも良い方向にしか作用していないように感じます。後戻りはできませんからね。
7位 ウラミコドク
個人的に4位にしてますが、この辺はもう点数の関係なので全部1位です。なのでもっと上で良いんじゃないですかね。
物語について2位ならこの上はあれかなと思いつつも、構成という面においては間違いなく1位に君臨する作品でした。とにかく上手い。その他が強いのは、ダン□ンフォロワー故に伸びなかった斬新の補填なのかな。
これのせいで睡眠時間が削れて、翌日の仕事に影響が出たくらいには面白い作品です。
筆者個人が推理好きということを差っ引いて考えても出色の出来であるシナリオは、構成においても展開においても極めて完成度の高いものになっています。こういう綺麗に作られた物語好きなんですよね。
8位 救済少年の終末
マルチシナリオというか各キャラクターを上手くザッピングした物語が評価されつつ、遊びやすさが十全に担保されているので納得の順位ですね。
ともすれば複雑になりがちな複数人が絡むシナリオを、タイムラインや瞬間移動なのでシステム面で出来るだけロスがないように補佐しているのが良い作品です。FF16の評価にもあったんですが、最後まで遊ばせてシナリオを見ることのできる丁寧なゲーム設計だったと思います。
9位 その日暮らしの冒険補償
保険というシステムを上手くゲームに取り入れてシミュレーションにしているので、斬新が高いのはむべなるかなという感じです。むしろ1位じゃないんですね。個人的には同率11位なんですが、もうこの辺は甲乙つけがたいのでそんなに順位に意味はありません。全部TOP10。
個人的に文字情報というかただのステータスしか表示されてない人たちに徐々に愛着湧くのが好きでした。子供一人でそんな危ないところ行かないでね、みたいな気持ち。しかしコメント返答を見る限り、作者さんはかなりドライなのは笑いました。いやまあCDBとかで管理してたらそうもなるかもしれない。
10位 プリティアックス外伝 ~斧姫~
前年に引き続き、丁寧にネタをゲームに昇華した短編枠が10位にランクインしましたね。丁寧さと謎の中毒性がポイントなのかもしれない。
ここまでツクール2000っぽく作る徹底さが良く、タイトル画面を見た時に一番笑った作品でもあります。あまりにも懐かしすぎる。
内容的にはAXE無双ではありながら、多種多様なAXEを全身につけて多段攻撃で敵を屠っているのは変な爽快感があります。その勢いだけで乗り切れるレベルでゲームがまとまっているのも良い。
11位 DayDreamDreamer
個人的にこれが3位なんですが、これは私があまりにもJRPGを好きすぎるからだとは思っているので、正当順位がどの辺かは分かりません。でももっと上でもよくないですか。
とにかくRPGとしての空気感が最高に良くて、JRPGやりたい人には無制限にお勧めできる作品でした。
大体のエリアがちゃんと地続きでありつつも広さを感じられる構成で、しかも割と最初から色んなところに行けることも相まって冒険しているという感触が強く残ります。ファンタジー世界を冒険できるの、そういうゲームの楽しさなので。
JRPG好きが投票者に偏ればもう少し上に行ったんじゃないですかね。知りませんけど。
12位 BerriesWitch
あらゆる面で高品質なゲームだったので10位以内入るかなと思っていたんですが、今年の層が厚かったんですかね。個人的には同率8位でした。
特にUIのグラフィックや動きの面においては、他の追随を許さないレベルの完成度があると思っています。果物を育てて品質を上げていくシンプルなゲーム性を一切邪魔せずに補佐してくれていたのは間違いなくこのUIでした。
ウィンドウをただ出すのではなく、イージングしたり動きを付けたりという遊び心がシステマティックでないゲーム感を出していて、個人的には好きでしたね。分かりやすい上に遊び心がある。
ここからは個人的に気になった作品を取り上げます。
13位 怖がらないでよ僧侶さん
良いADVでした。物語性で上位を取っているのも頷けます。
個人的に同率11位なのでもうちょっと上みたいな気持ちはあるんですが、上も上で納得感しかないので難しいですね。そういう意味ではジャンル別の順位というのは良いシステムなんだなと思っています。
14位 SICS(シックス)~特殊事件対策係~
質の良いガンアクションだったんですが、あまりに質が良くて逆に斬新が下がったんでしょうか。個人的にはガンアクションなのに斧が強かったので斧でごり押していましたが。
緩い雰囲気と、注力したいところに注力された振り切ったデザインがフリーゲームっぽくて好きな作品です。
15位 ギフテッドワールド
遊びやすさに関しては他の追随を許さないかと思っていましたが、プレイ時間30時間表記が壁になって合計点で惜しくも2位という感じでしょうか。
このゲームは実質的には5時間でいったん終わるので、5~30時間表記のほうが多分プレイヤー数は増えたのかもしれませんが、その辺のウディコン作法的なものはなんとなく変な感じもするので難しいところです。
16位 Forcelagoon2 因果律の少女
これもプレイ時間20時間表記が壁になってそうです。物語性、平均なら4位なんですけどね。
やはりウディコンは長編RPGには厳しい場なんでしょうか。10時間クラスの中編だと戦えるイメージはありますが。個人的には長編RPG好きなのでもう少し増えてほしい気持ちがあり、今年はいっぱいあったので満足していました。このゲームもちゃんと長編RPGをまとめ上げていて良いRPGとなっています。
18位 アドリブ・ロール
設定も斬新なら戦闘システムも斬新な、斬新さの塊みたいな作品ですが、合計点で惜しくも3位です。それにしても中央値9点は凄い。
原義のようなロールプレイングゲームとして、斬新な感覚を上手くゲーム性に落とし込んでいるのも凄いです。
25位 WOLFALL
今作は難易度緩和のためのシステムが盛り込まれていて遊びやすくなっているなあと感じていたんですが、意外と伸びていませんでした。どうして。
BGMに合わせて美しい弾幕を張るというのは結構好きなんですが、あんまりそういうプレイヤーがいないんでしょうか。
29位 Anthy
here の作者さんであることを差っ引けたかは分かりませんが、差っ引いても短編として良い作品だったと思っています。斬新さが高いのはやってみれば分かります。
唯一の後悔は、ウディコン終了直後にV2のファイナルアップデートがあったらしいことです。やってから投票したかった。プレイしていたらもっと得点を上げていた自分が想像できる。
コトノリ
恒例の、このレベルでもう圏外なんだゾーンです。斬新さがちゃんと高い順位を取ってるんですが、合計点がそんなに高くならないパターンでしょうか。
文字を制限されると、多答を一つ答えるだけでも多答っぽくなるんだなあと目から鱗の気分で解いていました。あの絶妙に被るクイズ考えるのは大変そうですが。
未来よ心のままに
個人的に7位なので、個人順位との乖離が一番激しいかもしれません。斬新さが高いのは戦闘システムの設計上頷けるところで、それ以外があんまり入っていないのが意外でした。斬新さの合計点がランク外なところを見るに、恐らくプレイヤー数が少ないんでしょうか。プレイしてほしいんですが。
シナリオ面でも個人的に好きな人間賛歌が描かれていたので、もうちょっと評価されて欲しい。これは誰に対する願いなんですか。
後記
以上で長々と書いたレビュー及び感想について終わりたいと思います。
今年は様々な観点から『良い』と感じるゲームが多く、熱中したり心動かしたり感じ入ったりしつつ楽しめた年でした。
前のめりの面白さ「ビャッコーギャモン」、差し合いの極致「SIBLINGS」、絶対的RPG「DayDreamDreamer」、両輪の思考「ウラミコドク」、ダイス運の沼「文無し行商人の遺跡探索」、とっつきやすいローグライト「不屈のスペラ」、制御する戦略性「未来よ心のままに」。
今年のウディコンは、印象に残るゲームが多い場でした。
魂を揺さぶるようなシナリオも、芸術的なまでの演出も、やめられなくなる中毒性も、完成されたシステムも、これ以上ない空気感も、全てのアプローチが等しくゲームという媒体をもって面白さを享受させてくれました。
また、こうして出展した作品を楽しく遊べたのは、ひとえに制作者の方々のおかげです。改めてここに感謝の意を申し上げたいと思います。
次のウディコンがあればまた楽しめるであろうことを確信し、この文章を終えます。
補記: タイムスケジュール
おまけ。全作品をクリアしつつウディコンを終える場合、そのスケジュールってどうなっているのか気になる酔狂な方へ。
| 日数 | プレイしているゲーム | 備考 |
|---|---|---|
| 7/16 | 零落と紺碧の海神 | 毎回必ず1番から始めることにしています |
| 少女大猩猩 -その猩猩、凶暴につき- | ||
| 祟女 -TATARIME- | ||
| 怖がらないでよ僧侶さん | ||
| オミくじ | ||
| 7/17 | SIBLINGS | 番号順でやるつもりでしたが、言及が多くネタバレ踏みそうだったので先にプレイ |
| Forcelagoon2 因果律の少女 | ||
| 7/18 ~ 7/19 | Forcelagoon2 因果律の少女 | |
| 7/20 | メリカと野菜の剣士たち | |
| 7/21 | 群像物語~タコ型宇宙人と残された七日間~ | |
| 7/22 | ギフテッドワールド | この時点ではストーリークリアまで |
| みかど出現 | ||
| 7/23 | 竜と黄金の梨と焼け残り | この辺で60作品出そろったので、大まかなスケジュールを立てました |
| 不屈のスペラ | 大体1日4~6時間やれば終わる見積もりでした | |
| 煽り時計の誕生の旅 | 実際は土日込みで調整して平日3時間くらいが目安 | |
| プリティアックス外伝 ~斧姫~ | ||
| 7/24 | ウラミコドク | |
| 7/25 | ウラミコドク | このゲームが平日の二日未満で終わったのは、シンプルに楽しくて睡眠時間が削れたからです |
| めっちゃ危険なダンジョンだろうとみんなで潜れば怖くない | ||
| 7/26 | 前進中の迷い人他四種のミニゲーム | |
| ビャッコーギャモン | ||
| 7/27 | ビャッコーギャモン | |
| その日暮らしの冒険補償 | ||
| ECO2クエスト | ||
| 7/28 | ECO2クエスト | |
| 7/29 | 九色カーズレボリューション | |
| Alkersas | ||
| ウディダッシュ | ||
| コトノリ | ||
| 7/30 | マインのパズルでバトル | |
| 一人非零和有限確定無情報非ゲーム | ||
| DayDreamDreamer | ||
| 7/31 | DayDreamDreamer | この時点でノーマルエンド。これも楽しすぎて睡眠時間が消えました |
| 女神の迷宮 | ||
| 8/1 | 女神の迷宮 | |
| STARCHILD | ||
| 8/2 | STARCHILD | |
| オチル | ||
| アドリブ・ロール | ||
| 8/3 | ロロろくプラス | |
| 8/4 | BerriesWitch | |
| 睡蓮 | ||
| ヒーローの冒険 | ||
| 8/5 | エド王子の冒険 大地の精霊と邪悪な神 | |
| ~罠~狙われた仔共たち・・ | ボス倒せなくてこの時点では未クリア | |
| デジチューバー | ||
| 可愛い子と夏祭りに行きてえよなあ! | ||
| 8/6 | ショートファンタジー マージョのマジかるパニカル | |
| じゃんけんバトラー俺 | ||
| オカルトノート 土雲ガクレ編 | ||
| WOLFALL | ||
| 異界門事変 | ||
| 救済少年の終末 | ||
| 8/7 | 未来よ心のままに | ここからリアルイベントにより進捗が鈍りますが、休暇でもあるので多分イーブン |
| 8/8 | アリアとウィヴィと魔女の塔 | |
| 8/9 | アリアとウィヴィと魔女の塔 | 多分、想定に対して最もずれが大きかったゲームです。(3時間 → 8時間) |
| マスコット | ||
| 「財宝竜と四騎士」The sunset and breaking dawn King | ||
| 8/10 | Know Your Enemy, Know Yourself | |
| 一画面で成し遂げる地獄再興 | ||
| 亡者の行軍 Invasion from OtherSide | ||
| 8/11 | SICS(シックス)~特殊事件対策係~ | |
| 文無し行商人の遺跡探索 | ||
| 棺ふる海 | ||
| Anthy | ||
| 8/12 | カエルはカエる | |
| 死をきたい | ||
| 異世界ノ迷宮 | ここまで10作品ごとに評価していたので、最後にその辺の分散を吸収する意味で再検討フェーズを入れました | |
| 8/13 | ~罠~狙われた仔共たち・・ | 思いついたことがあったので試してクリアしました |
| 8/14 | DayDreamDreamer | トゥルーエンドを見ました |
| 8/15~8/16 | ギフテッドワールド | エンドロールまで到達して終了 |
今回は試みで原則番号順にやってみましたが、前半に触った作品がアプデされても恩恵がないのに対し、後半に触ってると恩恵があるあたりが若干気になりました。
「みかど出現」とか「竜と黄金の梨と焼け残りあたり」が、割と大きめに遊びやすくしていそうな雰囲気を感じています。ただ、そういう作品を全部再ダウンロードして確かめるのは現実的でないので見送っています。申し訳ない。
感想
以下はもはや文章になっていないかもしれない感想です。ご笑覧ください。
今ウディコンはRPGが多種多様に取り揃えられていたことと、SIBLINGSとビャッコーギャモンというそれぞれ別軸で感情を揺さぶられる作品に出会えたことで、いたく満足しています。
この満足感が無くなった時というか、満足感を感じる心が摩耗して死んだ時がウディコンのゲームをやらなくなる時だと思うんですが、今の所は正常稼働しているようです。私の心が死ぬのが先か、ウディコンが終わるのが先か。今の所、心が摩耗する予定は特にありませんが、感受性は薄れていくような気がしています。
前ウディコンが割と滑り込みで遊んでいたところがあったので、今回はスケジュールをちゃんと立てて遊んでみました。
ティアキン発売日から1か月くらいやってクリアしていたBotWとティアキンのプレイ時間を勘案すると、筆者が全てを諦めると平日6時間くらいはゲームできることが分かっていたので、そのコースも覚悟していましたが、案外常識的な時間で終わったので安心しています。ウラミコドクとDayDreamDreamerは面白すぎて生活時間をぶち壊してきましたが、それ以外は平常運転で終えられました。個人的には満足。
デッキ構築ローグライク/トがTOP5に3作品入るという面白い年でしたね。それぞれ違った魅力があるというのも面白いです。被ってない。
個人的には文無しがクリアできるかどうかわからないバランスであることに楽しさを覚えるのに対し、スペラがクリアできるようになっているバランスに楽しさを覚えているので変な感じがしています。どっちに振っても上手くバランスすれば面白くなるんですね。
なお、初心者に対してはスペラも良いんですがメリカが推せるかなと思っていて、デッキ構築の融通が利くというか、ペナルティの少なさのおかげでだいぶ導入として良いんじゃないかなと感じています。文無しは一回コテンパンにやられる覚悟があるなら最初に選んでも良いかもしれない。
今回の個人的な順位としては、1位が4つくらいあって、TOP10が20個くらいあります。欲張りですね。
なお、点数差は付いてるかもしれませんが、気持ちと合計点数がちょくちょく乖離していることはあるので、実は総合の並びにはなっていません。1位4つはさすがに上の4つですが。
総合点と気持ちの乖離は気になってはいますが、そのためにその他点をいじると色々破綻するので、色々苦心したうえでのこの得点表となっています。得点付けるの烏滸がましい以前に、得点付けるのが難しすぎる。
ウディコンの作品を全部クリアするという、何がしたいかよくわからない行為に及んでいるわけですが、これは筆者が底の底からクリアラーであることに起因します。クリアすることに強いモチベーションがあるので、よっぽどのことがない限り辞めるという選択肢が頭の中に存在しません。
例えば年間100作品くらいSteamのゲームを遊んでいますが、クリアを諦めたのは毎年2作品とかそこらくらいになります。この自分でも良く分からないモチベーションがあると、全ての作品をクリアしようかなあという気持ちになれます。
その上で気にしているのは、いわゆるnot for meな作品についてです。筆者は雑食とは言えど好みはあるので、そのあたりでどうしても得点に偏りが出ることは否めません。まあそこは大数の法則で上手いこと正規化されるでしょうくらいの気持ちで得点を付けていますが、この感覚が変わったら何か考える必要があるんだろうなあと漠然と考えています。
得点表を眺めてみた感じでは、どうにも筆者の付けている得点は長編を評価し、短編あるいはミニゲームにキャップしている印象があります。あとはRPGとアクションが割と好きで、ローグライトやパズルのような思考を要求するのも結構好きみたいですね。分かりやすい。
今回は試みで5作品ずつ公開しようかと思っているんですが、5作品ごとに校正しているので効率悪い気がしてきました。しかし、全部書いてからだと結構間が開くのと、単純にモチベーションが続かないという問題があります。
去年やった半分書くくらいが良い塩梅かもしれません。
Q. 公開順、なんで4番からAnthyに飛んだんですか。
A. Anthy v3の他の人の感想が見たくてしょうがなくなったためです。感想を書き終えるまで、そのゲームの別の人の感想を出来るだけ見ないようにしています。
しかしネットの海にそんなにAnthyの情報は落ちていませんでしたね。もうちょっと軽率に考察を書いても良いと思いますよ。私は軽率に書きました。
筆者は感想なり気になる点に遊んでいて厳しかったところを書いていることもありますが、これは筆者が感じたものというだけなので、それ以上の意味はありません。何人にも指摘されていたらもしかしたら汎的な話かもしれませんが、それでも作者さんがそれに意義を見出しているならそのままのほうが良いのかなとも思っています。
何だかんだ書いてますが、筆者は悪い点全部潰して丸いゲームより、悪い点は色々あるかもしれないけどとにかく尖ってるゲームのほうが好きなので。
間が開いたのは、感想の話題を目にして書き方このままでいいのかなと考えたのが半分、スマブラでなぜかクラウドのモチベが上がって遊んでいたのが半分です。まあ感想も一つの表現としてお目こぼしいただこうという図々しい結論に至ったので、特にスタンスは変わってません。
さらに間が開いたのは色々と忙しかったからになります。感想は全部書き終わっていて、レビューはまだですが何とか書き終わる目途は立ったのでぼちぼち更新していこうと思います。決してシレンやってたせいで遅れたわけではありません。
5作品ずつ取り上げていくのを完走した感想なんですが、やっぱり一気にやる方が気持ちが楽だなという感じです。こういうのは勢いで書いたほうが楽で、何作かずつやると仕事というか作業みたいになってしまいます。結局Trello使って管理してしまいましたし。
次回があれば、もっと文字数少なくして勢いで書きあげたい所存。今年は16万字強で、一番文字数が多いのがDayDreamDreamerで7600字、次いで文無し行商人の遺跡探索とビャッコーギャモンが6000字くらいです。平均して2600字前後。なんで去年より増えてるんだ。